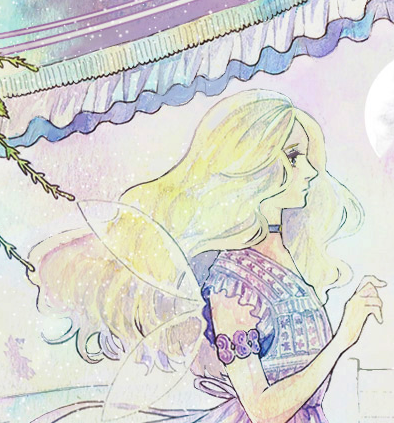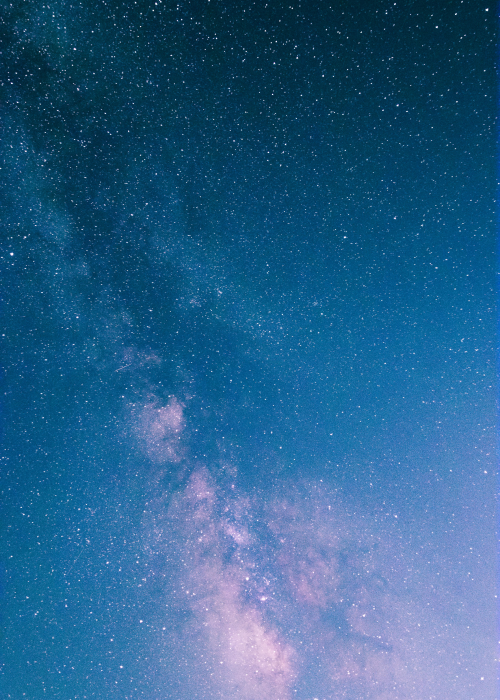夏の小さな約束
ー/ー真夏の陽射しが容赦なく照りつける午後、僕は一人、見知らぬ田舎道を歩いていた。足元に舞い上がる土埃と、どこからともなく漂ってくる草の匂い。祖父母の家に預けられて三日が過ぎた頃のことである。
東京のマンションでは、隣室の住人の顔さえ知らずに過ごしていた。学校という名の小さな社会でも、僕はいつも輪の外側にいた。休み時間には窓際の席で本のページをめくるか、ガラス越しに流れる雲を眺めている。給食の時間も、誰かと言葉を交わすでもなく、ただ黙々と食べていた。
夏休みが始まっても、僕を誘う声は聞こえてこなかった。同い年ぐらいの人たちが友人同士で海辺や花火大会に向かい歓声を上げたりする様子を、僕はガラス窓の向こうから眺めているだけだった。母がそんな僕を案じて、この田舎へと送り出したのであろう。
「少しは外の空気を吸いなさい」
そう促されて重い腰を上げたものの、場所が変わったところで、孤独は孤独のままだった。田舎の空気は確かに気持ちよかったけれど、僕の心の中の寂しさは変わらなかった。ここでも結局、誰とも話さずに一人で歩いているんだな、と思うと少し悲しくなった。
「あら」
道の向こうから、純白のワンピースに身を包んだ少女が現れた。僕と同年代だろうか。風に舞う長い髪、手には小さな虫取り網。まるで昔話の挿絵から抜け出してきたような、幻想的な姿だった。
「こんにちは」
少女は人懐っこい笑顔で声をかけてきた。
「こんにちは…」
僕は緊張して小さな声で答えた。
「どこから来たの?」
「東京から…」
「そうなんだ。一人?」
「うん」
少女は首を傾げて、僕の顔をじっと見つめた。
「なんだか寂しそうね。一緒に遊ばない?」
虫取り網を振りながら、少女は言った。同世代の子に遊びに誘われるなんて、記憶になかった。胸の奥で何かが弾んだ。こんなふうに誰かから声をかけてもらえるなんて、夢みたいだった。でも同時に、どうしていいか分からなくて緊張もした。
「僕、虫取りとかしたことないけど…」
「大丈夫、教えてあげる。名前は?」
「まさる」
「まさるくんね。よろしく」
僕は少女の名前を聞こうとしたが、なぜか彼女は教えてくれなかった。でも、不思議と気にならなかった。それよりも、誰かと一緒にいられることが嬉しくて仕方なかった。
それから僕たちは毎日、この田舎道で会うようになった。少女は虫の捕まえ方を教えてくれたり、川で魚を見つけたり、田んぼの道を歩いたりした。生まれて初めて、心から楽しいと思える時間を過ごした。友達と遊ぶってこんなに楽しいことなんだ、と僕は感動していた。
「明日もここで会おうね」
「うん」
毎日午後三時、この場所で待ち合わせることが習慣になった。少女はいつも、約束の時間より早くそこにいた。
一週間ほど経った頃、僕は胸の内を打ち明けた。少女といると安心して、自然と本当の気持ちを話したくなったのだ。
「僕ね、東京では友達がいないんだ」
「そうなの?」
「僕から話すのが苦手で、人と話すきっかけがあまりないから、いつも一人で…」
そう言いながら、僕は少し恥ずかしくなった。でも、少女なら分かってくれるような気がした。
少女は僕の隣に座って、じっと聞いてくれた。
「寂しいでしょう?」
「うん…とても」
僕の目に涙がにじんできた。誰かに気持ちを分かってもらえて、嬉しいような、悲しいような複雑な気持ちだった。
「君は違うよ。君は僕に話しかけてくれた。僕、誰かから話しかけてもらったのは初めてかも」
そう言うと、僕の心が少し軽くなった気がした。
「そうなの?でも、まさるくんはお話上手よ」
少女は微笑んだ。その笑顔には夕日のような温かさがあった。
「きっと東京にも、まさるくんと友達になりたいって思ってる子がいるわ。でも、みんな話しかけるきっかけが分からないのかもしれない」
「本当かな」
僕は半信半疑だった。でも、少女が言うと本当のような気がしてきた。
「本当よ。人はみんな、誰かとつながりたいと思ってる。でも、最初の一歩が怖いの。まさるくんが勇気を出して話しかけてみれば、きっと友達ができるわ」
少女の言葉は、僕の心に温かく響いた。初めて誰かに理解してもらえた気がした。今まで感じたことのない、希望のような気持ちが胸の奥に芽生えた。
「ありがとう。君がいてくれて、僕はもう寂しくない」
「私も、まさるくんと会えて嬉しい」
それから僕たちの関係はもっと深くなった。少女は僕の話を最後まで聞いてくれて、いつも優しい言葉をかけてくれた。僕は初めて、心から信頼できる友達ができたと思った。
夏休みが終わり、東京に帰る日がやってきた。僕は別れが辛くて仕方なかった。
「来年も来るから」
「本当?」
「本当だよ」
少女は少し寂しそうな顔をした。僕も同じ気持ちだった。
翌年の六年生の夏、僕は再び祖父母の家を訪れた。少女は約束通り、あの場所で僕を待っていた。前の年と変わらない笑顔で。僕は嬉しくて駆け寄った。
「まさるくん、来てくれたのね」
「約束したからね」
その夏も、僕たちは毎日同じ場所で過ごした。僕は東京で友達ができたことを報告した。少女のアドバイスのおかげで、勇気を出してクラスメイトに話しかけることができるようになったのだ。
「やっぱりね。まさるくんならきっとできると思ってた」
少女は僕のことのように喜んでくれた。僕は嬉しくて、胸がいっぱいになった。
それから何日かして今年も東京に帰る日が近づいてきた。今日も二人はいつも通りに川辺で遊んでいたが、その時に彼女がこう言った。
「いつまでも友達でいてね」
「もちろん。来年の夏も、またあの場所で会おう」
僕は彼女とそんな約束したが、今までみたことない満面の笑みの表情していた。普段は見せることない表情をしていたので少し驚いた気持ちもあったが、それと同時に心の底から幸せという気持ちも沸き上がってきたのだ。
だが翌年、中学生になると部活動に時間を取られるようになった。友人たちとの付き合いも増え、夏休みは合宿や遊びの予定で埋まっていく。祖父母の家を訪れる機会は失われ、気づけば少女との約束は記憶の彼方に埋もれていた。
時は流れていき、高校、大学、就職で忙しい日々の中で、あの夏の記憶は色あせていった。
そして二十八の歳を迎えた熱い夏の日、僕の元に祖母の訃報が届いた。
久しぶりに足を向けた町は、記憶の中の面影を失っていた。商店街には錆びついたシャッターが並び、人影はまばら。田んぼは荒れ地と化し、空き家が点在している。かつて生命力に満ちていた町は、まるで時の流れに取り残されたように静寂に包まれていた。
葬儀を終えた夕刻、僕は不意に幼い日々を思い返していた。毎日会っていた少女のこと。交わした約束のこと。
「そういえば、あの子は今どうしているのだろう」
僕はあの場所へと足を向けた。田舎道は舗装され、小川は細々とした流れに変わっていた。それでも、あの場所はすぐに見つけることができた。
そして、そこに彼女がいた。十数年の歳月など存在しなかったかのような、あの日と変わらぬ白いワンピース姿で。
「まさるくん」
少女は振り返って微笑んだ。だが、その姿はかすかに透けて見えた。
「君は…」
「ずっと待ってたの」
僕は現実を疑った。
「でも、君は…どうして昔のままなんだ」
少女はうつむきながら切なそうな表情を浮かべ、何も喋ろうとしなかった。
その時、僕は周囲を見渡した。錆びついた看板、崩れかけた塀、誰も住まなくなった家々。そして消えゆく少女の姿。町の衰退と、彼女の透明度がシンクロしていると思った。
「君は…まさか…」
僕の言葉に、少女は小さく頷いた。
「もうすぐ私は消える」
「えっ、なんで…」
「みんな、ここから去っていくから」
そして少女は昨日の出来事のように過去の話を喋り始めた。
「昔、ここに鉄道が開通したときは、とても賑やかだった。子どもたちの笑い声が響いて、商店街には人があふれていた。大変な時代もあったけど、みんなで支え合って生きていた。大きな争いの後の復興の時代は、大きな成長の波に乗って多くの若者が都会へ出て行ったけれど、それでも盆や正月には生まれ育った場所に帰ってきた」
語る物語は、彼女の年齢では体験し得ない過去の出来事だった。
「その時代に比べて今は…」
少女は深い悲しみの表情で町の方を見つめた。その瞳には、長い年月をかけて失われていったものへの哀愁が浮かんでいた。僕も少女の視線を追って振り返ると、夕暮れに染まった寂しい町並みが目に入った。僕の胸に、言いようのない切なさが込み上げてきた。
そして少女の姿がさらに薄れていく。
「でも、まさるくんとの思い出は、本当に宝物だった。友達になれて、私は幸せだった」
「僕も…君がいてくれて、本当に救われた」
「またここに来てくれて、ありがとう」
少女の姿は、もはやぼんやりとしか認識できなくなっていた。
「待って」
僕は手を伸ばしたが、それは空気を掴むだけだった。
「いつまでも、友達だよ」
そう僕が言うと風が吹いて、少女の姿は跡形もなく消えた。僕は一人、夕暮れの田舎道に佇んでいた。
帰りの電車の窓に映る僕の顔を見つめながら、僕は考え続けていた。
あの約束は些細なものだったかもしれない。しかし、それを待つ人にとっては、決して些細なものではなかった。少女にとって、僕との約束は代え難い宝だったのだ。
日々に追われる中で、僕は少女のことを忘れてしまった。
それから僕は一つのことを考えていた。携帯電話が普及した現代では、来るか来ないのかが分からない人を待ち続けるということが無くなってきている。約束の時間に遅れそうになれば連絡を取り、直前に会えなくなればこれも連絡し別の日に約束し直す。待ち合わせの時間に来ない相手をひたすら待つなど、もはや考えられない。待ち続けるという行為自体が過去の遺物となっているのかもしれない。
けれども、少女は待っていた。十数年もの間、あの場所で。僕がまた来ると信じて。
車窓を流れる風景を眺めながら、僕は心の中で呟いた。
「ごめんなさい。そして、ありがとう」
夏の小さな約束。それは消えゆく町と、一人の少年との間に結ばれた、小さくて大きな絆の物語だった。
僕はその日から、人との約束を大切にするようになった。どんなに小さな約束でも、それを待っている人がいる。そのことを、僕は決して忘れない…
東京のマンションでは、隣室の住人の顔さえ知らずに過ごしていた。学校という名の小さな社会でも、僕はいつも輪の外側にいた。休み時間には窓際の席で本のページをめくるか、ガラス越しに流れる雲を眺めている。給食の時間も、誰かと言葉を交わすでもなく、ただ黙々と食べていた。
夏休みが始まっても、僕を誘う声は聞こえてこなかった。同い年ぐらいの人たちが友人同士で海辺や花火大会に向かい歓声を上げたりする様子を、僕はガラス窓の向こうから眺めているだけだった。母がそんな僕を案じて、この田舎へと送り出したのであろう。
「少しは外の空気を吸いなさい」
そう促されて重い腰を上げたものの、場所が変わったところで、孤独は孤独のままだった。田舎の空気は確かに気持ちよかったけれど、僕の心の中の寂しさは変わらなかった。ここでも結局、誰とも話さずに一人で歩いているんだな、と思うと少し悲しくなった。
「あら」
道の向こうから、純白のワンピースに身を包んだ少女が現れた。僕と同年代だろうか。風に舞う長い髪、手には小さな虫取り網。まるで昔話の挿絵から抜け出してきたような、幻想的な姿だった。
「こんにちは」
少女は人懐っこい笑顔で声をかけてきた。
「こんにちは…」
僕は緊張して小さな声で答えた。
「どこから来たの?」
「東京から…」
「そうなんだ。一人?」
「うん」
少女は首を傾げて、僕の顔をじっと見つめた。
「なんだか寂しそうね。一緒に遊ばない?」
虫取り網を振りながら、少女は言った。同世代の子に遊びに誘われるなんて、記憶になかった。胸の奥で何かが弾んだ。こんなふうに誰かから声をかけてもらえるなんて、夢みたいだった。でも同時に、どうしていいか分からなくて緊張もした。
「僕、虫取りとかしたことないけど…」
「大丈夫、教えてあげる。名前は?」
「まさる」
「まさるくんね。よろしく」
僕は少女の名前を聞こうとしたが、なぜか彼女は教えてくれなかった。でも、不思議と気にならなかった。それよりも、誰かと一緒にいられることが嬉しくて仕方なかった。
それから僕たちは毎日、この田舎道で会うようになった。少女は虫の捕まえ方を教えてくれたり、川で魚を見つけたり、田んぼの道を歩いたりした。生まれて初めて、心から楽しいと思える時間を過ごした。友達と遊ぶってこんなに楽しいことなんだ、と僕は感動していた。
「明日もここで会おうね」
「うん」
毎日午後三時、この場所で待ち合わせることが習慣になった。少女はいつも、約束の時間より早くそこにいた。
一週間ほど経った頃、僕は胸の内を打ち明けた。少女といると安心して、自然と本当の気持ちを話したくなったのだ。
「僕ね、東京では友達がいないんだ」
「そうなの?」
「僕から話すのが苦手で、人と話すきっかけがあまりないから、いつも一人で…」
そう言いながら、僕は少し恥ずかしくなった。でも、少女なら分かってくれるような気がした。
少女は僕の隣に座って、じっと聞いてくれた。
「寂しいでしょう?」
「うん…とても」
僕の目に涙がにじんできた。誰かに気持ちを分かってもらえて、嬉しいような、悲しいような複雑な気持ちだった。
「君は違うよ。君は僕に話しかけてくれた。僕、誰かから話しかけてもらったのは初めてかも」
そう言うと、僕の心が少し軽くなった気がした。
「そうなの?でも、まさるくんはお話上手よ」
少女は微笑んだ。その笑顔には夕日のような温かさがあった。
「きっと東京にも、まさるくんと友達になりたいって思ってる子がいるわ。でも、みんな話しかけるきっかけが分からないのかもしれない」
「本当かな」
僕は半信半疑だった。でも、少女が言うと本当のような気がしてきた。
「本当よ。人はみんな、誰かとつながりたいと思ってる。でも、最初の一歩が怖いの。まさるくんが勇気を出して話しかけてみれば、きっと友達ができるわ」
少女の言葉は、僕の心に温かく響いた。初めて誰かに理解してもらえた気がした。今まで感じたことのない、希望のような気持ちが胸の奥に芽生えた。
「ありがとう。君がいてくれて、僕はもう寂しくない」
「私も、まさるくんと会えて嬉しい」
それから僕たちの関係はもっと深くなった。少女は僕の話を最後まで聞いてくれて、いつも優しい言葉をかけてくれた。僕は初めて、心から信頼できる友達ができたと思った。
夏休みが終わり、東京に帰る日がやってきた。僕は別れが辛くて仕方なかった。
「来年も来るから」
「本当?」
「本当だよ」
少女は少し寂しそうな顔をした。僕も同じ気持ちだった。
翌年の六年生の夏、僕は再び祖父母の家を訪れた。少女は約束通り、あの場所で僕を待っていた。前の年と変わらない笑顔で。僕は嬉しくて駆け寄った。
「まさるくん、来てくれたのね」
「約束したからね」
その夏も、僕たちは毎日同じ場所で過ごした。僕は東京で友達ができたことを報告した。少女のアドバイスのおかげで、勇気を出してクラスメイトに話しかけることができるようになったのだ。
「やっぱりね。まさるくんならきっとできると思ってた」
少女は僕のことのように喜んでくれた。僕は嬉しくて、胸がいっぱいになった。
それから何日かして今年も東京に帰る日が近づいてきた。今日も二人はいつも通りに川辺で遊んでいたが、その時に彼女がこう言った。
「いつまでも友達でいてね」
「もちろん。来年の夏も、またあの場所で会おう」
僕は彼女とそんな約束したが、今までみたことない満面の笑みの表情していた。普段は見せることない表情をしていたので少し驚いた気持ちもあったが、それと同時に心の底から幸せという気持ちも沸き上がってきたのだ。
だが翌年、中学生になると部活動に時間を取られるようになった。友人たちとの付き合いも増え、夏休みは合宿や遊びの予定で埋まっていく。祖父母の家を訪れる機会は失われ、気づけば少女との約束は記憶の彼方に埋もれていた。
時は流れていき、高校、大学、就職で忙しい日々の中で、あの夏の記憶は色あせていった。
そして二十八の歳を迎えた熱い夏の日、僕の元に祖母の訃報が届いた。
久しぶりに足を向けた町は、記憶の中の面影を失っていた。商店街には錆びついたシャッターが並び、人影はまばら。田んぼは荒れ地と化し、空き家が点在している。かつて生命力に満ちていた町は、まるで時の流れに取り残されたように静寂に包まれていた。
葬儀を終えた夕刻、僕は不意に幼い日々を思い返していた。毎日会っていた少女のこと。交わした約束のこと。
「そういえば、あの子は今どうしているのだろう」
僕はあの場所へと足を向けた。田舎道は舗装され、小川は細々とした流れに変わっていた。それでも、あの場所はすぐに見つけることができた。
そして、そこに彼女がいた。十数年の歳月など存在しなかったかのような、あの日と変わらぬ白いワンピース姿で。
「まさるくん」
少女は振り返って微笑んだ。だが、その姿はかすかに透けて見えた。
「君は…」
「ずっと待ってたの」
僕は現実を疑った。
「でも、君は…どうして昔のままなんだ」
少女はうつむきながら切なそうな表情を浮かべ、何も喋ろうとしなかった。
その時、僕は周囲を見渡した。錆びついた看板、崩れかけた塀、誰も住まなくなった家々。そして消えゆく少女の姿。町の衰退と、彼女の透明度がシンクロしていると思った。
「君は…まさか…」
僕の言葉に、少女は小さく頷いた。
「もうすぐ私は消える」
「えっ、なんで…」
「みんな、ここから去っていくから」
そして少女は昨日の出来事のように過去の話を喋り始めた。
「昔、ここに鉄道が開通したときは、とても賑やかだった。子どもたちの笑い声が響いて、商店街には人があふれていた。大変な時代もあったけど、みんなで支え合って生きていた。大きな争いの後の復興の時代は、大きな成長の波に乗って多くの若者が都会へ出て行ったけれど、それでも盆や正月には生まれ育った場所に帰ってきた」
語る物語は、彼女の年齢では体験し得ない過去の出来事だった。
「その時代に比べて今は…」
少女は深い悲しみの表情で町の方を見つめた。その瞳には、長い年月をかけて失われていったものへの哀愁が浮かんでいた。僕も少女の視線を追って振り返ると、夕暮れに染まった寂しい町並みが目に入った。僕の胸に、言いようのない切なさが込み上げてきた。
そして少女の姿がさらに薄れていく。
「でも、まさるくんとの思い出は、本当に宝物だった。友達になれて、私は幸せだった」
「僕も…君がいてくれて、本当に救われた」
「またここに来てくれて、ありがとう」
少女の姿は、もはやぼんやりとしか認識できなくなっていた。
「待って」
僕は手を伸ばしたが、それは空気を掴むだけだった。
「いつまでも、友達だよ」
そう僕が言うと風が吹いて、少女の姿は跡形もなく消えた。僕は一人、夕暮れの田舎道に佇んでいた。
帰りの電車の窓に映る僕の顔を見つめながら、僕は考え続けていた。
あの約束は些細なものだったかもしれない。しかし、それを待つ人にとっては、決して些細なものではなかった。少女にとって、僕との約束は代え難い宝だったのだ。
日々に追われる中で、僕は少女のことを忘れてしまった。
それから僕は一つのことを考えていた。携帯電話が普及した現代では、来るか来ないのかが分からない人を待ち続けるということが無くなってきている。約束の時間に遅れそうになれば連絡を取り、直前に会えなくなればこれも連絡し別の日に約束し直す。待ち合わせの時間に来ない相手をひたすら待つなど、もはや考えられない。待ち続けるという行為自体が過去の遺物となっているのかもしれない。
けれども、少女は待っていた。十数年もの間、あの場所で。僕がまた来ると信じて。
車窓を流れる風景を眺めながら、僕は心の中で呟いた。
「ごめんなさい。そして、ありがとう」
夏の小さな約束。それは消えゆく町と、一人の少年との間に結ばれた、小さくて大きな絆の物語だった。
僕はその日から、人との約束を大切にするようになった。どんなに小さな約束でも、それを待っている人がいる。そのことを、僕は決して忘れない…
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
真夏の陽射しが容赦なく照りつける午後、僕は一人、見知らぬ田舎道を歩いていた。足元に舞い上がる土埃と、どこからともなく漂ってくる草の匂い。祖父母の家に預けられて三日が過ぎた頃のことである。
東京のマンションでは、隣室の住人の顔さえ知らずに過ごしていた。学校という名の小さな社会でも、僕はいつも輪の外側にいた。休み時間には窓際の席で本のページをめくるか、ガラス越しに流れる雲を眺めている。給食の時間も、誰かと言葉を交わすでもなく、ただ黙々と食べていた。
夏休みが始まっても、僕を誘う声は聞こえてこなかった。同い年ぐらいの人たちが友人同士で海辺や花火大会に向かい歓声を上げたりする様子を、僕はガラス窓の向こうから眺めているだけだった。母がそんな僕を案じて、この田舎へと送り出したのであろう。
「少しは外の空気を吸いなさい」
そう促されて重い腰を上げたものの、場所が変わったところで、孤独は孤独のままだった。田舎の空気は確かに気持ちよかったけれど、僕の心の中の寂しさは変わらなかった。ここでも結局、誰とも話さずに一人で歩いているんだな、と思うと少し悲しくなった。
「あら」
道の向こうから、純白のワンピースに身を包んだ少女が現れた。僕と同年代だろうか。風に舞う長い髪、手には小さな虫取り網。まるで昔話の挿絵から抜け出してきたような、幻想的な姿だった。
「こんにちは」
少女は人懐っこい笑顔で声をかけてきた。
「こんにちは…」
僕は緊張して小さな声で答えた。
「どこから来たの?」
「東京から…」
「そうなんだ。一人?」
「うん」
少女は首を傾げて、僕の顔をじっと見つめた。
「なんだか寂しそうね。一緒に遊ばない?」
虫取り網を振りながら、少女は言った。同世代の子に遊びに誘われるなんて、記憶になかった。胸の奥で何かが弾んだ。こんなふうに誰かから声をかけてもらえるなんて、夢みたいだった。でも同時に、どうしていいか分からなくて緊張もした。
「僕、虫取りとかしたことないけど…」
「大丈夫、教えてあげる。名前は?」
「まさる」
「まさるくんね。よろしく」
僕は少女の名前を聞こうとしたが、なぜか彼女は教えてくれなかった。でも、不思議と気にならなかった。それよりも、誰かと一緒にいられることが嬉しくて仕方なかった。
東京のマンションでは、隣室の住人の顔さえ知らずに過ごしていた。学校という名の小さな社会でも、僕はいつも輪の外側にいた。休み時間には窓際の席で本のページをめくるか、ガラス越しに流れる雲を眺めている。給食の時間も、誰かと言葉を交わすでもなく、ただ黙々と食べていた。
夏休みが始まっても、僕を誘う声は聞こえてこなかった。同い年ぐらいの人たちが友人同士で海辺や花火大会に向かい歓声を上げたりする様子を、僕はガラス窓の向こうから眺めているだけだった。母がそんな僕を案じて、この田舎へと送り出したのであろう。
「少しは外の空気を吸いなさい」
そう促されて重い腰を上げたものの、場所が変わったところで、孤独は孤独のままだった。田舎の空気は確かに気持ちよかったけれど、僕の心の中の寂しさは変わらなかった。ここでも結局、誰とも話さずに一人で歩いているんだな、と思うと少し悲しくなった。
「あら」
道の向こうから、純白のワンピースに身を包んだ少女が現れた。僕と同年代だろうか。風に舞う長い髪、手には小さな虫取り網。まるで昔話の挿絵から抜け出してきたような、幻想的な姿だった。
「こんにちは」
少女は人懐っこい笑顔で声をかけてきた。
「こんにちは…」
僕は緊張して小さな声で答えた。
「どこから来たの?」
「東京から…」
「そうなんだ。一人?」
「うん」
少女は首を傾げて、僕の顔をじっと見つめた。
「なんだか寂しそうね。一緒に遊ばない?」
虫取り網を振りながら、少女は言った。同世代の子に遊びに誘われるなんて、記憶になかった。胸の奥で何かが弾んだ。こんなふうに誰かから声をかけてもらえるなんて、夢みたいだった。でも同時に、どうしていいか分からなくて緊張もした。
「僕、虫取りとかしたことないけど…」
「大丈夫、教えてあげる。名前は?」
「まさる」
「まさるくんね。よろしく」
僕は少女の名前を聞こうとしたが、なぜか彼女は教えてくれなかった。でも、不思議と気にならなかった。それよりも、誰かと一緒にいられることが嬉しくて仕方なかった。
それから僕たちは毎日、この田舎道で会うようになった。少女は虫の捕まえ方を教えてくれたり、川で魚を見つけたり、田んぼの道を歩いたりした。生まれて初めて、心から楽しいと思える時間を過ごした。友達と遊ぶってこんなに楽しいことなんだ、と僕は感動していた。
「明日もここで会おうね」
「うん」
毎日午後三時、この場所で待ち合わせることが習慣になった。少女はいつも、約束の時間より早くそこにいた。
一週間ほど経った頃、僕は胸の内を打ち明けた。少女といると安心して、自然と本当の気持ちを話したくなったのだ。
「僕ね、東京では友達がいないんだ」
「そうなの?」
「僕から話すのが苦手で、人と話すきっかけがあまりないから、いつも一人で…」
そう言いながら、僕は少し恥ずかしくなった。でも、少女なら分かってくれるような気がした。
少女は僕の隣に座って、じっと聞いてくれた。
「寂しいでしょう?」
「うん…とても」
僕の目に涙がにじんできた。誰かに気持ちを分かってもらえて、嬉しいような、悲しいような複雑な気持ちだった。
「君は違うよ。君は僕に話しかけてくれた。僕、誰かから話しかけてもらったのは初めてかも」
そう言うと、僕の心が少し軽くなった気がした。
「そうなの?でも、まさるくんはお話上手よ」
少女は微笑んだ。その笑顔には夕日のような温かさがあった。
「きっと東京にも、まさるくんと友達になりたいって思ってる子がいるわ。でも、みんな話しかけるきっかけが分からないのかもしれない」
「本当かな」
僕は半信半疑だった。でも、少女が言うと本当のような気がしてきた。
「本当よ。人はみんな、誰かとつながりたいと思ってる。でも、最初の一歩が怖いの。まさるくんが勇気を出して話しかけてみれば、きっと友達ができるわ」
少女の言葉は、僕の心に温かく響いた。初めて誰かに理解してもらえた気がした。今まで感じたことのない、希望のような気持ちが胸の奥に芽生えた。
「ありがとう。君がいてくれて、僕はもう寂しくない」
「私も、まさるくんと会えて嬉しい」
それから僕たちの関係はもっと深くなった。少女は僕の話を最後まで聞いてくれて、いつも優しい言葉をかけてくれた。僕は初めて、心から信頼できる友達ができたと思った。
夏休みが終わり、東京に帰る日がやってきた。僕は別れが辛くて仕方なかった。
「来年も来るから」
「本当?」
「本当だよ」
少女は少し寂しそうな顔をした。僕も同じ気持ちだった。
「明日もここで会おうね」
「うん」
毎日午後三時、この場所で待ち合わせることが習慣になった。少女はいつも、約束の時間より早くそこにいた。
一週間ほど経った頃、僕は胸の内を打ち明けた。少女といると安心して、自然と本当の気持ちを話したくなったのだ。
「僕ね、東京では友達がいないんだ」
「そうなの?」
「僕から話すのが苦手で、人と話すきっかけがあまりないから、いつも一人で…」
そう言いながら、僕は少し恥ずかしくなった。でも、少女なら分かってくれるような気がした。
少女は僕の隣に座って、じっと聞いてくれた。
「寂しいでしょう?」
「うん…とても」
僕の目に涙がにじんできた。誰かに気持ちを分かってもらえて、嬉しいような、悲しいような複雑な気持ちだった。
「君は違うよ。君は僕に話しかけてくれた。僕、誰かから話しかけてもらったのは初めてかも」
そう言うと、僕の心が少し軽くなった気がした。
「そうなの?でも、まさるくんはお話上手よ」
少女は微笑んだ。その笑顔には夕日のような温かさがあった。
「きっと東京にも、まさるくんと友達になりたいって思ってる子がいるわ。でも、みんな話しかけるきっかけが分からないのかもしれない」
「本当かな」
僕は半信半疑だった。でも、少女が言うと本当のような気がしてきた。
「本当よ。人はみんな、誰かとつながりたいと思ってる。でも、最初の一歩が怖いの。まさるくんが勇気を出して話しかけてみれば、きっと友達ができるわ」
少女の言葉は、僕の心に温かく響いた。初めて誰かに理解してもらえた気がした。今まで感じたことのない、希望のような気持ちが胸の奥に芽生えた。
「ありがとう。君がいてくれて、僕はもう寂しくない」
「私も、まさるくんと会えて嬉しい」
それから僕たちの関係はもっと深くなった。少女は僕の話を最後まで聞いてくれて、いつも優しい言葉をかけてくれた。僕は初めて、心から信頼できる友達ができたと思った。
夏休みが終わり、東京に帰る日がやってきた。僕は別れが辛くて仕方なかった。
「来年も来るから」
「本当?」
「本当だよ」
少女は少し寂しそうな顔をした。僕も同じ気持ちだった。
翌年の六年生の夏、僕は再び祖父母の家を訪れた。少女は約束通り、あの場所で僕を待っていた。前の年と変わらない笑顔で。僕は嬉しくて駆け寄った。
「まさるくん、来てくれたのね」
「約束したからね」
その夏も、僕たちは毎日同じ場所で過ごした。僕は東京で友達ができたことを報告した。少女のアドバイスのおかげで、勇気を出してクラスメイトに話しかけることができるようになったのだ。
「やっぱりね。まさるくんならきっとできると思ってた」
少女は僕のことのように喜んでくれた。僕は嬉しくて、胸がいっぱいになった。
それから何日かして今年も東京に帰る日が近づいてきた。今日も二人はいつも通りに川辺で遊んでいたが、その時に彼女がこう言った。
「いつまでも友達でいてね」
「もちろん。来年の夏も、またあの場所で会おう」
僕は彼女とそんな約束したが、今までみたことない満面の笑みの表情していた。普段は見せることない表情をしていたので少し驚いた気持ちもあったが、それと同時に心の底から幸せという気持ちも沸き上がってきたのだ。
「まさるくん、来てくれたのね」
「約束したからね」
その夏も、僕たちは毎日同じ場所で過ごした。僕は東京で友達ができたことを報告した。少女のアドバイスのおかげで、勇気を出してクラスメイトに話しかけることができるようになったのだ。
「やっぱりね。まさるくんならきっとできると思ってた」
少女は僕のことのように喜んでくれた。僕は嬉しくて、胸がいっぱいになった。
それから何日かして今年も東京に帰る日が近づいてきた。今日も二人はいつも通りに川辺で遊んでいたが、その時に彼女がこう言った。
「いつまでも友達でいてね」
「もちろん。来年の夏も、またあの場所で会おう」
僕は彼女とそんな約束したが、今までみたことない満面の笑みの表情していた。普段は見せることない表情をしていたので少し驚いた気持ちもあったが、それと同時に心の底から幸せという気持ちも沸き上がってきたのだ。
だが翌年、中学生になると部活動に時間を取られるようになった。友人たちとの付き合いも増え、夏休みは合宿や遊びの予定で埋まっていく。祖父母の家を訪れる機会は失われ、気づけば少女との約束は記憶の彼方に埋もれていた。
時は流れていき、高校、大学、就職で忙しい日々の中で、あの夏の記憶は色あせていった。
そして二十八の歳を迎えた熱い夏の日、僕の元に祖母の訃報が届いた。
久しぶりに足を向けた町は、記憶の中の面影を失っていた。商店街には錆びついたシャッターが並び、人影はまばら。田んぼは荒れ地と化し、空き家が点在している。かつて生命力に満ちていた町は、まるで時の流れに取り残されたように静寂に包まれていた。
葬儀を終えた夕刻、僕は不意に幼い日々を思い返していた。毎日会っていた少女のこと。交わした約束のこと。
「そういえば、あの子は今どうしているのだろう」
僕はあの場所へと足を向けた。田舎道は舗装され、小川は細々とした流れに変わっていた。それでも、あの場所はすぐに見つけることができた。
時は流れていき、高校、大学、就職で忙しい日々の中で、あの夏の記憶は色あせていった。
そして二十八の歳を迎えた熱い夏の日、僕の元に祖母の訃報が届いた。
久しぶりに足を向けた町は、記憶の中の面影を失っていた。商店街には錆びついたシャッターが並び、人影はまばら。田んぼは荒れ地と化し、空き家が点在している。かつて生命力に満ちていた町は、まるで時の流れに取り残されたように静寂に包まれていた。
葬儀を終えた夕刻、僕は不意に幼い日々を思い返していた。毎日会っていた少女のこと。交わした約束のこと。
「そういえば、あの子は今どうしているのだろう」
僕はあの場所へと足を向けた。田舎道は舗装され、小川は細々とした流れに変わっていた。それでも、あの場所はすぐに見つけることができた。
そして、そこに彼女がいた。十数年の歳月など存在しなかったかのような、あの日と変わらぬ白いワンピース姿で。
「まさるくん」
少女は振り返って微笑んだ。だが、その姿はかすかに透けて見えた。
「君は…」
「ずっと待ってたの」
僕は現実を疑った。
「でも、君は…どうして昔のままなんだ」
少女はうつむきながら切なそうな表情を浮かべ、何も喋ろうとしなかった。
その時、僕は周囲を見渡した。錆びついた看板、崩れかけた塀、誰も住まなくなった家々。そして消えゆく少女の姿。町の衰退と、彼女の透明度がシンクロしていると思った。
「君は…まさか…」
僕の言葉に、少女は小さく頷いた。
「もうすぐ私は消える」
「えっ、なんで…」
「みんな、ここから去っていくから」
そして少女は昨日の出来事のように過去の話を喋り始めた。
「昔、ここに鉄道が開通したときは、とても賑やかだった。子どもたちの笑い声が響いて、商店街には人があふれていた。大変な時代もあったけど、みんなで支え合って生きていた。大きな争いの後の復興の時代は、大きな成長の波に乗って多くの若者が都会へ出て行ったけれど、それでも盆や正月には生まれ育った場所に帰ってきた」
語る物語は、彼女の年齢では体験し得ない過去の出来事だった。
「その時代に比べて今は…」
少女は深い悲しみの表情で町の方を見つめた。その瞳には、長い年月をかけて失われていったものへの哀愁が浮かんでいた。僕も少女の視線を追って振り返ると、夕暮れに染まった寂しい町並みが目に入った。僕の胸に、言いようのない切なさが込み上げてきた。
そして少女の姿がさらに薄れていく。
「でも、まさるくんとの思い出は、本当に宝物だった。友達になれて、私は幸せだった」
「僕も…君がいてくれて、本当に救われた」
「またここに来てくれて、ありがとう」
少女の姿は、もはやぼんやりとしか認識できなくなっていた。
「待って」
僕は手を伸ばしたが、それは空気を掴むだけだった。
「いつまでも、友達だよ」
そう僕が言うと風が吹いて、少女の姿は跡形もなく消えた。僕は一人、夕暮れの田舎道に佇んでいた。
「まさるくん」
少女は振り返って微笑んだ。だが、その姿はかすかに透けて見えた。
「君は…」
「ずっと待ってたの」
僕は現実を疑った。
「でも、君は…どうして昔のままなんだ」
少女はうつむきながら切なそうな表情を浮かべ、何も喋ろうとしなかった。
その時、僕は周囲を見渡した。錆びついた看板、崩れかけた塀、誰も住まなくなった家々。そして消えゆく少女の姿。町の衰退と、彼女の透明度がシンクロしていると思った。
「君は…まさか…」
僕の言葉に、少女は小さく頷いた。
「もうすぐ私は消える」
「えっ、なんで…」
「みんな、ここから去っていくから」
そして少女は昨日の出来事のように過去の話を喋り始めた。
「昔、ここに鉄道が開通したときは、とても賑やかだった。子どもたちの笑い声が響いて、商店街には人があふれていた。大変な時代もあったけど、みんなで支え合って生きていた。大きな争いの後の復興の時代は、大きな成長の波に乗って多くの若者が都会へ出て行ったけれど、それでも盆や正月には生まれ育った場所に帰ってきた」
語る物語は、彼女の年齢では体験し得ない過去の出来事だった。
「その時代に比べて今は…」
少女は深い悲しみの表情で町の方を見つめた。その瞳には、長い年月をかけて失われていったものへの哀愁が浮かんでいた。僕も少女の視線を追って振り返ると、夕暮れに染まった寂しい町並みが目に入った。僕の胸に、言いようのない切なさが込み上げてきた。
そして少女の姿がさらに薄れていく。
「でも、まさるくんとの思い出は、本当に宝物だった。友達になれて、私は幸せだった」
「僕も…君がいてくれて、本当に救われた」
「またここに来てくれて、ありがとう」
少女の姿は、もはやぼんやりとしか認識できなくなっていた。
「待って」
僕は手を伸ばしたが、それは空気を掴むだけだった。
「いつまでも、友達だよ」
そう僕が言うと風が吹いて、少女の姿は跡形もなく消えた。僕は一人、夕暮れの田舎道に佇んでいた。
帰りの電車の窓に映る僕の顔を見つめながら、僕は考え続けていた。
あの約束は些細なものだったかもしれない。しかし、それを待つ人にとっては、決して些細なものではなかった。少女にとって、僕との約束は代え難い宝だったのだ。
日々に追われる中で、僕は少女のことを忘れてしまった。
それから僕は一つのことを考えていた。携帯電話が普及した現代では、来るか来ないのかが分からない人を待ち続けるということが無くなってきている。約束の時間に遅れそうになれば連絡を取り、直前に会えなくなればこれも連絡し別の日に約束し直す。待ち合わせの時間に来ない相手をひたすら待つなど、もはや考えられない。待ち続けるという行為自体が過去の遺物となっているのかもしれない。
けれども、少女は待っていた。十数年もの間、あの場所で。僕がまた来ると信じて。
車窓を流れる風景を眺めながら、僕は心の中で呟いた。
「ごめんなさい。そして、ありがとう」
夏の小さな約束。それは消えゆく町と、一人の少年との間に結ばれた、小さくて大きな絆の物語だった。
僕はその日から、人との約束を大切にするようになった。どんなに小さな約束でも、それを待っている人がいる。そのことを、僕は決して忘れない…
あの約束は些細なものだったかもしれない。しかし、それを待つ人にとっては、決して些細なものではなかった。少女にとって、僕との約束は代え難い宝だったのだ。
日々に追われる中で、僕は少女のことを忘れてしまった。
それから僕は一つのことを考えていた。携帯電話が普及した現代では、来るか来ないのかが分からない人を待ち続けるということが無くなってきている。約束の時間に遅れそうになれば連絡を取り、直前に会えなくなればこれも連絡し別の日に約束し直す。待ち合わせの時間に来ない相手をひたすら待つなど、もはや考えられない。待ち続けるという行為自体が過去の遺物となっているのかもしれない。
けれども、少女は待っていた。十数年もの間、あの場所で。僕がまた来ると信じて。
車窓を流れる風景を眺めながら、僕は心の中で呟いた。
「ごめんなさい。そして、ありがとう」
夏の小さな約束。それは消えゆく町と、一人の少年との間に結ばれた、小さくて大きな絆の物語だった。
僕はその日から、人との約束を大切にするようになった。どんなに小さな約束でも、それを待っている人がいる。そのことを、僕は決して忘れない…