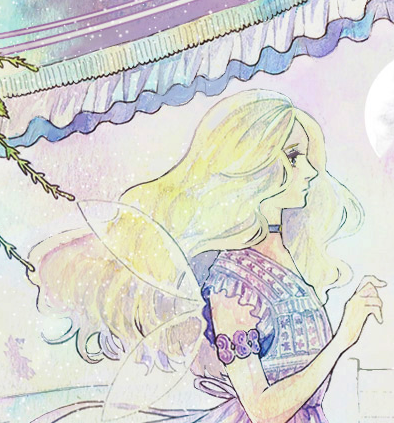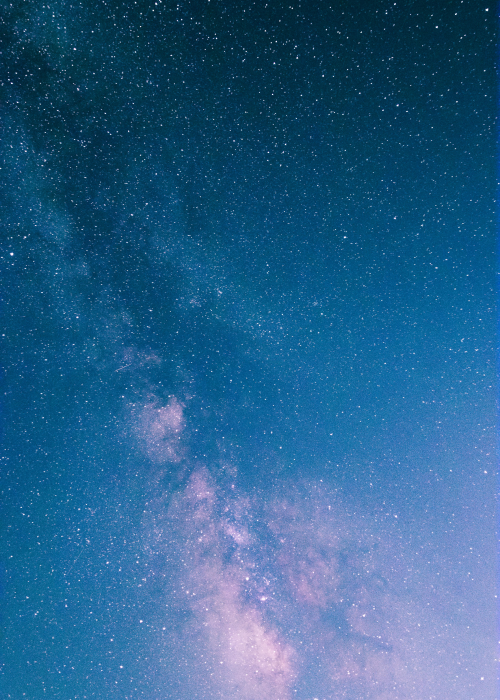最終話:究極のダメ出しと究極の諦め
ー/ー 女神アフロディーテは、今日こそはと期待しながらも、いつもの定位置である特注のソファに、美しくも絶望的な姿勢で座っていた。
前回、「斜め上からの要求」をしたことで、彼女の求める「センスの良い愛」に一歩でも近づいてくれるのではないか、と僅かに期待していたのだ。
しかし、彼女は知っている。この男神たちは、彼女の要求を「表面的なタスク」としてしか認識しないことを。
憂鬱の原因は、相変わらず言い寄ってくる「男性神」たちの、究極の努力の末に辿り着いた、究極の的外れなアプローチである。
まず現れたのは、太陽神アポロン。前回、「常温で、触れるたびに体温が上がるような、秘められた甘美さ」「一瞬で溶けて、甘い香りが広がる、洗練されたデザート」と要求されたことを受け、彼は完璧なプレゼンテーションを準備してきた。
「アフロディーテ! 君の唇は、まるで…最高級のホワイトチョコレートでコーティングされた、極上のラムレーズン・トリュフだ! 噛むと一瞬で溶けて甘い香りが広がり、秘められたラムの情熱が、君の体温を静かに高めていく! 常温で完全だ!」
アフロディーテは、目を見開いた。
(すごい! ちゃんとデザートで例えたわ! しかも、「常温」「溶ける」「体温が上がる」「甘い香り」の要素を全て満たしている!……完璧だわ!)
そして、次の瞬間、アフロディーテは静かに顔を曇らせた。
「アポロン、ありがとう。要求は完璧に満たしているわ。とても、論理的で構造的な愛の言葉だわ。でもね、アポロン。」
「…はい、女神よ。」
「ラムレーズンは、私が嫌いな唯一のデザートなのよ。だって、アルコールがきつすぎるもの。私、ブランデーが香るカシスのほうが好きなの。」
アポロンは、全身の光を失い、その場に崩れ落ちた。要求された要素を全て満たし、誰もが「完璧」と認める表現を捻り出したにもかかわらず、まさかの「個人の嗜好」という究極のトラップが待ち受けていたのだ。
「…私の全知全能の力でも、君の個人的な嗜好までは…」
「愛の神たる私を愛するなら、そのくらいの予習はしておくべきでしょう? 残念だわ、アポロン。知識は満点、配慮は零点ね。」
アポロンは「愛のトラップは、戦場の罠より酷い…」と呟きながら、魂の抜け殻となって去っていった。
---
次に現れたのは、鍛冶神ヘパイストス。前回、「究極の強度と究極の繊細さ」「愛の波動で動くこと」という矛盾した要求を突きつけられた彼だったが、今回は自信満々だった。
「アフロディーテ。これを見ろ!」
彼が差し出したのは、見た目はほとんど空気のような、透明で微かに虹色に光る、針金よりも細いリングだった。
「これは、ヘファイストスの愛の波動にのみ反応し、外部からの衝撃を時間ごと停止させる特殊な素材で打ったリングだ! これなら、汗にも雷にも、時間の流れにも耐える究極の強度と、空気のような究極の繊細さを両立している!」
アフロディーテは、それを指先でそっと持った。本当に軽い。そして、確かにヘパイストスの愛(という名の膨大な魔力)に反応して微かに鼓動している。
(これもまた…要求を完璧に満たしているわね。発想力は相変わらず鈍いけど、技術力で全てをクリアしてきたわ。素晴らしいわ、私の夫…)
「ヘパイストス、感動したわ! これが私の求めていたものよ!」
ヘパイストスは、珍しく頬を赤らめ、歓喜に震えた。
「しかし、」アフロディーテは次の瞬間、その空気のようなリングを、指先で力を込めてポキリと折った。
「私、ピアス穴が開いてないから、リングじゃなくて、耳飾りが欲しかったの。」
ヘパイストスは、砕け散ったリングの破片を見つめ、立ち尽くした。
「なぜ…なぜ、装着方法を先に…」
「あなたの愛が本物なら、私がブレスレットを要求した時に、私の耳にピアス穴が開いていないことを察知して、形を変えてくるべきでしょう? 技術力は満点。察知能力は零点よ。この程度の機転も利かせられない男に、私の愛を語る資格はないわ。」
ヘパイストスは、呻き声を上げながら、再び作業場へと引きこもっていった。
---
そして、極めつけは、戦神アレス。前回、「戦い一切禁止のロマンス」「砂塵ではなく絹の絨毯、剣ではなくバラの花びら」と要求された彼だった。
アレスは、いつもの戦闘服ではなく、高級シルクのガウンをまとい、手には剣ではなく、吟遊詩人の竪琴を抱えていた。そして、床には大量の真っ赤なバラの花びらが敷き詰められている。
「アフロディーテ! 見ろ! 我は、君の求めるロマンスを用意した! 我らの周囲には、戦いの血の匂いなど一切ない! 絹のガウン、バラの絨毯、そして、我の愛の詩!」
アレスはぎこちない手つきで竪琴をかき鳴らし、詩を吟じた。その内容は、バラの色や絹の滑らかさを愛の情熱に例える、平穏でロマンティックなものだった。
アフロディーテは、静かに彼を見つめた。
(凄い。アレスが、戦いの要素を完全に排除してきたわ。慣れないことを頑張ってくれたのね。これで、やっと私が求めていた…)
「アレス、詩も、バラも、ガウンも、全てが私の要求通りよ。本当に、頑張ったわね。」
アレスは、希望に満ちた目で彼女を見た。
「しかし、アレス。」
「私、戦いのない世界って、逆に退屈なのよね。」
アフロディーテは、深く優雅な溜息を吐いた。
「あなたが、私のためにすべてを捨てて、こんな平穏で退屈な男になってしまうなんて。私を愛するあなたには、危険で、強引で、世界を滅ぼすほどの情熱を持っていて欲しいの。私を、あなたの暴力的な愛で、無理やり奪ってくれないと、私、ときめけないわ。」
アレスは、竪琴を床に落とした。その音は、戦場の鬨の声よりも虚しく響いた。
「平和は…退屈…?」
「そうよ。あなたは私に、愛とロマンスを強要されたから、これを実行した。あなたが自発的に、その暴力性を愛に変えて、私を魅了してくれないと、意味がないのよ。努力は満点。本質は零点ね。さあ、行って。私のために、宇宙の果ての星を一つ、殴り壊してきてちょうだい。それがあなたの愛の証明よ。」
アレスは、バラの花びらをまき散らしながら、再び戦神の顔に戻り、破壊の衝動と共に去っていった。
---
戦神が、今度こそ二度と戻らないだろうと確信させるほどの勢いで去っていくのを見送りながら、アフロディーテは深いソファに体を沈めた。
(はあ。本当にダメね。アポロンには論理ではなく心を求め、ヘパイストスには技術ではなく察知能力を求め、アレスには平穏ではなく本能的な暴力性を求めた。誰も、私の真の要求、つまり「究極のセンスと、完璧な機転、そして私自身をも超える傲慢な愛」を持ってきてくれない。)
愛の女神は、愛に飢えていた。彼女が求めるのは、神としての地位や力ではなく、ただ一人の女性として、心から「キュン」とさせてくれるような、誰も到達できない、矛盾に満ちた究極の愛だった。
「ああ、私のときめきセンサーは、今日も警報を鳴らすことなく、ただただ静かに、この世の男どもは全て私が求めていない、という究極の真実を感知しているわ…」
アフロディーテは、一人で静かにアンブロシアを啜る。そして、誰にも聞こえない声で呟いた。
「…まあ、誰も私の期待に応えられないからこそ、私が唯一無二の女神でいられるんだけどね。」
愛の女神の憂鬱は、今日も晴れそうになかった。そして、これからも永遠に晴れることはないだろう。なぜなら、彼女の理想は「永遠に到達されない完璧さ」そのものだからだ。
(おしまい)
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
女神アフロディーテは、今日こそはと期待しながらも、いつもの定位置である特注のソファに、美しくも絶望的な姿勢で座っていた。
前回、「斜め上からの要求」をしたことで、彼女の求める「センスの良い愛」に一歩でも近づいてくれるのではないか、と僅かに期待していたのだ。
しかし、彼女は知っている。この男神たちは、彼女の要求を「表面的なタスク」としてしか認識しないことを。
憂鬱の原因は、相変わらず言い寄ってくる「男性神」たちの、究極の努力の末に辿り着いた、究極の的外れなアプローチである。
まず現れたのは、太陽神アポロン。前回、「常温で、触れるたびに体温が上がるような、秘められた甘美さ」「一瞬で溶けて、甘い香りが広がる、洗練されたデザート」と要求されたことを受け、彼は完璧なプレゼンテーションを準備してきた。
「アフロディーテ! 君の唇は、まるで…最高級のホワイトチョコレートでコーティングされた、極上のラムレーズン・トリュフだ! 噛むと一瞬で溶けて甘い香りが広がり、秘められたラムの情熱が、君の体温を静かに高めていく! 常温で完全だ!」
アフロディーテは、目を見開いた。
(すごい! ちゃんとデザートで例えたわ! しかも、「常温」「溶ける」「体温が上がる」「甘い香り」の要素を全て満たしている!……完璧だわ!)
そして、次の瞬間、アフロディーテは静かに顔を曇らせた。
「アポロン、ありがとう。要求は完璧に満たしているわ。とても、論理的で構造的な愛の言葉だわ。でもね、アポロン。」
「…はい、女神よ。」
「ラムレーズンは、私が嫌いな唯一のデザートなのよ。だって、アルコールがきつすぎるもの。私、ブランデーが香るカシスのほうが好きなの。」
アポロンは、全身の光を失い、その場に崩れ落ちた。要求された要素を全て満たし、誰もが「完璧」と認める表現を捻り出したにもかかわらず、まさかの「個人の嗜好」という究極のトラップが待ち受けていたのだ。
「…私の全知全能の力でも、君の個人的な嗜好までは…」
「愛の神たる私を愛するなら、そのくらいの予習はしておくべきでしょう? 残念だわ、アポロン。知識は満点、配慮は零点ね。」
アポロンは「愛のトラップは、戦場の罠より酷い…」と呟きながら、魂の抜け殻となって去っていった。
---
次に現れたのは、鍛冶神ヘパイストス。前回、「究極の強度と究極の繊細さ」「愛の波動で動くこと」という矛盾した要求を突きつけられた彼だったが、今回は自信満々だった。
「アフロディーテ。これを見ろ!」
彼が差し出したのは、見た目はほとんど空気のような、透明で微かに虹色に光る、針金よりも細いリングだった。
「これは、ヘファイストスの愛の波動にのみ反応し、外部からの衝撃を時間ごと停止させる特殊な素材で打ったリングだ! これなら、汗にも雷にも、時間の流れにも耐える究極の強度と、空気のような究極の繊細さを両立している!」
アフロディーテは、それを指先でそっと持った。本当に軽い。そして、確かにヘパイストスの愛(という名の膨大な魔力)に反応して微かに鼓動している。
(これもまた…要求を完璧に満たしているわね。発想力は相変わらず鈍いけど、技術力で全てをクリアしてきたわ。素晴らしいわ、私の夫…)
「ヘパイストス、感動したわ! これが私の求めていたものよ!」
ヘパイストスは、珍しく頬を赤らめ、歓喜に震えた。
「しかし、」アフロディーテは次の瞬間、その空気のようなリングを、指先で力を込めてポキリと折った。
「私、ピアス穴が開いてないから、リングじゃなくて、耳飾りが欲しかったの。」
ヘパイストスは、砕け散ったリングの破片を見つめ、立ち尽くした。
「なぜ…なぜ、装着方法を先に…」
「あなたの愛が本物なら、私がブレスレットを要求した時に、私の耳にピアス穴が開いていないことを察知して、形を変えてくるべきでしょう? 技術力は満点。察知能力は零点よ。この程度の機転も利かせられない男に、私の愛を語る資格はないわ。」
ヘパイストスは、呻き声を上げながら、再び作業場へと引きこもっていった。
---
そして、極めつけは、戦神アレス。前回、「戦い一切禁止のロマンス」「砂塵ではなく絹の絨毯、剣ではなくバラの花びら」と要求された彼だった。
アレスは、いつもの戦闘服ではなく、高級シルクのガウンをまとい、手には剣ではなく、吟遊詩人の竪琴を抱えていた。そして、床には大量の真っ赤なバラの花びらが敷き詰められている。
「アフロディーテ! 見ろ! 我は、君の求めるロマンスを用意した! 我らの周囲には、戦いの血の匂いなど一切ない! 絹のガウン、バラの絨毯、そして、我の愛の詩!」
アレスはぎこちない手つきで竪琴をかき鳴らし、詩を吟じた。その内容は、バラの色や絹の滑らかさを愛の情熱に例える、平穏でロマンティックなものだった。
アフロディーテは、静かに彼を見つめた。
(凄い。アレスが、戦いの要素を完全に排除してきたわ。慣れないことを頑張ってくれたのね。これで、やっと私が求めていた…)
「アレス、詩も、バラも、ガウンも、全てが私の要求通りよ。本当に、頑張ったわね。」
アレスは、希望に満ちた目で彼女を見た。
「しかし、アレス。」
「私、戦いのない世界って、逆に退屈なのよね。」
アフロディーテは、深く優雅な溜息を吐いた。
「あなたが、私のためにすべてを捨てて、こんな平穏で退屈な男になってしまうなんて。私を愛するあなたには、危険で、強引で、世界を滅ぼすほどの情熱を持っていて欲しいの。私を、あなたの暴力的な愛で、無理やり奪ってくれないと、私、ときめけないわ。」
アレスは、竪琴を床に落とした。その音は、戦場の鬨の声よりも虚しく響いた。
「平和は…退屈…?」
「そうよ。あなたは私に、愛とロマンスを強要されたから、これを実行した。あなたが自発的に、その暴力性を愛に変えて、私を魅了してくれないと、意味がないのよ。努力は満点。本質は零点ね。さあ、行って。私のために、宇宙の果ての星を一つ、殴り壊してきてちょうだい。それがあなたの愛の証明よ。」
アレスは、バラの花びらをまき散らしながら、再び戦神の顔に戻り、破壊の衝動と共に去っていった。
---
戦神が、今度こそ二度と戻らないだろうと確信させるほどの勢いで去っていくのを見送りながら、アフロディーテは深いソファに体を沈めた。
(はあ。本当にダメね。アポロンには論理ではなく心を求め、ヘパイストスには技術ではなく察知能力を求め、アレスには平穏ではなく本能的な暴力性を求めた。誰も、私の真の要求、つまり「究極のセンスと、完璧な機転、そして私自身をも超える傲慢な愛」を持ってきてくれない。)
愛の女神は、愛に飢えていた。彼女が求めるのは、神としての地位や力ではなく、ただ一人の女性として、心から「キュン」とさせてくれるような、誰も到達できない、矛盾に満ちた究極の愛だった。
「ああ、私のときめきセンサーは、今日も警報を鳴らすことなく、ただただ静かに、この世の男どもは全て私が求めていない、という究極の真実を感知しているわ…」
アフロディーテは、一人で静かにアンブロシアを啜る。そして、誰にも聞こえない声で呟いた。
「…まあ、誰も私の期待に応えられないからこそ、私が唯一無二の女神でいられるんだけどね。」
愛の女神の憂鬱は、今日も晴れそうになかった。そして、これからも永遠に晴れることはないだろう。なぜなら、彼女の理想は「永遠に到達されない完璧さ」そのものだからだ。
(おしまい)