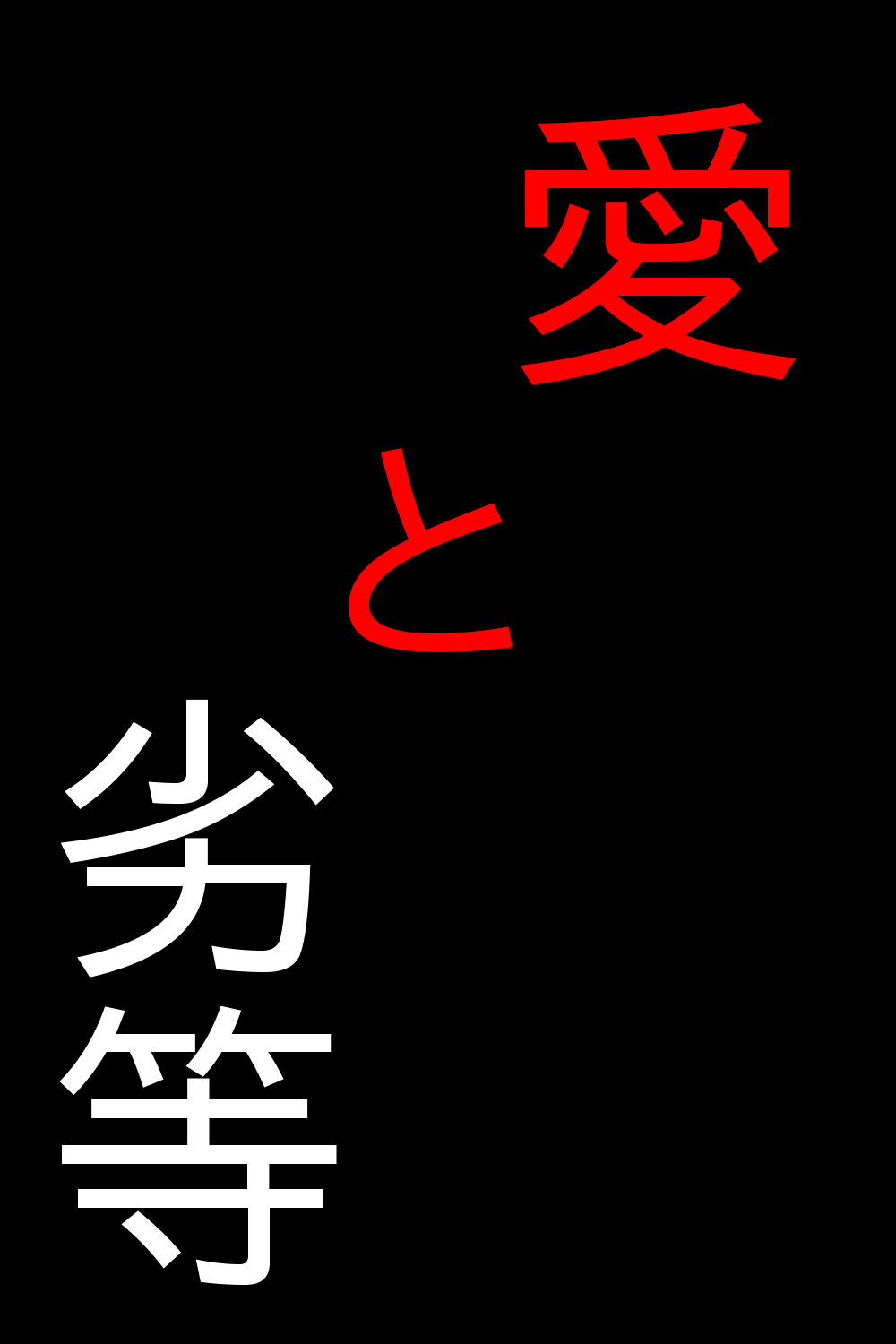ウツボカズラ
ー/ー最近、毎朝通勤電車でいつも同じ人と乗り合わせている。
いつも同じ時間の同じ乗り場で電車に乗っているから、まあそういうこともあるのかな、と思っていた。けれど、ある日、電車が踏切トラブルか何かで遅れていて、混雑で乗り場を変えないといけなくなったときに、ぎゅうぎゅうの車内で、いつものようにすぐ横から、あの香りがしてきた。
その人からは、いつも独特なバニラの香水の香りがしていた。これまで、バニラの強烈な香水をつけている人と時々すれ違うときがあるが、そのときは正直嫌な気分がした。でも、その人の香水は、何か人を魅了するような、それでいて、ちょうどいい強さの香りがしているのだ。
それから、彼女のイヤホンからいつもわずかに漏れる音楽。切ないラブソングが、どうにも心にひっかかるのだ。男ながらそういう女性の歌う切ないラブソングが好きな僕の趣味とぴったり合うのだ。
だから、そのとき、大人げもなく、中2のようなことを思ってしまった。
「これ、運命…?」
ぎゅうぎゅうの車内で、密着せざるを得ない。つり革に手を伸ばしたときに、その人の耳の後ろに、腕が触れてしまった気がした。イヤホンと、それからマスクのひもの感触だった。電車が揺れて、その人の長い髪に僕の口元が触れてしまった。ふわっと香るバニラが、いつもより強く顔の周りを包み込んだ。もう、これは責任をとらないといけないじゃないか。
そんな話を誰かにしたくなって、高校時代からの友人に電話する機会があったときにうっかり話してしまうと、そいつは失礼なことを言ってきた。
「ウツボカズラだな」
「は?」
「知らない?ウツボカズラ、食虫植物の。甘い蜜に寄ってきた虫を袋の中に滑り落として食べちまうんだよ。甘い香りで男を惹きつけて…」
「お前、会ったことのない人に失礼だろうが」
そう怒ると、笑いながら言われた。
「じゃあ、お前こそ、そのバニラの人の何を知っているんだよ」
その通り、たまたま同じ電車で乗っていただけ。何も知らない。ただ、もし、次も乗りあえたなら。いつもすぐそばで乗っている。だって、気になって仕方がないんだから、もうストレートに行くしかない。
ああ、こんなことを思ったのは人生で初めてだ。これが恋愛というやつなんだろう。恋は盲目、なんて言うけれど、何も見えていないのに、何も知らないのに、僕と彼女はどこかで通じ合える気がしているのだから。仮に彼女がウツボカズラで、僕が落ちているのが恋ではなくて消化する袋だとしても、もうそれでも良いような気がしているのだから。
そして、また次の日も、彼女の香りがした。すぐそばに、その気配がして温かい気持ちになる。思わず手を伸ばした。
「あっ…、あの…」
いざとなると、うまく舌が回らない。恥ずかしい。顔の温度が一気に上がったのを感じた。
彼女の顔がこちらを向いた。その空気の流れが、ほてった僕の顔を少しだけ冷ました。
「いつも同じ電車に乗っていますよね」
彼女は少し首を傾げた。
「あっ…なんか気持ち悪いですね。すみません…」
「いえ…」
マスク越しからする、こもった小さな声は、僕が思い描いていたよりも低い声だった。もしかしたら、風邪をひいているのかもしれない。
「毎朝、同じ人がいるな…と思っていて…。もしお時間が合うようであれば、今度お茶でもどうですか?あっ、なんなら今日でもよいですけど…なんて」
人生初のナンパに、わけのわからない感情が渦巻く。普通、こんな朝早くにお茶の時間があるわけがないだろう。まあ、絶対あり得ないけど、あなたさえよければ仕事休みますので、僕のことはお構いなく…
「ちょっといいですか…」
彼女はつぶやいた。
「はい?」
次の駅で電車が止まった。すると、彼女は僕が想像していないほど強い力で僕を引っ張って電車から降ろす。何か犯罪者と間違われたか、そう思うほどの力だ。まずいかもしれない。
駅の端まで来た。朝でも薄暗いスペースに二人きり。このシチュエーション、なんなんだ…。
彼女は突然こちらを向いて、にっこりした気がした。顔を近づけてくる。相変わらずの甘い香りが、また強くなった気がした。
マスクのひもに手をやる。
「…こんな顔でもよいですかー?」
勢いよくマスクをとった。
「…」
「…」
沈黙。
僕は、今までの張りつめていた気持ちのせいか、彼女の笑顔につられて(いや、彼女が笑っているというのは、僕の勘違いの可能性があるけど)、思わず笑いだしてしまった。
きょとんとした彼女。
「すみません…僕、生まれつき弱視で、ほとんどぼやけていて見えていないんです。きっと素敵な顔なんじゃないかと思います」
口が大きく裂けた女は、男の目の前で呆然としていた。狙う相手を間違えた。そして、こんな表情を浮かべられるのは、生まれて初めてのことだった。恥ずかしくなって、マスクを着け直した。
声があまり出ない。
「私、ブサイクなんですが…、よければ、お茶、ご一緒します。今からでも…大丈夫です!行きつけの喫茶店があるんですが…」
「ほっ…本当ですか…?わっ、やった!」
口元を隠しながらでも入れるいつものお店でないといろいろと問題があるのだ。女はいつもより浮足立ったまま、二人で都市伝説の話に出てきそうなうす暗い喫茶店へ向かった。
(了)
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
最近、毎朝通勤電車でいつも同じ人と乗り合わせている。
いつも同じ時間の同じ乗り場で電車に乗っているから、まあそういうこともあるのかな、と思っていた。けれど、ある日、電車が踏切トラブルか何かで遅れていて、混雑で乗り場を変えないといけなくなったときに、ぎゅうぎゅうの車内で、いつものようにすぐ横から、あの香りがしてきた。
その人からは、いつも独特なバニラの香水の香りがしていた。これまで、バニラの強烈な香水をつけている人と時々すれ違うときがあるが、そのときは正直嫌な気分がした。でも、その人の香水は、何か人を魅了するような、それでいて、ちょうどいい強さの香りがしているのだ。
それから、彼女のイヤホンからいつもわずかに漏れる音楽。切ないラブソングが、どうにも心にひっかかるのだ。男ながらそういう女性の歌う切ないラブソングが好きな僕の趣味とぴったり合うのだ。
だから、そのとき、大人げもなく、中2のようなことを思ってしまった。
「これ、運命…?」
ぎゅうぎゅうの車内で、密着せざるを得ない。つり革に手を伸ばしたときに、その人の耳の後ろに、腕が触れてしまった気がした。イヤホンと、それからマスクのひもの感触だった。電車が揺れて、その人の長い髪に僕の口元が触れてしまった。ふわっと香るバニラが、いつもより強く顔の周りを包み込んだ。もう、これは責任をとらないといけないじゃないか。
そんな話を誰かにしたくなって、高校時代からの友人に電話する機会があったときにうっかり話してしまうと、そいつは失礼なことを言ってきた。
「ウツボカズラだな」
「は?」
「知らない?ウツボカズラ、食虫植物の。甘い蜜に寄ってきた虫を袋の中に滑り落として食べちまうんだよ。甘い香りで男を惹きつけて…」
「お前、会ったことのない人に失礼だろうが」
そう怒ると、笑いながら言われた。
「じゃあ、お前こそ、そのバニラの人の何を知っているんだよ」
その通り、たまたま同じ電車で乗っていただけ。何も知らない。ただ、もし、次も乗りあえたなら。いつもすぐそばで乗っている。だって、気になって仕方がないんだから、もうストレートに行くしかない。
ああ、こんなことを思ったのは人生で初めてだ。これが恋愛というやつなんだろう。恋は盲目、なんて言うけれど、何も見えていないのに、何も知らないのに、僕と彼女はどこかで通じ合える気がしているのだから。仮に彼女がウツボカズラで、僕が落ちているのが恋ではなくて消化する袋だとしても、もうそれでも良いような気がしているのだから。
そして、また次の日も、彼女の香りがした。すぐそばに、その気配がして温かい気持ちになる。思わず手を伸ばした。
「あっ…、あの…」
いざとなると、うまく舌が回らない。恥ずかしい。顔の温度が一気に上がったのを感じた。
彼女の顔がこちらを向いた。その空気の流れが、ほてった僕の顔を少しだけ冷ました。
「いつも同じ電車に乗っていますよね」
彼女は少し首を傾げた。
「あっ…なんか気持ち悪いですね。すみません…」
「いえ…」
マスク越しからする、こもった小さな声は、僕が思い描いていたよりも低い声だった。もしかしたら、風邪をひいているのかもしれない。
「毎朝、同じ人がいるな…と思っていて…。もしお時間が合うようであれば、今度お茶でもどうですか?あっ、なんなら今日でもよいですけど…なんて」
人生初のナンパに、わけのわからない感情が渦巻く。普通、こんな朝早くにお茶の時間があるわけがないだろう。まあ、絶対あり得ないけど、あなたさえよければ仕事休みますので、僕のことはお構いなく…
「ちょっといいですか…」
彼女はつぶやいた。
「はい?」
次の駅で電車が止まった。すると、彼女は僕が想像していないほど強い力で僕を引っ張って電車から降ろす。何か犯罪者と間違われたか、そう思うほどの力だ。まずいかもしれない。
駅の端まで来た。朝でも薄暗いスペースに二人きり。このシチュエーション、なんなんだ…。
彼女は突然こちらを向いて、にっこりした気がした。顔を近づけてくる。相変わらずの甘い香りが、また強くなった気がした。
マスクのひもに手をやる。
「…こんな顔でもよいですかー?」
勢いよくマスクをとった。
「…」
「…」
沈黙。
僕は、今までの張りつめていた気持ちのせいか、彼女の笑顔につられて(いや、彼女が笑っているというのは、僕の勘違いの可能性があるけど)、思わず笑いだしてしまった。
きょとんとした彼女。
「すみません…僕、生まれつき弱視で、ほとんどぼやけていて見えていないんです。きっと素敵な顔なんじゃないかと思います」
口が大きく裂けた女は、男の目の前で呆然としていた。狙う相手を間違えた。そして、こんな表情を浮かべられるのは、生まれて初めてのことだった。恥ずかしくなって、マスクを着け直した。
声があまり出ない。
「私、ブサイクなんですが…、よければ、お茶、ご一緒します。今からでも…大丈夫です!行きつけの喫茶店があるんですが…」
「ほっ…本当ですか…?わっ、やった!」
口元を隠しながらでも入れるいつものお店でないといろいろと問題があるのだ。女はいつもより浮足立ったまま、二人で都市伝説の話に出てきそうなうす暗い喫茶店へ向かった。
(了)