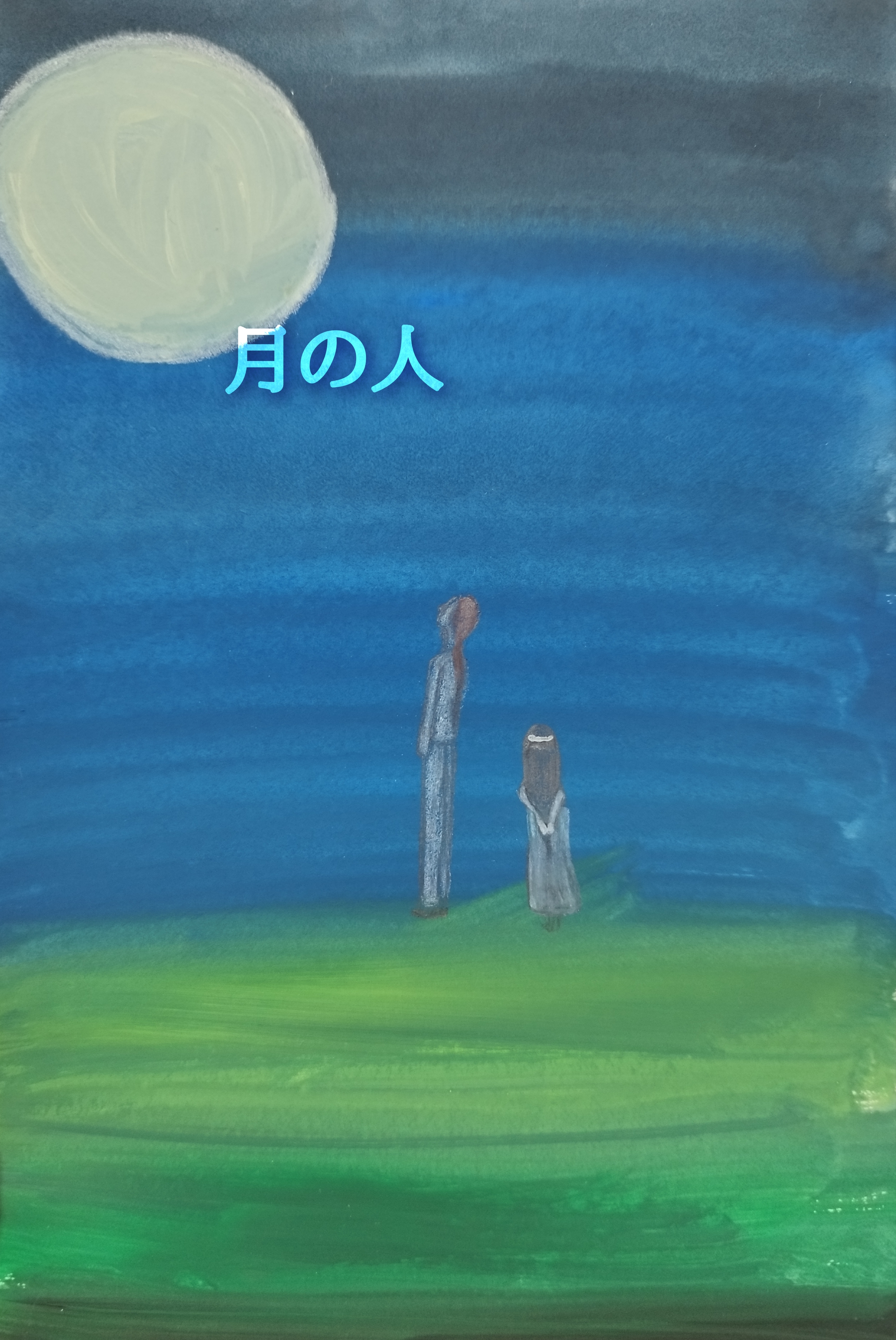2_Chocolate
ー/ー 春斗くんが、ケトルに水を入れ火にかけた。ドリッパーにフィルターをセットして、コーヒーの粉を入れる。
眼福だなぁ。手慣れた姿にうっとりする。春斗くんが淹れてくれるの、どれくらいぶりだろ。わくわくして待っていると、ふと、テーブルのカゴに積まれた色とりどりの小箱が目に入った。ざっと見、十個はある。
「これ、全部チョコ? バレンタインの……」
「好きなの食べていいよ」
春斗くん、モテるんだ――。それもかなり。チョコレートの数が証明してる。なんとなく知ってはいた。モテないはずないもん。どの角度から見ても素敵だし、性格もいいし、優しいし。
眼福だなぁ。手慣れた姿にうっとりする。春斗くんが淹れてくれるの、どれくらいぶりだろ。わくわくして待っていると、ふと、テーブルのカゴに積まれた色とりどりの小箱が目に入った。ざっと見、十個はある。
「これ、全部チョコ? バレンタインの……」
「好きなの食べていいよ」
春斗くん、モテるんだ――。それもかなり。チョコレートの数が証明してる。なんとなく知ってはいた。モテないはずないもん。どの角度から見ても素敵だし、性格もいいし、優しいし。
でも、こうしてじかに現実を突きつけられるのは初めてで、かなりの衝撃だった。ブランドもののチョコレート、こんなにもらっちゃうんだ。義理じゃなく、みんな本気だよね? 身近なひとだった春斗くんが、一気に遠い存在に感じた。
カゴのチョコはもらったときのまま、封が切られてない。食べていいって、食べられるわけないでしょうに。
「こっちの食べかけ、もらうね」
唯一開いてる箱を見ると半分ほどなくなっていた。きっと美味しいんだ。どんな味なんだろうと興味がわいて、小さな薄いチョコレートを頬張った。
「こっちの食べかけ、もらうね」
唯一開いてる箱を見ると半分ほどなくなっていた。きっと美味しいんだ。どんな味なんだろうと興味がわいて、小さな薄いチョコレートを頬張った。
「……にがっ!」
甘いものだと思っていたら全然違った。予想外のヘビーな苦味に口の中がパニくる。悶えるわたしを見て、春斗くんが笑いをこらえてる。
甘いものだと思っていたら全然違った。予想外のヘビーな苦味に口の中がパニくる。悶えるわたしを見て、春斗くんが笑いをこらえてる。
「それ砂糖不使用」
「先に言ってよぉ」
「甘いとは限らないだろ」
「チョコはふつう甘いの!」
涙目になりながら反論すると、春斗くんが
「ウサギは甘くないとだめだもんな。ほら、流し込め」とマグカップを差し出した。
受け取るとカップの中身はマイルドなカフェオレだった。適温で美味しい。生き返る。ありがたい心づかいに感謝。
「甘いとは限らないだろ」
「チョコはふつう甘いの!」
涙目になりながら反論すると、春斗くんが
「ウサギは甘くないとだめだもんな。ほら、流し込め」とマグカップを差し出した。
受け取るとカップの中身はマイルドなカフェオレだった。適温で美味しい。生き返る。ありがたい心づかいに感謝。
「このチョコくれたひと、意地悪じゃない?」
向かいに座った春斗くんに同意を求めると、
「慣れればうまいよ。紀元前から薬として扱われてるくらしだし、血流改善とか、コレステロールの抑制とか。無糖だとなおさら体にいい」
「慣れればうまいよ。紀元前から薬として扱われてるくらしだし、血流改善とか、コレステロールの抑制とか。無糖だとなおさら体にいい」
「製薬会社の女子が選ぶチョコは、さすが味も健康的」
「それ取引先の――あ、いやなんでもない」
春斗くんがめちゃくちゃ気になるところで言葉を切った。胸の中に、これまでと違う気持ちが生まれた。ざらざらとした感情だった。
「取引先? 隠さなきゃいけないような相手なの」
わたしは余裕もなく訊ねていた。
「それ取引先の――あ、いやなんでもない」
春斗くんがめちゃくちゃ気になるところで言葉を切った。胸の中に、これまでと違う気持ちが生まれた。ざらざらとした感情だった。
「取引先? 隠さなきゃいけないような相手なの」
わたしは余裕もなく訊ねていた。
「んー……さっきの電話の、友達の友達にもらった」
「もしかして、その人と今日会うはずだった?」
「もしかして、その人と今日会うはずだった?」
さらに突っ込むと、「まあそんなとこ」と春斗くんが目をそらした。
デートだったんだ。超ショック。推測するに、春斗くんの友達が無糖チョコをくれた女の子の仲介役で、引き合わせるために電話してきた――そういうことだよね。
デートだったんだ。超ショック。推測するに、春斗くんの友達が無糖チョコをくれた女の子の仲介役で、引き合わせるために電話してきた――そういうことだよね。
ここ数年で、一、二を争うレベルの動揺に、脳しんとうをおこしそうになった。息が止まりそう。深呼吸、深呼吸しなきゃ。
「春斗くん、ごめんね。もう帰るから準備して」
「さっき行かないって断ったの聞いてなかった?」
「聞いてたけど。でもだけど!」
焦るわたしとは対照的に、春斗くんがのんびりとコーヒーをすすってる。
「行かなくていいの」
「行って欲しいのか」
やだ。やだやだ。行かないで欲しい。でもそんなこと言ったら、春斗くんのこと好きだってバレちゃうよ。落ち着こう。気持ちをセーブでしょ!
「念のため訊くけど。ウサギの代わりに、無糖女子の肩抱き寄せてキスして、ホテルでエッチなことしてもいいんだ?」
「行かなくていいの」
「行って欲しいのか」
やだ。やだやだ。行かないで欲しい。でもそんなこと言ったら、春斗くんのこと好きだってバレちゃうよ。落ち着こう。気持ちをセーブでしょ!
「念のため訊くけど。ウサギの代わりに、無糖女子の肩抱き寄せてキスして、ホテルでエッチなことしてもいいんだ?」
「え、えええ? いまなんておっしゃいました? わたしの代わりに?」
「代わりに」
「そんなのダメに決まってるでしょ!!」
思わず力説すると、春斗くんが安堵したような表情を浮かべた。
「そう言ってくれなきゃ終わるとこだった」
終わる? どういう意味? 確かめたいけど怖くて訊けない。ひとりざわつくわたしを尻目に、春斗くんがカゴのチョコをひと箱取り上げた。
思わず力説すると、春斗くんが安堵したような表情を浮かべた。
「そう言ってくれなきゃ終わるとこだった」
終わる? どういう意味? 確かめたいけど怖くて訊けない。ひとりざわつくわたしを尻目に、春斗くんがカゴのチョコをひと箱取り上げた。
ぴりぴりと音を立て、包装紙を破いていく。箱を開けると、ひとくち大のハートが並んだ可愛いチョコの詰め合わせだった。一粒つまんで、春斗くんが口に含む。
「俺の好きな子知ってる? その子からはもらえなかったんだよ。去年も今年も」
「そ、それって」
思い当たる。わたし、高校を卒業してから春斗くんにあげてない。高校生までは勢いで毎年渡してたけど、去年はなんだか気後れして。
今年は春斗くんが一月の終わりから二月中旬までドイツに出張だったのもあって、バレンタイン当日にあげられないなら……と軽い気持ちでやめたんだ。
「ほかに好きなやつができたのかと思ってた」
「ちょ……それってなんか、わたしが春斗くんを好きみたいに聞こえ――」
「違うの?」
テーブルに身を乗り出した春斗くんが、ふわりとわたしにキスした。
「俺の好きな子知ってる? その子からはもらえなかったんだよ。去年も今年も」
「そ、それって」
思い当たる。わたし、高校を卒業してから春斗くんにあげてない。高校生までは勢いで毎年渡してたけど、去年はなんだか気後れして。
今年は春斗くんが一月の終わりから二月中旬までドイツに出張だったのもあって、バレンタイン当日にあげられないなら……と軽い気持ちでやめたんだ。
「ほかに好きなやつができたのかと思ってた」
「ちょ……それってなんか、わたしが春斗くんを好きみたいに聞こえ――」
「違うの?」
テーブルに身を乗り出した春斗くんが、ふわりとわたしにキスした。
唇が重なり体に電気が走る。
心臓が盛大に跳ね上がった。
「は、春斗く……」
間を置かず、もう一度キスされた。春斗くんの舌の上で溶けたハートのチョコレートが、わたしの舌先にのる。文字通りの甘いキスに思考回路がショート寸前……!
「莉衣は誰が好きなんだよ」
不意に本名で呼ばれ、体がじりじりと熱くなる。
不意に本名で呼ばれ、体がじりじりと熱くなる。
言っていいの? 伝えていいの? もう隠さなくていいの?
「春斗くんが……好き」
俺も莉衣が好きだよ、と春斗くんが囁いた。とてつもなく甘美な、極上の夢を見てるみたいだった。
「おばさんに伝えといて。俺が今夜食べたいのは、莉衣だって」
オオカミ発言に煽られて、一気に頬が熱くなる。
「こ、殺されるよ!」
「祝福されるの間違いだろ」
「その自信はどこからくるの……」
「春斗くんが……好き」
俺も莉衣が好きだよ、と春斗くんが囁いた。とてつもなく甘美な、極上の夢を見てるみたいだった。
「おばさんに伝えといて。俺が今夜食べたいのは、莉衣だって」
オオカミ発言に煽られて、一気に頬が熱くなる。
「こ、殺されるよ!」
「祝福されるの間違いだろ」
「その自信はどこからくるの……」
ああ、でもあらためて思えば、お母さんて何かにつけ春斗くんのこと「優秀」だとか「いい子」だとか話してた。頼まれてもいないのにたくさんお料理作って持たせるし。気に入ってるのは疑いようもない。だとしても。
「今夜はだめ。わたし上手く応えられないもん。時間ちょうだい。練習したいの!」
「ほかの男と?」
「ひとりで」
「意味不」
春斗くんがこらえ切れず吹き出した。
わたしは至って真面目なんですが。
「ばかだな。俺と練習しろよ」
遅れてやって来たバレンタインは、思いがけず糖度高めの甘々仕様だった。
「いろいろ教えてやるから覚悟しとけ」と不敵に笑う春斗くんは、抗いがたいほど魅力的で。抱き寄せられた腕の中で溶ろけてしまいそうだった。
【了】
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
春斗くんが、ケトルに水を入れ火にかけた。ドリッパーにフィルターをセットして、コーヒーの粉を入れる。
眼福だなぁ。手慣れた姿にうっとりする。春斗くんが淹れてくれるの、どれくらいぶりだろ。わくわくして待っていると、ふと、テーブルのカゴに積まれた色とりどりの小箱が目に入った。ざっと見、十個はある。
「これ、全部チョコ? バレンタインの……」
「好きなの食べていいよ」
「好きなの食べていいよ」
春斗くん、モテるんだ――。それもかなり。チョコレートの数が証明してる。なんとなく知ってはいた。モテないはずないもん。どの角度から見ても素敵だし、性格もいいし、優しいし。
でも、こうしてじかに現実を突きつけられるのは初めてで、かなりの衝撃だった。ブランドもののチョコレート、こんなにもらっちゃうんだ。義理じゃなく、みんな本気だよね? 身近なひとだった春斗くんが、一気に遠い存在に感じた。
カゴのチョコはもらったときのまま、封が切られてない。食べていいって、食べられるわけないでしょうに。
「こっちの食べかけ、もらうね」
「こっちの食べかけ、もらうね」
唯一開いてる箱を見ると半分ほどなくなっていた。きっと美味しいんだ。どんな味なんだろうと興味がわいて、小さな薄いチョコレートを頬張った。
「……にがっ!」
甘いものだと思っていたら全然違った。予想外のヘビーな苦味に口の中がパニくる。悶えるわたしを見て、春斗くんが笑いをこらえてる。
甘いものだと思っていたら全然違った。予想外のヘビーな苦味に口の中がパニくる。悶えるわたしを見て、春斗くんが笑いをこらえてる。
「それ砂糖不使用」
「先に言ってよぉ」
「甘いとは限らないだろ」
「チョコはふつう甘いの!」
「甘いとは限らないだろ」
「チョコはふつう甘いの!」
涙目になりながら反論すると、春斗くんが
「ウサギは甘くないとだめだもんな。ほら、流し込め」とマグカップを差し出した。
受け取るとカップの中身はマイルドなカフェオレだった。適温で美味しい。生き返る。ありがたい心づかいに感謝。
「ウサギは甘くないとだめだもんな。ほら、流し込め」とマグカップを差し出した。
受け取るとカップの中身はマイルドなカフェオレだった。適温で美味しい。生き返る。ありがたい心づかいに感謝。
「このチョコくれたひと、意地悪じゃない?」
向かいに座った春斗くんに同意を求めると、
「慣れればうまいよ。紀元前から薬として扱われてるくらしだし、血流改善とか、コレステロールの抑制とか。無糖だとなおさら体にいい」
「慣れればうまいよ。紀元前から薬として扱われてるくらしだし、血流改善とか、コレステロールの抑制とか。無糖だとなおさら体にいい」
「製薬会社の女子が選ぶチョコは、さすが味も健康的」
「それ取引先の――あ、いやなんでもない」
「それ取引先の――あ、いやなんでもない」
春斗くんがめちゃくちゃ気になるところで言葉を切った。胸の中に、これまでと違う気持ちが生まれた。ざらざらとした感情だった。
「取引先? 隠さなきゃいけないような相手なの」
わたしは余裕もなく訊ねていた。
「取引先? 隠さなきゃいけないような相手なの」
わたしは余裕もなく訊ねていた。
「んー……さっきの電話の、友達の友達にもらった」
「もしかして、その人と今日会うはずだった?」
「もしかして、その人と今日会うはずだった?」
さらに突っ込むと、「まあそんなとこ」と春斗くんが目をそらした。
デートだったんだ。超ショック。推測するに、春斗くんの友達が無糖チョコをくれた女の子の仲介役で、引き合わせるために電話してきた――そういうことだよね。
ここ数年で、一、二を争うレベルの動揺に、脳しんとうをおこしそうになった。息が止まりそう。深呼吸、深呼吸しなきゃ。
「春斗くん、ごめんね。もう帰るから準備して」
「さっき行かないって断ったの聞いてなかった?」
「聞いてたけど。でもだけど!」
「さっき行かないって断ったの聞いてなかった?」
「聞いてたけど。でもだけど!」
焦るわたしとは対照的に、春斗くんがのんびりとコーヒーをすすってる。
「行かなくていいの」
「行って欲しいのか」
「行って欲しいのか」
やだ。やだやだ。行かないで欲しい。でもそんなこと言ったら、春斗くんのこと好きだってバレちゃうよ。落ち着こう。気持ちをセーブでしょ!
「念のため訊くけど。ウサギの代わりに、無糖女子の肩抱き寄せてキスして、ホテルでエッチなことしてもいいんだ?」
「え、えええ? いまなんておっしゃいました? わたしの代わりに?」
「代わりに」
「そんなのダメに決まってるでしょ!!」
思わず力説すると、春斗くんが安堵したような表情を浮かべた。
「そう言ってくれなきゃ終わるとこだった」
思わず力説すると、春斗くんが安堵したような表情を浮かべた。
「そう言ってくれなきゃ終わるとこだった」
終わる? どういう意味? 確かめたいけど怖くて訊けない。ひとりざわつくわたしを尻目に、春斗くんがカゴのチョコをひと箱取り上げた。
ぴりぴりと音を立て、包装紙を破いていく。箱を開けると、ひとくち大のハートが並んだ可愛いチョコの詰め合わせだった。一粒つまんで、春斗くんが口に含む。
「俺の好きな子知ってる? その子からはもらえなかったんだよ。去年も今年も」
「そ、それって」
思い当たる。わたし、高校を卒業してから春斗くんにあげてない。高校生までは勢いで毎年渡してたけど、去年はなんだか気後れして。
「そ、それって」
思い当たる。わたし、高校を卒業してから春斗くんにあげてない。高校生までは勢いで毎年渡してたけど、去年はなんだか気後れして。
今年は春斗くんが一月の終わりから二月中旬までドイツに出張だったのもあって、バレンタイン当日にあげられないなら……と軽い気持ちでやめたんだ。
「ほかに好きなやつができたのかと思ってた」
「ちょ……それってなんか、わたしが春斗くんを好きみたいに聞こえ――」
「違うの?」
「ちょ……それってなんか、わたしが春斗くんを好きみたいに聞こえ――」
「違うの?」
テーブルに身を乗り出した春斗くんが、ふわりとわたしにキスした。
唇が重なり体に電気が走る。
心臓が盛大に跳ね上がった。
「は、春斗く……」
間を置かず、もう一度キスされた。春斗くんの舌の上で溶けたハートのチョコレートが、わたしの舌先にのる。文字通りの甘いキスに思考回路がショート寸前……!
「莉衣《りい》は誰が好きなんだよ」
不意に本名で呼ばれ、体がじりじりと熱くなる。
不意に本名で呼ばれ、体がじりじりと熱くなる。
言っていいの? 伝えていいの? もう隠さなくていいの?
「春斗くんが……好き」
俺も莉衣が好きだよ、と春斗くんが囁いた。とてつもなく甘美な、極上の夢を見てるみたいだった。
「春斗くんが……好き」
俺も莉衣が好きだよ、と春斗くんが囁いた。とてつもなく甘美な、極上の夢を見てるみたいだった。
「おばさんに伝えといて。俺が今夜食べたいのは、莉衣だって」
オオカミ発言に煽られて、一気に頬が熱くなる。
「こ、殺されるよ!」
「祝福されるの間違いだろ」
「その自信はどこからくるの……」
オオカミ発言に煽られて、一気に頬が熱くなる。
「こ、殺されるよ!」
「祝福されるの間違いだろ」
「その自信はどこからくるの……」
ああ、でもあらためて思えば、お母さんて何かにつけ春斗くんのこと「優秀」だとか「いい子」だとか話してた。頼まれてもいないのにたくさんお料理作って持たせるし。気に入ってるのは疑いようもない。だとしても。
「今夜はだめ。わたし上手く応えられないもん。時間ちょうだい。練習したいの!」
「ほかの男と?」
「ひとりで」
「意味不」
春斗くんがこらえ切れず吹き出した。
わたしは至って真面目なんですが。
「ほかの男と?」
「ひとりで」
「意味不」
春斗くんがこらえ切れず吹き出した。
わたしは至って真面目なんですが。
「ばかだな。俺と練習しろよ」
遅れてやって来たバレンタインは、思いがけず糖度高めの甘々仕様だった。
「いろいろ教えてやるから覚悟しとけ」と不敵に笑う春斗くんは、抗いがたいほど魅力的で。抱き寄せられた腕の中で溶ろけてしまいそうだった。
【了】