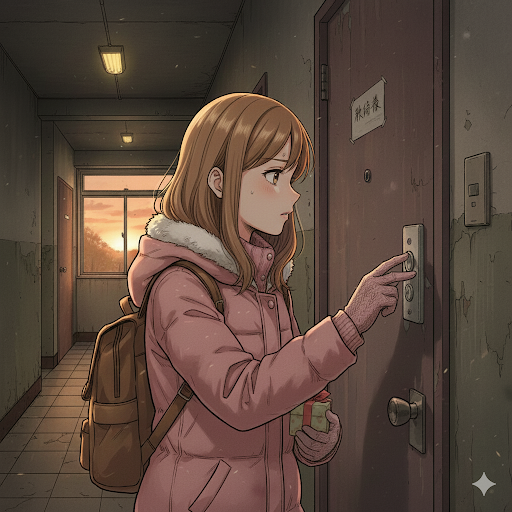軌跡
ー/ー 雲の隙間から、柔らかな日差しが差し込む。凍てつくような朝の空気を伝って、だんだんと近づいてくる鈴の音と賑やかな人々の声に、私は長い眠りから目を覚ました。
「おはよう、みんな。久しぶり」
白い息を吐きながら我先にと駆けてくる人々は、紙切れをスタッフに手渡すと、近くのベンチに座って急いで靴を履き替えている。その隣に設置されている券売機の前には、あっという間に長蛇の列ができあがった。
「そんなに焦らなくても私は逃げないよ。ゆっくり、順番にね」
私の制止も聞かず、一番初めに勢いよくゲートをくぐったのは、若い学生のグループだ。朝早くからずっと並んで待っていたのだろうか、大はしゃぎで一斉に駆け出していく。とても賑やかで楽しそうだ。少し遅れて次にゲートをくぐったのは、小さな子供連れの家族。初めにパパが、続いてママが足を踏み入れる。でも、小さな男の子は少し不安そうで、ゲートの縁を掴んで離さない。
「初めての世界は、怖いよね。でも、一歩踏み出してみようよ。さあ、パパとママの手を取って」
私は男の子に優しく語りかける。ようやく決心がついたのか、男の子は縁から手を離してそっと片足を前に出した。しかし、その拍子にバランスを崩して転んでしまう。
「あっ!ごめんね。私、うまく加減ができないんだ」
目に涙を浮かべる男の子の姿に、何もできない私は申し訳ない気持ちでいっぱいになる。
「痛いよね。冷たいよね。どうか、泣かないで。もう一度、二人の手を掴んでみて」
男の子は、差し伸べられた両親の手を取り、ふらふらと立ち上がる。
「そう、その調子。怖くても、一歩踏み出す勇気があれば大丈夫。後は流れに身を任せて…」
一度は離してしまった両親の手をしっかりと握り、そのままゆっくりと前進する。
「ほら!進んだ!やったね!」
不安に満ちていた男の子の表情は、次第にきらきらと明るい笑顔に変わる。いつもとは違う地面の感覚も、繋ぎ止めた家族の手も、きっと素敵な思い出になるだろう。背丈の異なる三人の後ろ姿を、和やかな気持ちで見送る。
「おや…」
続々とゲートをくぐる人々。その中で、純白のシューズを纏った女の子が目に留まった。はしゃいで横並びになってしまう人々や、転んでしまう人もいる中で、彼女はスムーズに流れに乗りつつ華麗にその間を縫って進む。
「あの子だ!」
私は確信する。毎年必ずここに来てくれる、とても上手な女の子。他の人のことももちろん覚えているけれど、この子は特によく覚えている。ベンチや券売機に並ぶ人の視線も釘付けだ。ひそひそと何かを話している人もいる。彼女はそれを気に留めず、慣れた様子で私の上を反時計回りに進む。しかし、軽快なその姿とは対照的に、彼女の表情は雪雲のように暗く沈んでいた。
「ねえ、どうしてそんなに、悲しい顔をしているの?」
「みんな笑顔なのに、とっても上手なのに…どうしてあなたは、ずっと苦しそうなの?」
問いかけても、私の声は届かない。私からあなたに触れることもできない。私にできるのは、ただ見守って、その姿を覚えておくことだけだ。
空高く昇る陽の光が、私の頬を伝う雫を照らした。
だんだんと冷え込みが穏やかになって、閉園を告げる音楽にも聞き飽きてくる頃、人々は次第に私の元を離れていく。賑わっていた日中の光景が嘘のように、気づけば辺りはしんと静まり返っていた。しばらくして、機械の駆動音とともに、大きな鉄の塊が私のもとへやって来る。作業服を着た人々が私を取り囲んだら、また長い眠りにつく合図だ。
春は出会いと別れの季節なんて言うけれど、私にとっては別れだけだ。明日の朝になれば、全部消えて無くなってしまう。そうして時の流れとともに、少しずつ忘れられていく。
でも、寂しくなんかないよ。少し経てばまた会えるから。その時には、何も無かったみたいにまっさらになっているけれど、みんなの代わりに私がちゃんと覚えているから。だからまた、会いに来てね。
一年先に思いを馳せて、私はゆっくりと眠りについた。
暖かな春が来て、溶けるような夏が来て、流れるように秋が過ぎて…。また、凍えるような冬が訪れる。
描いては消え、描かれては消え。何度も何度も、繰り返す。そうやってずっと、いつまでも続いていく。
「おはよう、みんな。久しぶり!また会えたね」
古びたスピーカーから流れる少しこもったような鈴の音と、まばらな人々の声に、私はゆっくりと目を覚ます。今年もまた、この季節がやってきた。
…でも、永遠なんてないって私は知っている。いや、知ってしまったんだ。
「ねえ、聞いた?今年で最後なんだって、このスケートリンク」
「えー、嘘ー」
「本当だって!ホームページで見たもん。老朽化と経営難で、季節もののイベントはもうできないらしいよ」
「そっか〜、毎年来てたのにね」
「終わったら取り壊されちゃうのかな」
「そうだろうねー、残念だけど…」
ベンチに横並びに座って靴を履き替える、女子高生の二人組の会話。突然突きつけられた「最期」の冬を、私は受け入れるしかなかった。
春の足音が近づいてくる。最終日と書かれた看板に引き寄せられるようにして、今までよりもたくさんの人が私の元へやって来ていた。混雑緩和のためか券売機は撤去され、スタッフの仕事も、紙切れのもぎりからスマートフォンの画面読み取りになっている。それでも、入場口には押し寄せた人々が列を作っていた。
何時間も前から開園を待っていたであろう男女のグループが、大はしゃぎでゲートをくぐった。少し背が伸びた少年は、両親の手を借りることなく、自分の足でゆっくりと進んでいく。老若男女で賑わう会場。でも、あの子の姿は見つからない。毎日必死になって探していたけれど、風をきって私の上を舞っていた彼女は、どこにも見当たらなかった。
あっという間に陽は沈み、最期の夜が訪れる。メロディを口ずさめるくらい何度も聞いた音楽もついに途切れて、辺りの照明がふっと落とされた。結局、彼女には会えなかった。唯一の心残りはどんどん膨らんで、私を埋め尽くしていく。
あの子の滑る姿、すごく好きだったんだ。忘れられてもいいって言っていたのに、忘れないでって思ってしまうなんて。私の体は動かないし、声だって出せない。ここを飛び出して、探しに行くこともままならない。
ああ、どうしよう。どうすることもできないのに。
最期に一度だけ、少しだけでもいいから、あの子に会いたいって思ってしまうなんて。
その時。
――カンッ!
純白のシューズを高らかに鳴らして、リンクの中央へ滑走する一人の女性。白と水色のドレスにあしらわれた装飾がスポットライトに照らされて、宝石のようにきらきらと光り輝く。華やかな衣装に身を包んだ「あの子」は、錆びついたスピーカーから流れるソナタとともに、滑らかに氷上を舞う。
「あぁ…」
その姿、その滑り方。ずっと大切にしまっていた記憶が、宝箱を開けるようにして、次々と私の頭を駆け巡る。
「やっと、会えたね」
イベント最終日の閉園間際。この日を記念して、地元のスケーターによるエキシビションが開催されるという話は耳にしていた。でも、まさか彼女がそうだったなんて。真っ暗で分からなかったが、気づけばたくさんの人々が私の周りを取り囲んでいた。ベンチは満席、リンクの縁に沿って何重にも隙間なく立ち見の人々が並び、彼女の演技に息を呑んでいる。繊細なピアノで紡がれるソナタは、次第にストリングスが重なり、情熱的な旋律へ展開していく。
かつて、冬が来るたびに私の上を滑っていた「あの子」は、数年の時を経て、アマチュアスケーターとして再出発を切った。その過程に何があったのか、どれほどの苦悩があったのか、私に知る由はない。ただ一つ確かなことは、悲しみと苦しみを抱えていた彼女の軌跡が、明日への希望と喜びに満ちた、力強いものへと変化を遂げたということだった。リンクを滑走する彼女は軽く息を整えると、助走をつけて高く飛び上がり、三回転半の螺旋を描く。
「…綺麗」
思わず溢れた言葉。この景色を、ずっと見ていたい。終わりが来てほしくない。時間が止まってしまえばいいのに。スピーカーが壊れて、音楽がずっと鳴り続ければいいのに。そんな自分勝手な願いを嘲笑うように、音楽は終盤に差し掛かる。彼女はそのまま鮮やかなステップでステージの中央に移動すると、体を捻り回転し始めた。高さと速さを自在に変える、スピンコンビネーション。その軸がブレることはない。しなやかで繊細かつ芯の通った、彼女の意志がそのまま現れたようなスピン。壮大なストリングスとともに、フィナーレを迎える。
どこまでも高く続く空。その先に煌めく星々を掴むように、彼女は伸ばした手をゆっくりと握りしめた。
一瞬の静寂を切り裂くようにして、割れんばかりの歓声と拍手が辺りを包み込む。
「すごい…すごいよ!やっぱりみんな、あなたの滑る姿が大好きなんだ!」
私は彼女を誇らしげに思う。しかし、ノーミスで滑り切った達成感と安堵からか、彼女は目を潤ませて、その場にしゃがみ込んでしまった。
「上手だったよ!大丈夫、自信を持って。胸を張って、これからも羽ばたいていって」
両腕を広げて抱きしめてあげたいけれど、私にはできない。その代わりに、届くことのない心からの賞賛とエールを送り続ける。
「ここはあなたには狭すぎるから…。寂しいけれど、忘れてもいいよ。私が代わりに覚えておくから」
その時、彼女は両膝を冷たい地面について、そっと私に手を触れる。
「…ありがとう」
小さく震える声で呟かれた五文字。鳴り止まない歓声と拍手の中で、その言葉は私の耳に確かに届けられた。
そして私は初めて、辺りを包む観客の声が、拍手の音が、彼女だけではなく自身にも向けられたものであることに気づく。
「ありがとー!」
「また会おうね!」
「大好きだよー!」
ああ、そうか。
私だけじゃなかったんだ。
忘れたくないのも、会えなくなってしまうのが辛いのも、別れが惜しいのも…みんな同じだったんだ。
届かないはずの言葉が、心が通じ合ったような気がして、胸の奥に抑えていた感情が溢れ出しそうになる。
どうしよう、泣かせないでよ。氷が溶けちゃうから。
涙が溢れないように、上を向く。果てしなく広がる夜空を伝う流星の煌めきを、私は目に焼き付けた。
次第に人々の声は少なくなり、辺りは再び静寂に包まれる。否応なく最期と向き合うことになった私の心に、忘れかけていた寂しさが再び込み上げてきた。別れは寂しい。今までは一年経ったらまた会えるって思っていたからなんとも思わなかったけれど、これからもう会えなくなるなんて。もう、久しぶりって言えないなんて。
…でも、大丈夫。私がいなくなっても、みんな前に進んでいける。いつかまた私のことを思い出してなんて、我儘は言わない。粉々に砕かれてしまっても、氷が全部溶けてしまっても、何も形に残らなかったとしても。私がみんなの思い出を、みんなと描いてきた軌跡を、ちゃんと全部覚えているから。
だから、どうかこれからも、一歩踏み出すことを忘れないで。転んでも大丈夫。また立ち上がればいい。繋いだ手を離してしまっても大丈夫。また手を取り合って、強く握り直せばいい。迷ってもいい。ふらついていてもいい。あなたが私に描いた軌跡は、いつか空の星に届くくらいに、あなた自身を高く飛び上がらせるバネになるから。
「おはよう、みんな。久しぶり」
白い息を吐きながら我先にと駆けてくる人々は、紙切れをスタッフに手渡すと、近くのベンチに座って急いで靴を履き替えている。その隣に設置されている券売機の前には、あっという間に長蛇の列ができあがった。
「そんなに焦らなくても私は逃げないよ。ゆっくり、順番にね」
私の制止も聞かず、一番初めに勢いよくゲートをくぐったのは、若い学生のグループだ。朝早くからずっと並んで待っていたのだろうか、大はしゃぎで一斉に駆け出していく。とても賑やかで楽しそうだ。少し遅れて次にゲートをくぐったのは、小さな子供連れの家族。初めにパパが、続いてママが足を踏み入れる。でも、小さな男の子は少し不安そうで、ゲートの縁を掴んで離さない。
「初めての世界は、怖いよね。でも、一歩踏み出してみようよ。さあ、パパとママの手を取って」
私は男の子に優しく語りかける。ようやく決心がついたのか、男の子は縁から手を離してそっと片足を前に出した。しかし、その拍子にバランスを崩して転んでしまう。
「あっ!ごめんね。私、うまく加減ができないんだ」
目に涙を浮かべる男の子の姿に、何もできない私は申し訳ない気持ちでいっぱいになる。
「痛いよね。冷たいよね。どうか、泣かないで。もう一度、二人の手を掴んでみて」
男の子は、差し伸べられた両親の手を取り、ふらふらと立ち上がる。
「そう、その調子。怖くても、一歩踏み出す勇気があれば大丈夫。後は流れに身を任せて…」
一度は離してしまった両親の手をしっかりと握り、そのままゆっくりと前進する。
「ほら!進んだ!やったね!」
不安に満ちていた男の子の表情は、次第にきらきらと明るい笑顔に変わる。いつもとは違う地面の感覚も、繋ぎ止めた家族の手も、きっと素敵な思い出になるだろう。背丈の異なる三人の後ろ姿を、和やかな気持ちで見送る。
「おや…」
続々とゲートをくぐる人々。その中で、純白のシューズを纏った女の子が目に留まった。はしゃいで横並びになってしまう人々や、転んでしまう人もいる中で、彼女はスムーズに流れに乗りつつ華麗にその間を縫って進む。
「あの子だ!」
私は確信する。毎年必ずここに来てくれる、とても上手な女の子。他の人のことももちろん覚えているけれど、この子は特によく覚えている。ベンチや券売機に並ぶ人の視線も釘付けだ。ひそひそと何かを話している人もいる。彼女はそれを気に留めず、慣れた様子で私の上を反時計回りに進む。しかし、軽快なその姿とは対照的に、彼女の表情は雪雲のように暗く沈んでいた。
「ねえ、どうしてそんなに、悲しい顔をしているの?」
「みんな笑顔なのに、とっても上手なのに…どうしてあなたは、ずっと苦しそうなの?」
問いかけても、私の声は届かない。私からあなたに触れることもできない。私にできるのは、ただ見守って、その姿を覚えておくことだけだ。
空高く昇る陽の光が、私の頬を伝う雫を照らした。
だんだんと冷え込みが穏やかになって、閉園を告げる音楽にも聞き飽きてくる頃、人々は次第に私の元を離れていく。賑わっていた日中の光景が嘘のように、気づけば辺りはしんと静まり返っていた。しばらくして、機械の駆動音とともに、大きな鉄の塊が私のもとへやって来る。作業服を着た人々が私を取り囲んだら、また長い眠りにつく合図だ。
春は出会いと別れの季節なんて言うけれど、私にとっては別れだけだ。明日の朝になれば、全部消えて無くなってしまう。そうして時の流れとともに、少しずつ忘れられていく。
でも、寂しくなんかないよ。少し経てばまた会えるから。その時には、何も無かったみたいにまっさらになっているけれど、みんなの代わりに私がちゃんと覚えているから。だからまた、会いに来てね。
一年先に思いを馳せて、私はゆっくりと眠りについた。
暖かな春が来て、溶けるような夏が来て、流れるように秋が過ぎて…。また、凍えるような冬が訪れる。
描いては消え、描かれては消え。何度も何度も、繰り返す。そうやってずっと、いつまでも続いていく。
「おはよう、みんな。久しぶり!また会えたね」
古びたスピーカーから流れる少しこもったような鈴の音と、まばらな人々の声に、私はゆっくりと目を覚ます。今年もまた、この季節がやってきた。
…でも、永遠なんてないって私は知っている。いや、知ってしまったんだ。
「ねえ、聞いた?今年で最後なんだって、このスケートリンク」
「えー、嘘ー」
「本当だって!ホームページで見たもん。老朽化と経営難で、季節もののイベントはもうできないらしいよ」
「そっか〜、毎年来てたのにね」
「終わったら取り壊されちゃうのかな」
「そうだろうねー、残念だけど…」
ベンチに横並びに座って靴を履き替える、女子高生の二人組の会話。突然突きつけられた「最期」の冬を、私は受け入れるしかなかった。
春の足音が近づいてくる。最終日と書かれた看板に引き寄せられるようにして、今までよりもたくさんの人が私の元へやって来ていた。混雑緩和のためか券売機は撤去され、スタッフの仕事も、紙切れのもぎりからスマートフォンの画面読み取りになっている。それでも、入場口には押し寄せた人々が列を作っていた。
何時間も前から開園を待っていたであろう男女のグループが、大はしゃぎでゲートをくぐった。少し背が伸びた少年は、両親の手を借りることなく、自分の足でゆっくりと進んでいく。老若男女で賑わう会場。でも、あの子の姿は見つからない。毎日必死になって探していたけれど、風をきって私の上を舞っていた彼女は、どこにも見当たらなかった。
あっという間に陽は沈み、最期の夜が訪れる。メロディを口ずさめるくらい何度も聞いた音楽もついに途切れて、辺りの照明がふっと落とされた。結局、彼女には会えなかった。唯一の心残りはどんどん膨らんで、私を埋め尽くしていく。
あの子の滑る姿、すごく好きだったんだ。忘れられてもいいって言っていたのに、忘れないでって思ってしまうなんて。私の体は動かないし、声だって出せない。ここを飛び出して、探しに行くこともままならない。
ああ、どうしよう。どうすることもできないのに。
最期に一度だけ、少しだけでもいいから、あの子に会いたいって思ってしまうなんて。
その時。
――カンッ!
純白のシューズを高らかに鳴らして、リンクの中央へ滑走する一人の女性。白と水色のドレスにあしらわれた装飾がスポットライトに照らされて、宝石のようにきらきらと光り輝く。華やかな衣装に身を包んだ「あの子」は、錆びついたスピーカーから流れるソナタとともに、滑らかに氷上を舞う。
「あぁ…」
その姿、その滑り方。ずっと大切にしまっていた記憶が、宝箱を開けるようにして、次々と私の頭を駆け巡る。
「やっと、会えたね」
イベント最終日の閉園間際。この日を記念して、地元のスケーターによるエキシビションが開催されるという話は耳にしていた。でも、まさか彼女がそうだったなんて。真っ暗で分からなかったが、気づけばたくさんの人々が私の周りを取り囲んでいた。ベンチは満席、リンクの縁に沿って何重にも隙間なく立ち見の人々が並び、彼女の演技に息を呑んでいる。繊細なピアノで紡がれるソナタは、次第にストリングスが重なり、情熱的な旋律へ展開していく。
かつて、冬が来るたびに私の上を滑っていた「あの子」は、数年の時を経て、アマチュアスケーターとして再出発を切った。その過程に何があったのか、どれほどの苦悩があったのか、私に知る由はない。ただ一つ確かなことは、悲しみと苦しみを抱えていた彼女の軌跡が、明日への希望と喜びに満ちた、力強いものへと変化を遂げたということだった。リンクを滑走する彼女は軽く息を整えると、助走をつけて高く飛び上がり、三回転半の螺旋を描く。
「…綺麗」
思わず溢れた言葉。この景色を、ずっと見ていたい。終わりが来てほしくない。時間が止まってしまえばいいのに。スピーカーが壊れて、音楽がずっと鳴り続ければいいのに。そんな自分勝手な願いを嘲笑うように、音楽は終盤に差し掛かる。彼女はそのまま鮮やかなステップでステージの中央に移動すると、体を捻り回転し始めた。高さと速さを自在に変える、スピンコンビネーション。その軸がブレることはない。しなやかで繊細かつ芯の通った、彼女の意志がそのまま現れたようなスピン。壮大なストリングスとともに、フィナーレを迎える。
どこまでも高く続く空。その先に煌めく星々を掴むように、彼女は伸ばした手をゆっくりと握りしめた。
一瞬の静寂を切り裂くようにして、割れんばかりの歓声と拍手が辺りを包み込む。
「すごい…すごいよ!やっぱりみんな、あなたの滑る姿が大好きなんだ!」
私は彼女を誇らしげに思う。しかし、ノーミスで滑り切った達成感と安堵からか、彼女は目を潤ませて、その場にしゃがみ込んでしまった。
「上手だったよ!大丈夫、自信を持って。胸を張って、これからも羽ばたいていって」
両腕を広げて抱きしめてあげたいけれど、私にはできない。その代わりに、届くことのない心からの賞賛とエールを送り続ける。
「ここはあなたには狭すぎるから…。寂しいけれど、忘れてもいいよ。私が代わりに覚えておくから」
その時、彼女は両膝を冷たい地面について、そっと私に手を触れる。
「…ありがとう」
小さく震える声で呟かれた五文字。鳴り止まない歓声と拍手の中で、その言葉は私の耳に確かに届けられた。
そして私は初めて、辺りを包む観客の声が、拍手の音が、彼女だけではなく自身にも向けられたものであることに気づく。
「ありがとー!」
「また会おうね!」
「大好きだよー!」
ああ、そうか。
私だけじゃなかったんだ。
忘れたくないのも、会えなくなってしまうのが辛いのも、別れが惜しいのも…みんな同じだったんだ。
届かないはずの言葉が、心が通じ合ったような気がして、胸の奥に抑えていた感情が溢れ出しそうになる。
どうしよう、泣かせないでよ。氷が溶けちゃうから。
涙が溢れないように、上を向く。果てしなく広がる夜空を伝う流星の煌めきを、私は目に焼き付けた。
次第に人々の声は少なくなり、辺りは再び静寂に包まれる。否応なく最期と向き合うことになった私の心に、忘れかけていた寂しさが再び込み上げてきた。別れは寂しい。今までは一年経ったらまた会えるって思っていたからなんとも思わなかったけれど、これからもう会えなくなるなんて。もう、久しぶりって言えないなんて。
…でも、大丈夫。私がいなくなっても、みんな前に進んでいける。いつかまた私のことを思い出してなんて、我儘は言わない。粉々に砕かれてしまっても、氷が全部溶けてしまっても、何も形に残らなかったとしても。私がみんなの思い出を、みんなと描いてきた軌跡を、ちゃんと全部覚えているから。
だから、どうかこれからも、一歩踏み出すことを忘れないで。転んでも大丈夫。また立ち上がればいい。繋いだ手を離してしまっても大丈夫。また手を取り合って、強く握り直せばいい。迷ってもいい。ふらついていてもいい。あなたが私に描いた軌跡は、いつか空の星に届くくらいに、あなた自身を高く飛び上がらせるバネになるから。
「またね」
冷たい空気を胸いっぱいに吸い込んで、誰にも聞こえない声で呟いた。遠くから、重機の駆動音が聞こえてくる。
今日のことを、これまでのことを全部、ずっと忘れずに覚えていられますように。
月の光に照らされて、銀盤に刻まれたかけがえのない軌跡が、煌々と輝いていた。
―了―
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
雲の隙間から、柔らかな日差しが差し込む。凍てつくような朝の空気を伝って、だんだんと近づいてくる鈴の音と賑やかな人々の声に、私は長い眠りから目を覚ました。
「おはよう、みんな。久しぶり」
白い息を吐きながら我先にと駆けてくる人々は、紙切れをスタッフに手渡すと、近くのベンチに座って急いで靴を履き替えている。その隣に設置されている券売機の前には、あっという間に長蛇の列ができあがった。
「そんなに焦らなくても私は逃げないよ。ゆっくり、順番にね」
私の制止も聞かず、一番初めに勢いよくゲートをくぐったのは、若い学生のグループだ。朝早くからずっと並んで待っていたのだろうか、大はしゃぎで一斉に駆け出していく。とても賑やかで楽しそうだ。少し遅れて次にゲートをくぐったのは、小さな子供連れの家族。初めにパパが、続いてママが足を踏み入れる。でも、小さな男の子は少し不安そうで、ゲートの縁を掴んで離さない。
「初めての世界は、怖いよね。でも、一歩踏み出してみようよ。さあ、パパとママの手を取って」
私は男の子に優しく語りかける。ようやく決心がついたのか、男の子は縁から手を離してそっと片足を前に出した。しかし、その拍子にバランスを崩して転んでしまう。
「あっ!ごめんね。私、うまく加減ができないんだ」
目に涙を浮かべる男の子の姿に、何もできない私は申し訳ない気持ちでいっぱいになる。
「痛いよね。冷たいよね。どうか、泣かないで。もう一度、二人の手を掴んでみて」
男の子は、差し伸べられた両親の手を取り、ふらふらと立ち上がる。
「そう、その調子。怖くても、一歩踏み出す勇気があれば大丈夫。後は流れに身を任せて…」
一度は離してしまった両親の手をしっかりと握り、そのままゆっくりと前進する。
「ほら!進んだ!やったね!」
不安に満ちていた男の子の表情は、次第にきらきらと明るい笑顔に変わる。いつもとは違う地面の感覚も、繋ぎ止めた家族の手も、きっと素敵な思い出になるだろう。背丈の異なる三人の後ろ姿を、和やかな気持ちで見送る。
「おや…」
続々とゲートをくぐる人々。その中で、純白のシューズを纏った女の子が目に留まった。はしゃいで横並びになってしまう人々や、転んでしまう人もいる中で、彼女はスムーズに流れに乗りつつ華麗にその間を縫って進む。
「あの子だ!」
私は確信する。毎年必ずここに来てくれる、とても上手な女の子。他の人のことももちろん覚えているけれど、この子は特によく覚えている。ベンチや券売機に並ぶ人の視線も釘付けだ。ひそひそと何かを話している人もいる。彼女はそれを気に留めず、慣れた様子で私の上を反時計回りに進む。しかし、軽快なその姿とは対照的に、彼女の表情は雪雲のように暗く沈んでいた。
「ねえ、どうしてそんなに、悲しい顔をしているの?」
「みんな笑顔なのに、とっても上手なのに…どうしてあなたは、ずっと苦しそうなの?」
問いかけても、私の声は届かない。私からあなたに触れることもできない。私にできるのは、ただ見守って、その姿を覚えておくことだけだ。
空高く昇る陽の光が、私の頬を伝う雫を照らした。
「おはよう、みんな。久しぶり」
白い息を吐きながら我先にと駆けてくる人々は、紙切れをスタッフに手渡すと、近くのベンチに座って急いで靴を履き替えている。その隣に設置されている券売機の前には、あっという間に長蛇の列ができあがった。
「そんなに焦らなくても私は逃げないよ。ゆっくり、順番にね」
私の制止も聞かず、一番初めに勢いよくゲートをくぐったのは、若い学生のグループだ。朝早くからずっと並んで待っていたのだろうか、大はしゃぎで一斉に駆け出していく。とても賑やかで楽しそうだ。少し遅れて次にゲートをくぐったのは、小さな子供連れの家族。初めにパパが、続いてママが足を踏み入れる。でも、小さな男の子は少し不安そうで、ゲートの縁を掴んで離さない。
「初めての世界は、怖いよね。でも、一歩踏み出してみようよ。さあ、パパとママの手を取って」
私は男の子に優しく語りかける。ようやく決心がついたのか、男の子は縁から手を離してそっと片足を前に出した。しかし、その拍子にバランスを崩して転んでしまう。
「あっ!ごめんね。私、うまく加減ができないんだ」
目に涙を浮かべる男の子の姿に、何もできない私は申し訳ない気持ちでいっぱいになる。
「痛いよね。冷たいよね。どうか、泣かないで。もう一度、二人の手を掴んでみて」
男の子は、差し伸べられた両親の手を取り、ふらふらと立ち上がる。
「そう、その調子。怖くても、一歩踏み出す勇気があれば大丈夫。後は流れに身を任せて…」
一度は離してしまった両親の手をしっかりと握り、そのままゆっくりと前進する。
「ほら!進んだ!やったね!」
不安に満ちていた男の子の表情は、次第にきらきらと明るい笑顔に変わる。いつもとは違う地面の感覚も、繋ぎ止めた家族の手も、きっと素敵な思い出になるだろう。背丈の異なる三人の後ろ姿を、和やかな気持ちで見送る。
「おや…」
続々とゲートをくぐる人々。その中で、純白のシューズを纏った女の子が目に留まった。はしゃいで横並びになってしまう人々や、転んでしまう人もいる中で、彼女はスムーズに流れに乗りつつ華麗にその間を縫って進む。
「あの子だ!」
私は確信する。毎年必ずここに来てくれる、とても上手な女の子。他の人のことももちろん覚えているけれど、この子は特によく覚えている。ベンチや券売機に並ぶ人の視線も釘付けだ。ひそひそと何かを話している人もいる。彼女はそれを気に留めず、慣れた様子で私の上を反時計回りに進む。しかし、軽快なその姿とは対照的に、彼女の表情は雪雲のように暗く沈んでいた。
「ねえ、どうしてそんなに、悲しい顔をしているの?」
「みんな笑顔なのに、とっても上手なのに…どうしてあなたは、ずっと苦しそうなの?」
問いかけても、私の声は届かない。私からあなたに触れることもできない。私にできるのは、ただ見守って、その姿を覚えておくことだけだ。
空高く昇る陽の光が、私の頬を伝う雫を照らした。
だんだんと冷え込みが穏やかになって、閉園を告げる音楽にも聞き飽きてくる頃、人々は次第に私の元を離れていく。賑わっていた日中の光景が嘘のように、気づけば辺りはしんと静まり返っていた。しばらくして、機械の駆動音とともに、大きな鉄の塊が私のもとへやって来る。作業服を着た人々が私を取り囲んだら、また長い眠りにつく合図だ。
春は出会いと別れの季節なんて言うけれど、私にとっては別れだけだ。明日の朝になれば、全部消えて無くなってしまう。そうして時の流れとともに、少しずつ忘れられていく。
でも、寂しくなんかないよ。少し経てばまた会えるから。その時には、何も無かったみたいにまっさらになっているけれど、みんなの代わりに私がちゃんと覚えているから。だからまた、会いに来てね。
一年先に思いを馳せて、私はゆっくりと眠りについた。
春は出会いと別れの季節なんて言うけれど、私にとっては別れだけだ。明日の朝になれば、全部消えて無くなってしまう。そうして時の流れとともに、少しずつ忘れられていく。
でも、寂しくなんかないよ。少し経てばまた会えるから。その時には、何も無かったみたいにまっさらになっているけれど、みんなの代わりに私がちゃんと覚えているから。だからまた、会いに来てね。
一年先に思いを馳せて、私はゆっくりと眠りについた。
暖かな春が来て、溶けるような夏が来て、流れるように秋が過ぎて…。また、凍えるような冬が訪れる。
描いては消え、描かれては消え。何度も何度も、繰り返す。そうやってずっと、いつまでも続いていく。
「おはよう、みんな。久しぶり!また会えたね」
古びたスピーカーから流れる少しこもったような鈴の音と、まばらな人々の声に、私はゆっくりと目を覚ます。今年もまた、この季節がやってきた。
…でも、永遠なんてないって私は知っている。いや、知ってしまったんだ。
「ねえ、聞いた?今年で最後なんだって、このスケートリンク」
「えー、嘘ー」
「本当だって!ホームページで見たもん。老朽化と経営難で、季節もののイベントはもうできないらしいよ」
「そっか〜、毎年来てたのにね」
「終わったら取り壊されちゃうのかな」
「そうだろうねー、残念だけど…」
ベンチに横並びに座って靴を履き替える、女子高生の二人組の会話。突然突きつけられた「最期」の冬を、私は受け入れるしかなかった。
描いては消え、描かれては消え。何度も何度も、繰り返す。そうやってずっと、いつまでも続いていく。
「おはよう、みんな。久しぶり!また会えたね」
古びたスピーカーから流れる少しこもったような鈴の音と、まばらな人々の声に、私はゆっくりと目を覚ます。今年もまた、この季節がやってきた。
…でも、永遠なんてないって私は知っている。いや、知ってしまったんだ。
「ねえ、聞いた?今年で最後なんだって、このスケートリンク」
「えー、嘘ー」
「本当だって!ホームページで見たもん。老朽化と経営難で、季節もののイベントはもうできないらしいよ」
「そっか〜、毎年来てたのにね」
「終わったら取り壊されちゃうのかな」
「そうだろうねー、残念だけど…」
ベンチに横並びに座って靴を履き替える、女子高生の二人組の会話。突然突きつけられた「最期」の冬を、私は受け入れるしかなかった。
春の足音が近づいてくる。最終日と書かれた看板に引き寄せられるようにして、今までよりもたくさんの人が私の元へやって来ていた。混雑緩和のためか券売機は撤去され、スタッフの仕事も、紙切れのもぎりからスマートフォンの画面読み取りになっている。それでも、入場口には押し寄せた人々が列を作っていた。
何時間も前から開園を待っていたであろう男女のグループが、大はしゃぎでゲートをくぐった。少し背が伸びた少年は、両親の手を借りることなく、自分の足でゆっくりと進んでいく。老若男女で賑わう会場。でも、あの子の姿は見つからない。毎日必死になって探していたけれど、風をきって私の上を舞っていた彼女は、どこにも見当たらなかった。
何時間も前から開園を待っていたであろう男女のグループが、大はしゃぎでゲートをくぐった。少し背が伸びた少年は、両親の手を借りることなく、自分の足でゆっくりと進んでいく。老若男女で賑わう会場。でも、あの子の姿は見つからない。毎日必死になって探していたけれど、風をきって私の上を舞っていた彼女は、どこにも見当たらなかった。
あっという間に陽は沈み、最期の夜が訪れる。メロディを口ずさめるくらい何度も聞いた音楽もついに途切れて、辺りの照明がふっと落とされた。結局、彼女には会えなかった。唯一の心残りはどんどん膨らんで、私を埋め尽くしていく。
あの子の滑る姿、すごく好きだったんだ。忘れられてもいいって言っていたのに、忘れないでって思ってしまうなんて。私の体は動かないし、声だって出せない。ここを飛び出して、探しに行くこともままならない。
ああ、どうしよう。どうすることもできないのに。
最期に一度だけ、少しだけでもいいから、あの子に会いたいって思ってしまうなんて。
あの子の滑る姿、すごく好きだったんだ。忘れられてもいいって言っていたのに、忘れないでって思ってしまうなんて。私の体は動かないし、声だって出せない。ここを飛び出して、探しに行くこともままならない。
ああ、どうしよう。どうすることもできないのに。
最期に一度だけ、少しだけでもいいから、あの子に会いたいって思ってしまうなんて。
その時。
――カンッ!
純白のシューズを高らかに鳴らして、リンクの中央へ滑走する一人の女性。白と水色のドレスにあしらわれた装飾がスポットライトに照らされて、宝石のようにきらきらと光り輝く。華やかな衣装に身を包んだ「あの子」は、錆びついたスピーカーから流れるソナタとともに、滑らかに氷上を舞う。
「あぁ…」
その姿、その滑り方。ずっと大切にしまっていた記憶が、宝箱を開けるようにして、次々と私の頭を駆け巡る。
「やっと、会えたね」
イベント最終日の閉園間際。この日を記念して、地元のスケーターによるエキシビションが開催されるという話は耳にしていた。でも、まさか彼女がそうだったなんて。真っ暗で分からなかったが、気づけばたくさんの人々が私の周りを取り囲んでいた。ベンチは満席、リンクの縁に沿って何重にも隙間なく立ち見の人々が並び、彼女の演技に息を呑んでいる。繊細なピアノで紡がれるソナタは、次第にストリングスが重なり、情熱的な旋律へ展開していく。
かつて、冬が来るたびに私の上を滑っていた「あの子」は、数年の時を経て、アマチュアスケーターとして再出発を切った。その過程に何があったのか、どれほどの苦悩があったのか、私に知る由はない。ただ一つ確かなことは、悲しみと苦しみを抱えていた彼女の軌跡が、明日への希望と喜びに満ちた、力強いものへと変化を遂げたということだった。リンクを滑走する彼女は軽く息を整えると、助走をつけて高く飛び上がり、三回転半の螺旋を描く。
「…綺麗」
思わず溢れた言葉。この景色を、ずっと見ていたい。終わりが来てほしくない。時間が止まってしまえばいいのに。スピーカーが壊れて、音楽がずっと鳴り続ければいいのに。そんな自分勝手な願いを嘲笑うように、音楽は終盤に差し掛かる。彼女はそのまま鮮やかなステップでステージの中央に移動すると、体を捻り回転し始めた。高さと速さを自在に変える、スピンコンビネーション。その軸がブレることはない。しなやかで繊細かつ芯の通った、彼女の意志がそのまま現れたようなスピン。壮大なストリングスとともに、フィナーレを迎える。
どこまでも高く続く空。その先に煌めく星々を掴むように、彼女は伸ばした手をゆっくりと握りしめた。
「あぁ…」
その姿、その滑り方。ずっと大切にしまっていた記憶が、宝箱を開けるようにして、次々と私の頭を駆け巡る。
「やっと、会えたね」
イベント最終日の閉園間際。この日を記念して、地元のスケーターによるエキシビションが開催されるという話は耳にしていた。でも、まさか彼女がそうだったなんて。真っ暗で分からなかったが、気づけばたくさんの人々が私の周りを取り囲んでいた。ベンチは満席、リンクの縁に沿って何重にも隙間なく立ち見の人々が並び、彼女の演技に息を呑んでいる。繊細なピアノで紡がれるソナタは、次第にストリングスが重なり、情熱的な旋律へ展開していく。
かつて、冬が来るたびに私の上を滑っていた「あの子」は、数年の時を経て、アマチュアスケーターとして再出発を切った。その過程に何があったのか、どれほどの苦悩があったのか、私に知る由はない。ただ一つ確かなことは、悲しみと苦しみを抱えていた彼女の軌跡が、明日への希望と喜びに満ちた、力強いものへと変化を遂げたということだった。リンクを滑走する彼女は軽く息を整えると、助走をつけて高く飛び上がり、三回転半の螺旋を描く。
「…綺麗」
思わず溢れた言葉。この景色を、ずっと見ていたい。終わりが来てほしくない。時間が止まってしまえばいいのに。スピーカーが壊れて、音楽がずっと鳴り続ければいいのに。そんな自分勝手な願いを嘲笑うように、音楽は終盤に差し掛かる。彼女はそのまま鮮やかなステップでステージの中央に移動すると、体を捻り回転し始めた。高さと速さを自在に変える、スピンコンビネーション。その軸がブレることはない。しなやかで繊細かつ芯の通った、彼女の意志がそのまま現れたようなスピン。壮大なストリングスとともに、フィナーレを迎える。
どこまでも高く続く空。その先に煌めく星々を掴むように、彼女は伸ばした手をゆっくりと握りしめた。
一瞬の静寂を切り裂くようにして、割れんばかりの歓声と拍手が辺りを包み込む。
「すごい…すごいよ!やっぱりみんな、あなたの滑る姿が大好きなんだ!」
私は彼女を誇らしげに思う。しかし、ノーミスで滑り切った達成感と安堵からか、彼女は目を潤ませて、その場にしゃがみ込んでしまった。
「上手だったよ!大丈夫、自信を持って。胸を張って、これからも羽ばたいていって」
両腕を広げて抱きしめてあげたいけれど、私にはできない。その代わりに、届くことのない心からの賞賛とエールを送り続ける。
「ここはあなたには狭すぎるから…。寂しいけれど、忘れてもいいよ。私が代わりに覚えておくから」
その時、彼女は両膝を冷たい地面について、そっと私に手を触れる。
「…ありがとう」
小さく震える声で呟かれた五文字。鳴り止まない歓声と拍手の中で、その言葉は私の耳に確かに届けられた。
そして私は初めて、辺りを包む観客の声が、拍手の音が、彼女だけではなく自身にも向けられたものであることに気づく。
「ありがとー!」
「また会おうね!」
「大好きだよー!」
ああ、そうか。
私だけじゃなかったんだ。
忘れたくないのも、会えなくなってしまうのが辛いのも、別れが惜しいのも…みんな同じだったんだ。
届かないはずの言葉が、心が通じ合ったような気がして、胸の奥に抑えていた感情が溢れ出しそうになる。
どうしよう、泣かせないでよ。氷が溶けちゃうから。
涙が溢れないように、上を向く。果てしなく広がる夜空を伝う流星の煌めきを、私は目に焼き付けた。
「すごい…すごいよ!やっぱりみんな、あなたの滑る姿が大好きなんだ!」
私は彼女を誇らしげに思う。しかし、ノーミスで滑り切った達成感と安堵からか、彼女は目を潤ませて、その場にしゃがみ込んでしまった。
「上手だったよ!大丈夫、自信を持って。胸を張って、これからも羽ばたいていって」
両腕を広げて抱きしめてあげたいけれど、私にはできない。その代わりに、届くことのない心からの賞賛とエールを送り続ける。
「ここはあなたには狭すぎるから…。寂しいけれど、忘れてもいいよ。私が代わりに覚えておくから」
その時、彼女は両膝を冷たい地面について、そっと私に手を触れる。
「…ありがとう」
小さく震える声で呟かれた五文字。鳴り止まない歓声と拍手の中で、その言葉は私の耳に確かに届けられた。
そして私は初めて、辺りを包む観客の声が、拍手の音が、彼女だけではなく自身にも向けられたものであることに気づく。
「ありがとー!」
「また会おうね!」
「大好きだよー!」
ああ、そうか。
私だけじゃなかったんだ。
忘れたくないのも、会えなくなってしまうのが辛いのも、別れが惜しいのも…みんな同じだったんだ。
届かないはずの言葉が、心が通じ合ったような気がして、胸の奥に抑えていた感情が溢れ出しそうになる。
どうしよう、泣かせないでよ。氷が溶けちゃうから。
涙が溢れないように、上を向く。果てしなく広がる夜空を伝う流星の煌めきを、私は目に焼き付けた。
次第に人々の声は少なくなり、辺りは再び静寂に包まれる。否応なく最期と向き合うことになった私の心に、忘れかけていた寂しさが再び込み上げてきた。別れは寂しい。今までは一年経ったらまた会えるって思っていたからなんとも思わなかったけれど、これからもう会えなくなるなんて。もう、久しぶりって言えないなんて。
…でも、大丈夫。私がいなくなっても、みんな前に進んでいける。いつかまた私のことを思い出してなんて、我儘は言わない。粉々に砕かれてしまっても、氷が全部溶けてしまっても、何も形に残らなかったとしても。私がみんなの思い出を、みんなと描いてきた軌跡を、ちゃんと全部覚えているから。
だから、どうかこれからも、一歩踏み出すことを忘れないで。転んでも大丈夫。また立ち上がればいい。繋いだ手を離してしまっても大丈夫。また手を取り合って、強く握り直せばいい。迷ってもいい。ふらついていてもいい。あなたが私に描いた軌跡は、いつか空の星に届くくらいに、あなた自身を高く飛び上がらせるバネになるから。
…でも、大丈夫。私がいなくなっても、みんな前に進んでいける。いつかまた私のことを思い出してなんて、我儘は言わない。粉々に砕かれてしまっても、氷が全部溶けてしまっても、何も形に残らなかったとしても。私がみんなの思い出を、みんなと描いてきた軌跡を、ちゃんと全部覚えているから。
だから、どうかこれからも、一歩踏み出すことを忘れないで。転んでも大丈夫。また立ち上がればいい。繋いだ手を離してしまっても大丈夫。また手を取り合って、強く握り直せばいい。迷ってもいい。ふらついていてもいい。あなたが私に描いた軌跡は、いつか空の星に届くくらいに、あなた自身を高く飛び上がらせるバネになるから。
「またね」
冷たい空気を胸いっぱいに吸い込んで、誰にも聞こえない声で呟いた。遠くから、重機の駆動音が聞こえてくる。
今日のことを、これまでのことを全部、ずっと忘れずに覚えていられますように。
月の光に照らされて、銀盤に刻まれたかけがえのない軌跡が、煌々と輝いていた。
月の光に照らされて、銀盤に刻まれたかけがえのない軌跡が、煌々と輝いていた。
―了―