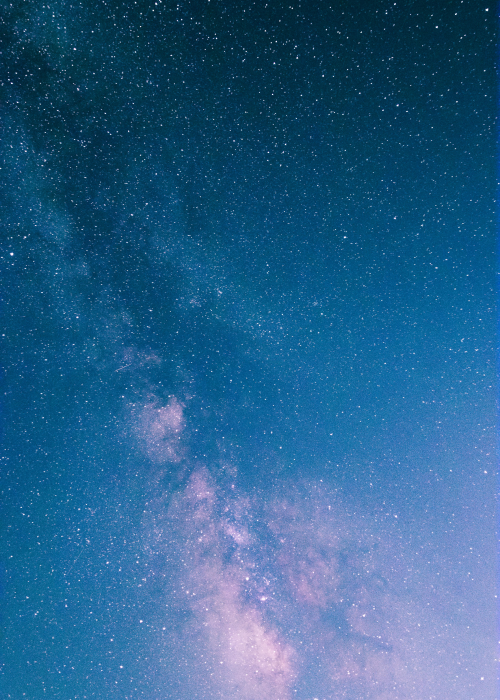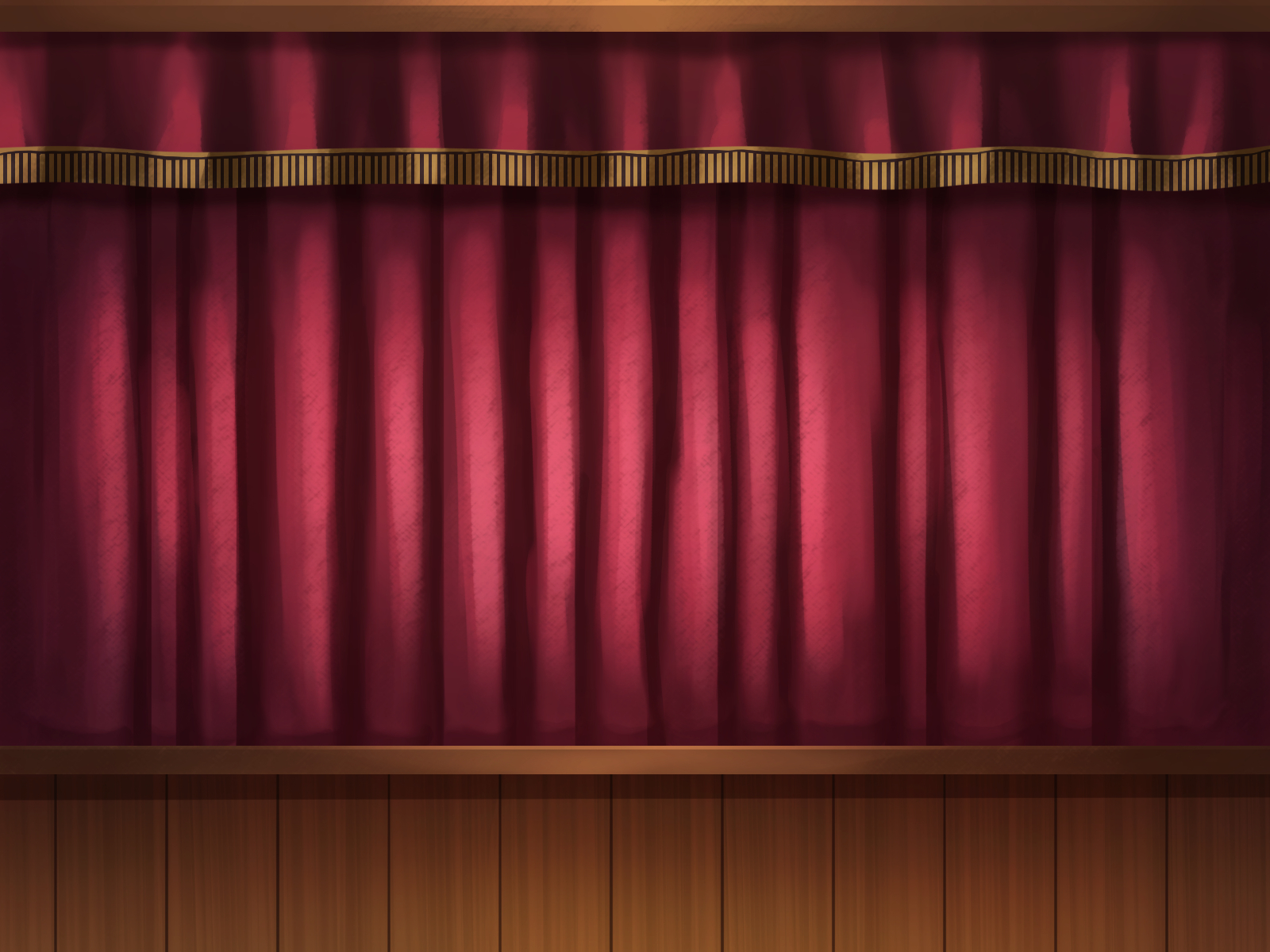戦前の赤紙
ー/ー湿気を含んだ空気が、オフィスの窓を伝って滴を作っていた。佐藤健一は目を凝らしてモニターを見つめながら、最後のコードをタイプし終えた。午後五時四十五分。若手エンジニアの育成計画の資料作りに予定より時間がかかってしまった。
「佐藤さん、この部分の実装について質問していいですか?」
新入社員が、おずおずと声をかけてきた。システムエンジニアとして働き始めて七年目の健一は、最近では若手の教育係も任されるようになっていた。
「ああ、このループ処理のところね。ここはね...」
説明を終えると、時計は六時を指していた。健一は画面に映る自分の顔を見た。疲れた目が微かに赤くなっている。早めに帰ろうと思っていたのに、また定時を過ぎてしまった。
「じゃ、お先に失礼します」
デスクの上に置かれた写真立てに目をやる。結婚式の写真だ。白いドレス姿の由里が、はにかんだ笑顔を見せている。写真の横には手帳があった。来週の土曜日に、新居の家具を見に行く約束が書き込まれている。
エレベーターに乗り込みながら、スマートフォンを取り出した。由里からのメッセージが三件届いていた。
『今日は唐揚げ作るね。新しいレシピ見つけたの!』
『あ、ニンニクの効いた甘辛味だよ。健一が好きな感じ』
『仕事、頑張ってる?』
返信を打ちながら、健一は思わず微笑んだ。
「そうだ」健一は突然思いついたように文を送った。
『子供の名前、航って名前はどう?大空を飛ぶイメージで」
由里は妊娠しており健一は早く子供の顔を見たいと思っていた。
『航...素敵な名前ね。私、大好き!』。
健一は会社から帰宅しマンションのエントランスに着くと、同じ階に住む夫妻とすれ違った。二歳の双子を連れた若い夫婦だ。
「あら、佐藤さん。今日は早めなのね」
「ええ、まあ...」
双子が元気に手を振る。健一も笑顔で応えながら、自分たちの未来を想像していた。
そしてポストに手を伸ばすと、普段の郵便物の感触と違う何かがある。チラシや請求書の束に混ざって、一通の封筒が目に留まった。夕陽に照らされ、不自然なまでに赤く輝いている。
一見すると自衛隊を思わせるエンブレムが印刷されている。しかし、よく見ると現行の自衛隊のものとは微妙に異なっていた。より近未来的な、どこか無機質な印象のデザインだ。
教科書の歴史の章でしか見たことのないものが、いま自分の手の中にある。震える指で封を切る。高級な和紙のような手触りの紙が、中から姿を現した。
『召集令状』
黒々とした活字体で印刷された文字が、夕暮れの薄明かりの中で異様な存在感を放っている。
佐藤健一、1992年8月15日生まれ。現住所、職業、家族構成——すべての個人情報が克明に記されている。
「これは...冗談か?」
誰かの悪質ないたずらを疑いたくなる。しかし、封筒の質感も、印刷の精密さも、紛れもなく公文書としか思えない重みがある。それに、このエンブレムの違和感。現代の技術では作れないような、微細な加工が施されているようにも見える。
汗ばんだ手でスマートフォンを取り出し、検索を始める。「赤紙」「召集令状」「現代日本」しかし、関連する記事は戦前の歴史的な解説ばかりで、現代における類似の事例は一件もヒットしない。
マンションの自室の前まで来ると、中からは料理の音と香りが漂ってきた。いつもなら心が躍る瞬間なのに、今は胃の底が凍るような感覚に襲われる。
玄関のドアノブに手をかけた瞬間、ふと思い出した。今朝、由里が話していた週末の計画。新しいソファを見に行って、その後は映画を観る約束をしたばかりだった。たった数時間前の会話が、まるで遠い過去のように感じられる。
「た、ただいま...」
自分の声が震えていることに気づく。ドアを開けると、台所から由里が顔を出した。白いエプロンに、お気に入りの紺のワンピース姿。結婚してからよく見る光景なのに、今日は特別に痛々しく映る。
「お帰りなさい!ねえ、唐揚げ、もう少しで」
由里の声が途切れた。健一の表情に、何か異変を感じ取ったのだろう。彼女の笑顔が徐々に消えていく。
「どうしたの...?顔色、悪いわよ」
台所から出てきた由里に、黙って赤紙を差し出す。彼女はエプロンを外しながら、おそるおそる受け取った。文書に目を通す彼女の顔が、みるみる血の気を失っていく。
「うそ...でしょう?こんなの...現代の日本じゃ...ありえない...」
由里の声が震えている。書類を持つ手も小刻みに揺れている。健一は何も答えられない。ただ、崩れ落ちそうになる妻を抱きしめることしかできなかった。
「これから...私たち...どうなるの?」
その問いに、健一は答えることができなかった。まだ二人の生活が始まったばかりなのに。これから家族を作っていこうとしていた矢先に。子供部屋にしようと話していた部屋は、このまま物置きのままなのだろうか。なぜ、こんな形で未来を奪われなければならないのか。
台所からは、唐揚げを揚げかけたままの油の香りが漂ってくる。火を止めるのも忘れて、二人は長い間、ただ抱き合っていた。
その夜、健一は眠れなかった。エアコンの微かな音と、時折聞こえる由里の寝返りの音だけが、暗闇の中に響く。天井を見つめながら、いくつもの考えが頭の中を駆け巡る。会社にはどう説明すればいいのか。両親にはなんと伝えればいいのか。そもそも、これは本当に現実なのか。
隣では由里が、不安げな寝息を立てている。普段は安らかに感じる寝顔が、今は痛々しく見えた。結婚指輪が、月明かりに微かに光っている。
窓の外では、いつもと変わらない夜景が広がっていた。マンションの明かりが、星のように点々と灯っている。向かいのビルでは、残業をしているサラリーマンの影が見える。その日常の風景が、今までとは全く違って見える。まるで、もう二度と戻れない異世界の光景のように。
赤紙を受け取った翌朝、健一は会社に向かった。いつもの通勤電車が、どこか非現実的に感じられる。スマートフォンを見ながら無表情に座る会社員たち。彼らは知らない。今、自分の手元にある非常識な召集令状のことを。
その夜、由里と二人でインターネットを徹底的に調べた。「現代」「赤紙」「召集令状」—検索キーワードを変えながら、可能性のある情報を探す。しかし、どれも歴史的な解説か、フィクション作品の話だった。
「これ、偽物なんじゃない?」
由里が震える声で言う。彼女は広告代理店でコピーライターとして働いている。文字や印刷物を見る目には自信があるはずだ。
「でも、この紙質も印刷の質も、一般的な技術では作れないと思う。それに、このエンブレム。見る角度によって模様が変化するの。ホログラムでもこんな精密なものは...」
翌日、都内の法律事務所を三つ回った。どの弁護士も首を傾げるばかり。一人は防衛省の関係者に問い合わせてくれると約束したが、結局、返事はなかった。
時間だけが過ぎていく。由里は会社を休んで付き添ってくれた。実家にも相談しようか迷ったが、却って心配をかけるだけだと思い、止めた。
そうして一週間が経過した。指定された日時、午前九時の十分前——。
突然のインターホンに、二人で顔を見合わせた。
「佐藤健一様、お迎えに参りました」
モニター画面に映っていたのは、黒いスーツに身を包んだ二人の男だった。一見すると普通のビジネススーツに見えたが、生地の質感が異様に滑らかで、光の加減によって微妙に色が変化する。まるで液体金属のようなつやを持っていた。
「行かないで...」
由里が健一の腕にしがみつく。その手が震えているのがわかった。
ドアを開けると、男たちの持つ機器が目に入った。スマートフォンのような形状だが、全面が透明なガラスのようで、その中を青い光が走っている。画面には立体的な文字が浮かび上がり、何かのデータが流れている。明らかに現代の技術レベルを超えていた。
「お時間となりました。ご同行願います」
低く落ち着いた声音。しかし、その中に含まれる威圧感に、背筋が凍る。
「待ってください。せめて、妻に別れを...」
「申し訳ありません。これ以上の接触は許可されておりません」
男の一人が透明な機器を掲げた瞬間、二人の間に青白い光の膜のようなものが形成された。由里の手が、まるで磁石の反発のように健一から離される。
「健一さん!」
由里の悲鳴が、不思議なほど遠くから聞こえる。視界が歪み始め、体が急に重く感じられる。足元がふらつき、意識が遠のいていく。最後に見た由里の表情が、網膜に焼き付いて離れない。
目が覚めたのは、真っ白な天井の下だった。体は柔らかなベッドのような台の上にある。指先を動かすと、布地は通常の繊維とは明らかに異なる感触だった。
「気分はどうですか?」
声をかけてきたのは、白衣を着た若い女性だった。その姿は医師のようでいて、どこか違和感がある。白衣の生地も、先ほどの黒服の男たちと同じような不思議な質感を持っていた。
「ここは...?」
喉が渇いているのか、声が掠れる。
「第七転送施設です。まもなく説明会が始まります」
立ち上がってみると、そこは巨大なドーム状の空間だった。直径は五十メートルはあるだろうか。壁面には見たこともない装置が並び、、半透明のスクリーンに浮かび上がっている。天井からは青白い光が降り注ぎ、未来的な雰囲気を醸し出していた。
部屋の中には、自分と同じように召集されたらしき人々が三十人ほど集まっていた。年齢層は様々。スーツ姿のビジネスマンもいれば、作業着姿の人も。女性は五人ほど。皆一様に困惑した表情を浮かべている。
「君も召集されたのかい?」
声をかけてきたのは、四十代半ばくらいの男性だった。短く刈り込んだ髪に、知的な印象の眼鏡。
「ええ...一週間前に赤紙が」
「私もだ。大学で量子物理を教えているんだが...まさかこんなことになるとは」
話を聞いてみると、他にも様々な分野の専門家が集められているようだった。AIの研究者、宇宙工学の技術者、それに医療関係者。しかし、なぜ自分のようなシステムエンジニアまでが選ばれたのか。そして、この未来的な施設の目的は何なのか。
その時、ドーム中央の空中に、巨大なホログラムが浮かび上がった。三次元の映像が、まるで実体があるかのように空間に浮かぶ。技術者である健一の目には、それが既知の技術の範疇を超えていることが明らかだった。
映像の中で、一人の人物が姿を現した。そして、彼の最初の言葉が、部屋中の空気を凍りつかせた。
「皆様、お待ちしておりました」
巨大なホログラムに映し出された人物は、軍服のような制服を着ていたが、そのデザインは現代の自衛隊のものとは明らかに異なっていた。より洗練された未来的なデザインで、肩章には見たことのない階級章が輝いている。
「私は統合防衛軍第三師団長の山本です。皆様には大変な困惑を与えていることと思います」
その声は穏やかでありながら、強い意志を感じさせるものだった。
「我々は2045年の日本から、皆様を召集しています。この施設は、2025年の日本国政府と我々2045年の日本国政府が共同で運営する特殊施設です。現在の国会でも極秘裏に承認された『時空間安全保障協定』に基づいて設置されています」
会場がざわめいた。健一の隣にいた量子物理学の教授が、眼鏡の奥で目を細める。
「ここで進められているのは『時間徴用計画』と呼ばれる作戦です。2045年の日本は、かつてない規模の戦争に直面しています。その戦争に対処するため、我々は現在の日本政府と協議を重ね、この異例の対応を決定しました」
ホログラムが切り替わり、アジア太平洋地域の地図が浮かび上がった。そこには複雑な戦線が描かれ、紛争地域が赤く示されている。
「2042年に始まるこの戦争は、既存の概念を超えた新しい形の戦争です。AIによる戦術予測、量子暗号通信、ナノテクノロジーを駆使した兵器。しかし、皮肉なことに、この高度に発達した戦争において、最も重要なのは依然として『人材』なのです」
画面が切り替わり、時間軸に沿った図表が現れた。山本師団長は続ける。
「なぜ過去から人材を召集するのか。それは、私たちの時代では得られない特殊な適応力と問題解決能力を持つ方々が必要だからです。2025年は、時代の変化の最中にあり、皆様はかつてない速度で変化する技術環境の中で働いてきました。新技術が次々と登場する中で、常に学び、適応し続けてきた世代です。その経験は、私たちの時代の高度な技術を習得する上で、極めて重要な意味を持ちます。
さらに、皆様は限られたリソースと技術的制約の中で、創意工夫を重ねてきました。システムの根本的な仕組みを理解し、時には手作業での対応も厭わない。そうした柔軟な問題解決能力は、高度に自動化された2045年では失われつつある貴重な資質なのです。システムが完全に機能停止した際、基礎的な部分から問題を解決できる人材が、私たちには必要不可欠なのです」
健一は思わず、となりにいる量子物理学の教授を見た。教授は深い思索に耽っているようだった。
「この計画は、両政府の厳重な管理下で実施されています。現代の自衛隊も、極秘裏にこの施設の警備を担当しています。皆様の家族や周囲の人々の安全は、しっかりと保証されています」
そう言いながら、山本師団長の表情が一瞬曇った。
「しかし、申し訳ありません。この召集には拒否の選択肢がありません。皆様には、まもなく実施される転送プログラムによって、2045年の日本へと移動していただきます」
会場が騒然となった。怒号が飛び交い、中には床に崩れ落ちる者もいる。
「なぜ我々が!」
「家族はどうなる!」
「これは人権侵害だ!」
山本師団長は、その混乱を静かに見つめていた。そして、おもむろに新しい映像を投影した。
「これが、未来です。この戦争は、既に多くの国々を破壊しています。そして日本も、その渦中にあります」
映像は次々と切り替わる。避難する市民たち。破壊された建物。そして、見たこともない兵器で武装した軍隊。
「皆様の召集は、決して軽い決断ではありません。両政府とも、これが最後の手段であることを認識しています。しかし——」
その時、会場の後方で誰かが立ち上がった。五十代くらいの男性だ。
「私には分かります」その男性は静かに、しかし確固とした口調で話し始めた。「私は広島で生まれ育ちました。祖父から聞いた話があります。戦争は、突然日常を破壊します。しかし、その後に来るものはもっと恐ろしい」
会場が静まり返る。
「私たちには、それを止める機会があるということですね」
山本師団長は深く頭を下げた。「はい。その通りです」
休憩時間が設けられ、召集された人々は小グループに分かれて話し合い始めた。健一は量子物理学の教授と、もう一人のソフトウェアエンジニアという女性と話をすることになった。
「私には高校生の息子がいるんです」女性エンジニアが静かな声で話す。「どうして突然、こんな...」
「私も、妻と生まれてくる子供のことを考えると...」健一は言葉を詰まらせた。
「時間軸での人材徴用か...」教授が眼鏡を押し上げながら呟く。「時空間移動が理論的には可能性は指摘されていたが、まさか実現されているとは。しかし、これほどの規模での時空間移動には、莫大なエネルギーが必要なはずだ。両政府が共同でこれを承認し、実行するということは、相当な切迫した状況なのかもしれない」
彼らの会話は、同じような境遇の人々の輪に広がっていった。医師、研究者、技術者——それぞれが自分の人生を突然奪われた衝撃と、残してきた家族への思いを語り合う。
説明会の後、徴用者たちは仮設の宿泊施設に案内された。未来的な装飾が施された建物の中で、健一は一人、窓際に立っていた。外の景色は巧妙に遮断されており、ここが日本のどこなのかも分からない。フロアを横切るたびに、壁に埋め込まれたセンサーが青く光る。
部屋は広くはないが、これまで見たことのない素材で作られた家具が配置されていた。ベッドは一見普通に見えるが、触れると体温に反応するように形を微調整する。デスクの天板は半透明で、中を光が走っているように見える。
健一は、デスクに向かった。与えられた紙とペンで、由里への手紙を書き始める。しかし、ペンは何度も止まり何度も紙を破り捨てた。結局、短い言葉しか残せなかった。
朝日が昇り始めた頃、施設内のスピーカーから声が響いた。
「転送準備を開始します。徴用者の皆様は、指定の集合場所へお集まりください」
アナウンスの声は、不思議なほど温かみがあった。まるで、彼らの決意を待っていたかのように。
集合場所に向かう廊下で、手紙を、施設のスタッフに託す。黒服の男は「必ず配達される」と約束した。それが唯一の救いだった。
それから健一は昨夜の仲間たちと再会した。先ほどまでの脱出劇が嘘のように、皆整然と列を作っている。しかし、その表情は昨夜とは違っていた。
諦めでも、単なる受容でもない。そこにあったのは、未来を変えるという強い決意だった。それは、与えられた運命を受け入れつつ、なおその中で何ができるかを模索する、人間としての意志の表れだった。
転送室は、巨大なドーム状の空間だった。天井までの高さは優に30メートルはあり、その壁面には無数の装置が並んでいる。青く輝くエネルギー導管が網目状に壁を覆い、まるで生命体の血管のようだった。中央には直径20メートルほどの円形プラットフォームがあり、その周囲を青白い光の帯が螺旋状に取り巻いていた。
健一は与えられた白い転送用スーツに袖を通しながら、そのあまりの非現実性に戸惑いを覚えていた。スーツの生地は、触れると微かに温かみがあり、まるで生きているかのように体の動きに合わせて形状を変える。
「では、転送を開始します」
白衣の女性技術者が、宙に浮かぶように見える透明なコンソールに手を置いた。画面には複雑な数式とグラフが次々と展開される。プラットフォームの周囲に立つ12本の支柱が、低い振動音を発し始めた。その先端からは、紫がかった光が放射されている。
「皆様、プラットフォームの中央にお集まりください。所持品は全て専用のコンテナに収められ、別ルートで転送されます」
健一は他の徴用者たちと共に指定の場所へ移動した。足元の金属プレートが微かに脈動しているのが感じられる。表面には幾何学的な文様が刻まれており、それが徐々に淡い光を放ち始めた。
「転送には約30秒を要します。強いめまいを感じる可能性がありますが、これは正常な反応です。意識の喪失を経験する方もいらっしゃいますが、心配はいりません」
カウントダウンが始まると、支柱から放たれる光が徐々に強まっていった。まるで紫がかった霧が空間を満たしていくようだ。健一の視界が歪み始める。世界全体が液体のように揺らぎ、色彩が互いに溶け合っていく。
「10、9、8......」
機械的な声が響く中、健一は懐から取り出したエコー写真を強く握りしめた。由里のことを、そしてまだ見ぬ息子のことを思い浮かべる。
「3、2、1......転送開始」
一瞬の閃光。そして、世界が消失した。
意識が戻ったとき、健一は別の施設の床に横たわっていた。天井の低い、より実務的な印象の空間。医療スタッフらしき人々が、バイタルをチェックしている。
「意識、正常です。バイタルも安定しています」
起き上がると、大きな窓の外には見覚えのある東京の街並みが広がっていた。しかし、それは20年の歳月を経た東京だった。
高層ビル群の形状は基本的に変わっていないものの、その表面は全て光を反射する特殊な素材で覆われていた。建物の外壁には巨大なホログラムが浮かび、天気予報や警報システムの情報が立体的に表示されている。道路には自動運転の車両が整然と流れ、その多くは地上数センチを浮遊していた。空にはドローンらしき物体が規則正しく飛び交い、時折、半透明の円盤のような物体も見える。
街路樹は健在だが、その葉は明らかに人工的な輝きを放っている。幹には微細なセンサーが埋め込まれ、常に環境データを収集しているという。
「環境浄化ナノマシンを組み込んだ改良種です」
案内役の若い士官が説明した。切れ長の目をした30代前半の男性で、名札には「渡辺」とある。
「大気汚染への対策として、街路樹の80%をこのタイプに置き換えています。CO2の吸収効率は従来種の5倍です」
通りを行き交う人々の姿は、しかし、20年前と大きくは変わっていなかった。服装こそ未来的だが、足早に歩くサラリーマン、買い物帰りの主婦、下校途中の学生たち——。その何気ない日常の風景の中に、現代の面影を強く感じた。
人々の多くは、薄型のゴーグルのようなデバイスを身につけている。拡張現実を通して、様々な情報を直接網膜に投影しているのだという。中には、完全な義手や義足を持つ人も珍しくない。その動きは極めて自然で、一目では判別できないほどだ。
「あれが防衛省です」
渡辺士官が指差した先には、巨大な複合施設が建っていた。従来の防衛省とは全く異なる、
「これより、3週間の基礎訓練が始まります」
訓練施設は、地下100メートルの深さに設けられていた。巨大な訓練フロアには、最新の装備が整然と並んでいる。バーチャル戦闘シミュレーターは、完全な没入感を実現する脳内接続型で、実戦さながらの訓練が可能だった。
健一は他の技術者たちと共に、特殊部隊のサイバー戦対策チームに配属された。チームメンバーは10名。全員が2025年からの徴用者だった。
「これが最新の戦術端末です」
配られた装置は、一見するとシンプルな腕時計のように見える。しかし、その機能は現代のスーパーコンピュータを遥かに凌駕していた。量子暗号通信、生体センサー、ホログラフィック投影、脳内接続インターフェース。マニュアルに目を通すだけで、頭が眩むような最先端技術の数々。健一は自分のシステムエンジニアとしての知識を総動員して、この新しい技術の習得に励んだ。
「面白いですよね、この技術」
同じチームのデータサイエンティスト、村上が話しかけてきた。彼女は40代前半の女性で、現代では大手IT企業の研究開発部門で働いていたという。
訓練は過酷を極めた。脳内接続デバイスの使用には強い精神的負荷が伴い、最初の一週間は頭痛に悩まされ続けた。しかし、チームメンバーたちと励まし合いながら、徐々に新しい技術に適応していく。
特に、村上とは親しい関係になっていった。彼女には高校生の息子がいるという。その息子は今、40代になっているはずだ。
ある日、訓練の休憩時間に健一が尋ねた。
「会いたいですか?息子さんに」
村上は遠くを見つめながら答えた。
「ええ」
その言葉に、健一は自分の状況を重ね合わせていた。この2045年のどこかに、自分の子供がいるかもしれない。会いたい気持ちが常に彼の心の中にあった、
2025年、東京。
由里は届けられた手紙を何度も読み返していた。そこには、「由里、そしてこれから生まれてくる自分たちの子供の未来を守る」という言葉だけが記されている。
そして航は、10月4日に生まれた。
「お母さんは強いね」
見舞いに来た友人はそう言った。「一人で育てるって決めたの?」
由里はただ微笑んで頷いた。夫の突然の失踪。家族からは再婚を勧められることもある。しかし、由里は息子を育てることを選んだ。
数年後。息子は父親そっくりに育った。プログラミングの才能、そして何より、強い正義感も。
そして2042年、アジアで最初の戦火が上がった。
高校を卒業したばかりの航は、すでに父親を超える優秀なプログラマーになっていた。
そんなある日、航の元に赤紙が届いた時、由里は何も言えなかった。ただ、強く息子を抱きしめた。
2045年8月15日の朝。
テレビは戦況を伝えている。新型AI兵器の制御システムの異常を直し多くの命を救った一人の戦死した若い兵士を大々的に報道している。そこには航の名前があった。
その日の夕暮れ、由里は六畳間に座っていた。航の成長を見守ってきた部屋。壁には航の写真が何枚も飾られている。
そして人々は気付いていない。この戦争の裏で、時間を超えた戦いが既に始まっていることを。
「佐藤さん、この部分の実装について質問していいですか?」
新入社員が、おずおずと声をかけてきた。システムエンジニアとして働き始めて七年目の健一は、最近では若手の教育係も任されるようになっていた。
「ああ、このループ処理のところね。ここはね...」
説明を終えると、時計は六時を指していた。健一は画面に映る自分の顔を見た。疲れた目が微かに赤くなっている。早めに帰ろうと思っていたのに、また定時を過ぎてしまった。
「じゃ、お先に失礼します」
デスクの上に置かれた写真立てに目をやる。結婚式の写真だ。白いドレス姿の由里が、はにかんだ笑顔を見せている。写真の横には手帳があった。来週の土曜日に、新居の家具を見に行く約束が書き込まれている。
エレベーターに乗り込みながら、スマートフォンを取り出した。由里からのメッセージが三件届いていた。
『今日は唐揚げ作るね。新しいレシピ見つけたの!』
『あ、ニンニクの効いた甘辛味だよ。健一が好きな感じ』
『仕事、頑張ってる?』
返信を打ちながら、健一は思わず微笑んだ。
「そうだ」健一は突然思いついたように文を送った。
『子供の名前、航って名前はどう?大空を飛ぶイメージで」
由里は妊娠しており健一は早く子供の顔を見たいと思っていた。
『航...素敵な名前ね。私、大好き!』。
健一は会社から帰宅しマンションのエントランスに着くと、同じ階に住む夫妻とすれ違った。二歳の双子を連れた若い夫婦だ。
「あら、佐藤さん。今日は早めなのね」
「ええ、まあ...」
双子が元気に手を振る。健一も笑顔で応えながら、自分たちの未来を想像していた。
そしてポストに手を伸ばすと、普段の郵便物の感触と違う何かがある。チラシや請求書の束に混ざって、一通の封筒が目に留まった。夕陽に照らされ、不自然なまでに赤く輝いている。
一見すると自衛隊を思わせるエンブレムが印刷されている。しかし、よく見ると現行の自衛隊のものとは微妙に異なっていた。より近未来的な、どこか無機質な印象のデザインだ。
教科書の歴史の章でしか見たことのないものが、いま自分の手の中にある。震える指で封を切る。高級な和紙のような手触りの紙が、中から姿を現した。
『召集令状』
黒々とした活字体で印刷された文字が、夕暮れの薄明かりの中で異様な存在感を放っている。
佐藤健一、1992年8月15日生まれ。現住所、職業、家族構成——すべての個人情報が克明に記されている。
「これは...冗談か?」
誰かの悪質ないたずらを疑いたくなる。しかし、封筒の質感も、印刷の精密さも、紛れもなく公文書としか思えない重みがある。それに、このエンブレムの違和感。現代の技術では作れないような、微細な加工が施されているようにも見える。
汗ばんだ手でスマートフォンを取り出し、検索を始める。「赤紙」「召集令状」「現代日本」しかし、関連する記事は戦前の歴史的な解説ばかりで、現代における類似の事例は一件もヒットしない。
マンションの自室の前まで来ると、中からは料理の音と香りが漂ってきた。いつもなら心が躍る瞬間なのに、今は胃の底が凍るような感覚に襲われる。
玄関のドアノブに手をかけた瞬間、ふと思い出した。今朝、由里が話していた週末の計画。新しいソファを見に行って、その後は映画を観る約束をしたばかりだった。たった数時間前の会話が、まるで遠い過去のように感じられる。
「た、ただいま...」
自分の声が震えていることに気づく。ドアを開けると、台所から由里が顔を出した。白いエプロンに、お気に入りの紺のワンピース姿。結婚してからよく見る光景なのに、今日は特別に痛々しく映る。
「お帰りなさい!ねえ、唐揚げ、もう少しで」
由里の声が途切れた。健一の表情に、何か異変を感じ取ったのだろう。彼女の笑顔が徐々に消えていく。
「どうしたの...?顔色、悪いわよ」
台所から出てきた由里に、黙って赤紙を差し出す。彼女はエプロンを外しながら、おそるおそる受け取った。文書に目を通す彼女の顔が、みるみる血の気を失っていく。
「うそ...でしょう?こんなの...現代の日本じゃ...ありえない...」
由里の声が震えている。書類を持つ手も小刻みに揺れている。健一は何も答えられない。ただ、崩れ落ちそうになる妻を抱きしめることしかできなかった。
「これから...私たち...どうなるの?」
その問いに、健一は答えることができなかった。まだ二人の生活が始まったばかりなのに。これから家族を作っていこうとしていた矢先に。子供部屋にしようと話していた部屋は、このまま物置きのままなのだろうか。なぜ、こんな形で未来を奪われなければならないのか。
台所からは、唐揚げを揚げかけたままの油の香りが漂ってくる。火を止めるのも忘れて、二人は長い間、ただ抱き合っていた。
その夜、健一は眠れなかった。エアコンの微かな音と、時折聞こえる由里の寝返りの音だけが、暗闇の中に響く。天井を見つめながら、いくつもの考えが頭の中を駆け巡る。会社にはどう説明すればいいのか。両親にはなんと伝えればいいのか。そもそも、これは本当に現実なのか。
隣では由里が、不安げな寝息を立てている。普段は安らかに感じる寝顔が、今は痛々しく見えた。結婚指輪が、月明かりに微かに光っている。
窓の外では、いつもと変わらない夜景が広がっていた。マンションの明かりが、星のように点々と灯っている。向かいのビルでは、残業をしているサラリーマンの影が見える。その日常の風景が、今までとは全く違って見える。まるで、もう二度と戻れない異世界の光景のように。
赤紙を受け取った翌朝、健一は会社に向かった。いつもの通勤電車が、どこか非現実的に感じられる。スマートフォンを見ながら無表情に座る会社員たち。彼らは知らない。今、自分の手元にある非常識な召集令状のことを。
その夜、由里と二人でインターネットを徹底的に調べた。「現代」「赤紙」「召集令状」—検索キーワードを変えながら、可能性のある情報を探す。しかし、どれも歴史的な解説か、フィクション作品の話だった。
「これ、偽物なんじゃない?」
由里が震える声で言う。彼女は広告代理店でコピーライターとして働いている。文字や印刷物を見る目には自信があるはずだ。
「でも、この紙質も印刷の質も、一般的な技術では作れないと思う。それに、このエンブレム。見る角度によって模様が変化するの。ホログラムでもこんな精密なものは...」
翌日、都内の法律事務所を三つ回った。どの弁護士も首を傾げるばかり。一人は防衛省の関係者に問い合わせてくれると約束したが、結局、返事はなかった。
時間だけが過ぎていく。由里は会社を休んで付き添ってくれた。実家にも相談しようか迷ったが、却って心配をかけるだけだと思い、止めた。
そうして一週間が経過した。指定された日時、午前九時の十分前——。
突然のインターホンに、二人で顔を見合わせた。
「佐藤健一様、お迎えに参りました」
モニター画面に映っていたのは、黒いスーツに身を包んだ二人の男だった。一見すると普通のビジネススーツに見えたが、生地の質感が異様に滑らかで、光の加減によって微妙に色が変化する。まるで液体金属のようなつやを持っていた。
「行かないで...」
由里が健一の腕にしがみつく。その手が震えているのがわかった。
ドアを開けると、男たちの持つ機器が目に入った。スマートフォンのような形状だが、全面が透明なガラスのようで、その中を青い光が走っている。画面には立体的な文字が浮かび上がり、何かのデータが流れている。明らかに現代の技術レベルを超えていた。
「お時間となりました。ご同行願います」
低く落ち着いた声音。しかし、その中に含まれる威圧感に、背筋が凍る。
「待ってください。せめて、妻に別れを...」
「申し訳ありません。これ以上の接触は許可されておりません」
男の一人が透明な機器を掲げた瞬間、二人の間に青白い光の膜のようなものが形成された。由里の手が、まるで磁石の反発のように健一から離される。
「健一さん!」
由里の悲鳴が、不思議なほど遠くから聞こえる。視界が歪み始め、体が急に重く感じられる。足元がふらつき、意識が遠のいていく。最後に見た由里の表情が、網膜に焼き付いて離れない。
目が覚めたのは、真っ白な天井の下だった。体は柔らかなベッドのような台の上にある。指先を動かすと、布地は通常の繊維とは明らかに異なる感触だった。
「気分はどうですか?」
声をかけてきたのは、白衣を着た若い女性だった。その姿は医師のようでいて、どこか違和感がある。白衣の生地も、先ほどの黒服の男たちと同じような不思議な質感を持っていた。
「ここは...?」
喉が渇いているのか、声が掠れる。
「第七転送施設です。まもなく説明会が始まります」
立ち上がってみると、そこは巨大なドーム状の空間だった。直径は五十メートルはあるだろうか。壁面には見たこともない装置が並び、、半透明のスクリーンに浮かび上がっている。天井からは青白い光が降り注ぎ、未来的な雰囲気を醸し出していた。
部屋の中には、自分と同じように召集されたらしき人々が三十人ほど集まっていた。年齢層は様々。スーツ姿のビジネスマンもいれば、作業着姿の人も。女性は五人ほど。皆一様に困惑した表情を浮かべている。
「君も召集されたのかい?」
声をかけてきたのは、四十代半ばくらいの男性だった。短く刈り込んだ髪に、知的な印象の眼鏡。
「ええ...一週間前に赤紙が」
「私もだ。大学で量子物理を教えているんだが...まさかこんなことになるとは」
話を聞いてみると、他にも様々な分野の専門家が集められているようだった。AIの研究者、宇宙工学の技術者、それに医療関係者。しかし、なぜ自分のようなシステムエンジニアまでが選ばれたのか。そして、この未来的な施設の目的は何なのか。
その時、ドーム中央の空中に、巨大なホログラムが浮かび上がった。三次元の映像が、まるで実体があるかのように空間に浮かぶ。技術者である健一の目には、それが既知の技術の範疇を超えていることが明らかだった。
映像の中で、一人の人物が姿を現した。そして、彼の最初の言葉が、部屋中の空気を凍りつかせた。
「皆様、お待ちしておりました」
巨大なホログラムに映し出された人物は、軍服のような制服を着ていたが、そのデザインは現代の自衛隊のものとは明らかに異なっていた。より洗練された未来的なデザインで、肩章には見たことのない階級章が輝いている。
「私は統合防衛軍第三師団長の山本です。皆様には大変な困惑を与えていることと思います」
その声は穏やかでありながら、強い意志を感じさせるものだった。
「我々は2045年の日本から、皆様を召集しています。この施設は、2025年の日本国政府と我々2045年の日本国政府が共同で運営する特殊施設です。現在の国会でも極秘裏に承認された『時空間安全保障協定』に基づいて設置されています」
会場がざわめいた。健一の隣にいた量子物理学の教授が、眼鏡の奥で目を細める。
「ここで進められているのは『時間徴用計画』と呼ばれる作戦です。2045年の日本は、かつてない規模の戦争に直面しています。その戦争に対処するため、我々は現在の日本政府と協議を重ね、この異例の対応を決定しました」
ホログラムが切り替わり、アジア太平洋地域の地図が浮かび上がった。そこには複雑な戦線が描かれ、紛争地域が赤く示されている。
「2042年に始まるこの戦争は、既存の概念を超えた新しい形の戦争です。AIによる戦術予測、量子暗号通信、ナノテクノロジーを駆使した兵器。しかし、皮肉なことに、この高度に発達した戦争において、最も重要なのは依然として『人材』なのです」
画面が切り替わり、時間軸に沿った図表が現れた。山本師団長は続ける。
「なぜ過去から人材を召集するのか。それは、私たちの時代では得られない特殊な適応力と問題解決能力を持つ方々が必要だからです。2025年は、時代の変化の最中にあり、皆様はかつてない速度で変化する技術環境の中で働いてきました。新技術が次々と登場する中で、常に学び、適応し続けてきた世代です。その経験は、私たちの時代の高度な技術を習得する上で、極めて重要な意味を持ちます。
さらに、皆様は限られたリソースと技術的制約の中で、創意工夫を重ねてきました。システムの根本的な仕組みを理解し、時には手作業での対応も厭わない。そうした柔軟な問題解決能力は、高度に自動化された2045年では失われつつある貴重な資質なのです。システムが完全に機能停止した際、基礎的な部分から問題を解決できる人材が、私たちには必要不可欠なのです」
健一は思わず、となりにいる量子物理学の教授を見た。教授は深い思索に耽っているようだった。
「この計画は、両政府の厳重な管理下で実施されています。現代の自衛隊も、極秘裏にこの施設の警備を担当しています。皆様の家族や周囲の人々の安全は、しっかりと保証されています」
そう言いながら、山本師団長の表情が一瞬曇った。
「しかし、申し訳ありません。この召集には拒否の選択肢がありません。皆様には、まもなく実施される転送プログラムによって、2045年の日本へと移動していただきます」
会場が騒然となった。怒号が飛び交い、中には床に崩れ落ちる者もいる。
「なぜ我々が!」
「家族はどうなる!」
「これは人権侵害だ!」
山本師団長は、その混乱を静かに見つめていた。そして、おもむろに新しい映像を投影した。
「これが、未来です。この戦争は、既に多くの国々を破壊しています。そして日本も、その渦中にあります」
映像は次々と切り替わる。避難する市民たち。破壊された建物。そして、見たこともない兵器で武装した軍隊。
「皆様の召集は、決して軽い決断ではありません。両政府とも、これが最後の手段であることを認識しています。しかし——」
その時、会場の後方で誰かが立ち上がった。五十代くらいの男性だ。
「私には分かります」その男性は静かに、しかし確固とした口調で話し始めた。「私は広島で生まれ育ちました。祖父から聞いた話があります。戦争は、突然日常を破壊します。しかし、その後に来るものはもっと恐ろしい」
会場が静まり返る。
「私たちには、それを止める機会があるということですね」
山本師団長は深く頭を下げた。「はい。その通りです」
休憩時間が設けられ、召集された人々は小グループに分かれて話し合い始めた。健一は量子物理学の教授と、もう一人のソフトウェアエンジニアという女性と話をすることになった。
「私には高校生の息子がいるんです」女性エンジニアが静かな声で話す。「どうして突然、こんな...」
「私も、妻と生まれてくる子供のことを考えると...」健一は言葉を詰まらせた。
「時間軸での人材徴用か...」教授が眼鏡を押し上げながら呟く。「時空間移動が理論的には可能性は指摘されていたが、まさか実現されているとは。しかし、これほどの規模での時空間移動には、莫大なエネルギーが必要なはずだ。両政府が共同でこれを承認し、実行するということは、相当な切迫した状況なのかもしれない」
彼らの会話は、同じような境遇の人々の輪に広がっていった。医師、研究者、技術者——それぞれが自分の人生を突然奪われた衝撃と、残してきた家族への思いを語り合う。
説明会の後、徴用者たちは仮設の宿泊施設に案内された。未来的な装飾が施された建物の中で、健一は一人、窓際に立っていた。外の景色は巧妙に遮断されており、ここが日本のどこなのかも分からない。フロアを横切るたびに、壁に埋め込まれたセンサーが青く光る。
部屋は広くはないが、これまで見たことのない素材で作られた家具が配置されていた。ベッドは一見普通に見えるが、触れると体温に反応するように形を微調整する。デスクの天板は半透明で、中を光が走っているように見える。
健一は、デスクに向かった。与えられた紙とペンで、由里への手紙を書き始める。しかし、ペンは何度も止まり何度も紙を破り捨てた。結局、短い言葉しか残せなかった。
朝日が昇り始めた頃、施設内のスピーカーから声が響いた。
「転送準備を開始します。徴用者の皆様は、指定の集合場所へお集まりください」
アナウンスの声は、不思議なほど温かみがあった。まるで、彼らの決意を待っていたかのように。
集合場所に向かう廊下で、手紙を、施設のスタッフに託す。黒服の男は「必ず配達される」と約束した。それが唯一の救いだった。
それから健一は昨夜の仲間たちと再会した。先ほどまでの脱出劇が嘘のように、皆整然と列を作っている。しかし、その表情は昨夜とは違っていた。
諦めでも、単なる受容でもない。そこにあったのは、未来を変えるという強い決意だった。それは、与えられた運命を受け入れつつ、なおその中で何ができるかを模索する、人間としての意志の表れだった。
転送室は、巨大なドーム状の空間だった。天井までの高さは優に30メートルはあり、その壁面には無数の装置が並んでいる。青く輝くエネルギー導管が網目状に壁を覆い、まるで生命体の血管のようだった。中央には直径20メートルほどの円形プラットフォームがあり、その周囲を青白い光の帯が螺旋状に取り巻いていた。
健一は与えられた白い転送用スーツに袖を通しながら、そのあまりの非現実性に戸惑いを覚えていた。スーツの生地は、触れると微かに温かみがあり、まるで生きているかのように体の動きに合わせて形状を変える。
「では、転送を開始します」
白衣の女性技術者が、宙に浮かぶように見える透明なコンソールに手を置いた。画面には複雑な数式とグラフが次々と展開される。プラットフォームの周囲に立つ12本の支柱が、低い振動音を発し始めた。その先端からは、紫がかった光が放射されている。
「皆様、プラットフォームの中央にお集まりください。所持品は全て専用のコンテナに収められ、別ルートで転送されます」
健一は他の徴用者たちと共に指定の場所へ移動した。足元の金属プレートが微かに脈動しているのが感じられる。表面には幾何学的な文様が刻まれており、それが徐々に淡い光を放ち始めた。
「転送には約30秒を要します。強いめまいを感じる可能性がありますが、これは正常な反応です。意識の喪失を経験する方もいらっしゃいますが、心配はいりません」
カウントダウンが始まると、支柱から放たれる光が徐々に強まっていった。まるで紫がかった霧が空間を満たしていくようだ。健一の視界が歪み始める。世界全体が液体のように揺らぎ、色彩が互いに溶け合っていく。
「10、9、8......」
機械的な声が響く中、健一は懐から取り出したエコー写真を強く握りしめた。由里のことを、そしてまだ見ぬ息子のことを思い浮かべる。
「3、2、1......転送開始」
一瞬の閃光。そして、世界が消失した。
意識が戻ったとき、健一は別の施設の床に横たわっていた。天井の低い、より実務的な印象の空間。医療スタッフらしき人々が、バイタルをチェックしている。
「意識、正常です。バイタルも安定しています」
起き上がると、大きな窓の外には見覚えのある東京の街並みが広がっていた。しかし、それは20年の歳月を経た東京だった。
高層ビル群の形状は基本的に変わっていないものの、その表面は全て光を反射する特殊な素材で覆われていた。建物の外壁には巨大なホログラムが浮かび、天気予報や警報システムの情報が立体的に表示されている。道路には自動運転の車両が整然と流れ、その多くは地上数センチを浮遊していた。空にはドローンらしき物体が規則正しく飛び交い、時折、半透明の円盤のような物体も見える。
街路樹は健在だが、その葉は明らかに人工的な輝きを放っている。幹には微細なセンサーが埋め込まれ、常に環境データを収集しているという。
「環境浄化ナノマシンを組み込んだ改良種です」
案内役の若い士官が説明した。切れ長の目をした30代前半の男性で、名札には「渡辺」とある。
「大気汚染への対策として、街路樹の80%をこのタイプに置き換えています。CO2の吸収効率は従来種の5倍です」
通りを行き交う人々の姿は、しかし、20年前と大きくは変わっていなかった。服装こそ未来的だが、足早に歩くサラリーマン、買い物帰りの主婦、下校途中の学生たち——。その何気ない日常の風景の中に、現代の面影を強く感じた。
人々の多くは、薄型のゴーグルのようなデバイスを身につけている。拡張現実を通して、様々な情報を直接網膜に投影しているのだという。中には、完全な義手や義足を持つ人も珍しくない。その動きは極めて自然で、一目では判別できないほどだ。
「あれが防衛省です」
渡辺士官が指差した先には、巨大な複合施設が建っていた。従来の防衛省とは全く異なる、
「これより、3週間の基礎訓練が始まります」
訓練施設は、地下100メートルの深さに設けられていた。巨大な訓練フロアには、最新の装備が整然と並んでいる。バーチャル戦闘シミュレーターは、完全な没入感を実現する脳内接続型で、実戦さながらの訓練が可能だった。
健一は他の技術者たちと共に、特殊部隊のサイバー戦対策チームに配属された。チームメンバーは10名。全員が2025年からの徴用者だった。
「これが最新の戦術端末です」
配られた装置は、一見するとシンプルな腕時計のように見える。しかし、その機能は現代のスーパーコンピュータを遥かに凌駕していた。量子暗号通信、生体センサー、ホログラフィック投影、脳内接続インターフェース。マニュアルに目を通すだけで、頭が眩むような最先端技術の数々。健一は自分のシステムエンジニアとしての知識を総動員して、この新しい技術の習得に励んだ。
「面白いですよね、この技術」
同じチームのデータサイエンティスト、村上が話しかけてきた。彼女は40代前半の女性で、現代では大手IT企業の研究開発部門で働いていたという。
訓練は過酷を極めた。脳内接続デバイスの使用には強い精神的負荷が伴い、最初の一週間は頭痛に悩まされ続けた。しかし、チームメンバーたちと励まし合いながら、徐々に新しい技術に適応していく。
特に、村上とは親しい関係になっていった。彼女には高校生の息子がいるという。その息子は今、40代になっているはずだ。
ある日、訓練の休憩時間に健一が尋ねた。
「会いたいですか?息子さんに」
村上は遠くを見つめながら答えた。
「ええ」
その言葉に、健一は自分の状況を重ね合わせていた。この2045年のどこかに、自分の子供がいるかもしれない。会いたい気持ちが常に彼の心の中にあった、
2025年、東京。
由里は届けられた手紙を何度も読み返していた。そこには、「由里、そしてこれから生まれてくる自分たちの子供の未来を守る」という言葉だけが記されている。
そして航は、10月4日に生まれた。
「お母さんは強いね」
見舞いに来た友人はそう言った。「一人で育てるって決めたの?」
由里はただ微笑んで頷いた。夫の突然の失踪。家族からは再婚を勧められることもある。しかし、由里は息子を育てることを選んだ。
数年後。息子は父親そっくりに育った。プログラミングの才能、そして何より、強い正義感も。
そして2042年、アジアで最初の戦火が上がった。
高校を卒業したばかりの航は、すでに父親を超える優秀なプログラマーになっていた。
そんなある日、航の元に赤紙が届いた時、由里は何も言えなかった。ただ、強く息子を抱きしめた。
2045年8月15日の朝。
テレビは戦況を伝えている。新型AI兵器の制御システムの異常を直し多くの命を救った一人の戦死した若い兵士を大々的に報道している。そこには航の名前があった。
その日の夕暮れ、由里は六畳間に座っていた。航の成長を見守ってきた部屋。壁には航の写真が何枚も飾られている。
そして人々は気付いていない。この戦争の裏で、時間を超えた戦いが既に始まっていることを。
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
湿気を含んだ空気が、オフィスの窓を伝って滴を作っていた。佐藤健一は目を凝らしてモニターを見つめながら、最後のコードをタイプし終えた。午後五時四十五分。若手エンジニアの育成計画の資料作りに予定より時間がかかってしまった。
「佐藤さん、この部分の実装について質問していいですか?」
新入社員が、おずおずと声をかけてきた。システムエンジニアとして働き始めて七年目の健一は、最近では若手の教育係も任されるようになっていた。
「ああ、このループ処理のところね。ここはね...」
説明を終えると、時計は六時を指していた。健一は画面に映る自分の顔を見た。疲れた目が微かに赤くなっている。早めに帰ろうと思っていたのに、また定時を過ぎてしまった。
「じゃ、お先に失礼します」
デスクの上に置かれた写真立てに目をやる。結婚式の写真だ。白いドレス姿の由里が、はにかんだ笑顔を見せている。写真の横には手帳があった。来週の土曜日に、新居の家具を見に行く約束が書き込まれている。
エレベーターに乗り込みながら、スマートフォンを取り出した。由里からのメッセージが三件届いていた。
『今日は唐揚げ作るね。新しいレシピ見つけたの!』
『あ、ニンニクの効いた甘辛味だよ。健一が好きな感じ』
『仕事、頑張ってる?』
返信を打ちながら、健一は思わず微笑んだ。
「そうだ」健一は突然思いついたように文を送った。
『子供の名前、航って名前はどう?大空を飛ぶイメージで」
由里は妊娠しており健一は早く子供の顔を見たいと思っていた。
『航...素敵な名前ね。私、大好き!』。
健一は会社から帰宅しマンションのエントランスに着くと、同じ階に住む夫妻とすれ違った。二歳の双子を連れた若い夫婦だ。
「あら、佐藤さん。今日は早めなのね」
「ええ、まあ...」
双子が元気に手を振る。健一も笑顔で応えながら、自分たちの未来を想像していた。
そしてポストに手を伸ばすと、普段の郵便物の感触と違う何かがある。チラシや請求書の束に混ざって、一通の封筒が目に留まった。夕陽に照らされ、不自然なまでに赤く輝いている。
一見すると自衛隊を思わせるエンブレムが印刷されている。しかし、よく見ると現行の自衛隊のものとは微妙に異なっていた。より近未来的な、どこか無機質な印象のデザインだ。
教科書の歴史の章でしか見たことのないものが、いま自分の手の中にある。震える指で封を切る。高級な和紙のような手触りの紙が、中から姿を現した。
『召集令状』
黒々とした活字体で印刷された文字が、夕暮れの薄明かりの中で異様な存在感を放っている。
佐藤健一、1992年8月15日生まれ。現住所、職業、家族構成——すべての個人情報が克明に記されている。
「これは...冗談か?」
誰かの悪質ないたずらを疑いたくなる。しかし、封筒の質感も、印刷の精密さも、紛れもなく公文書としか思えない重みがある。それに、このエンブレムの違和感。現代の技術では作れないような、微細な加工が施されているようにも見える。
汗ばんだ手でスマートフォンを取り出し、検索を始める。「赤紙」「召集令状」「現代日本」しかし、関連する記事は戦前の歴史的な解説ばかりで、現代における類似の事例は一件もヒットしない。
マンションの自室の前まで来ると、中からは料理の音と香りが漂ってきた。いつもなら心が躍る瞬間なのに、今は胃の底が凍るような感覚に襲われる。
玄関のドアノブに手をかけた瞬間、ふと思い出した。今朝、由里が話していた週末の計画。新しいソファを見に行って、その後は映画を観る約束をしたばかりだった。たった数時間前の会話が、まるで遠い過去のように感じられる。
「た、ただいま...」
自分の声が震えていることに気づく。ドアを開けると、台所から由里が顔を出した。白いエプロンに、お気に入りの紺のワンピース姿。結婚してからよく見る光景なのに、今日は特別に痛々しく映る。
「お帰りなさい!ねえ、唐揚げ、もう少しで」
由里の声が途切れた。健一の表情に、何か異変を感じ取ったのだろう。彼女の笑顔が徐々に消えていく。
「どうしたの...?顔色、悪いわよ」
台所から出てきた由里に、黙って赤紙を差し出す。彼女はエプロンを外しながら、おそるおそる受け取った。文書に目を通す彼女の顔が、みるみる血の気を失っていく。
「うそ...でしょう?こんなの...現代の日本じゃ...ありえない...」
由里の声が震えている。書類を持つ手も小刻みに揺れている。健一は何も答えられない。ただ、崩れ落ちそうになる妻を抱きしめることしかできなかった。
「これから...私たち...どうなるの?」
その問いに、健一は答えることができなかった。まだ二人の生活が始まったばかりなのに。これから家族を作っていこうとしていた矢先に。子供部屋にしようと話していた部屋は、このまま物置きのままなのだろうか。なぜ、こんな形で未来を奪われなければならないのか。
台所からは、唐揚げを揚げかけたままの油の香りが漂ってくる。火を止めるのも忘れて、二人は長い間、ただ抱き合っていた。
その夜、健一は眠れなかった。エアコンの微かな音と、時折聞こえる由里の寝返りの音だけが、暗闇の中に響く。天井を見つめながら、いくつもの考えが頭の中を駆け巡る。会社にはどう説明すればいいのか。両親にはなんと伝えればいいのか。そもそも、これは本当に現実なのか。
隣では由里が、不安げな寝息を立てている。普段は安らかに感じる寝顔が、今は痛々しく見えた。結婚指輪が、月明かりに微かに光っている。
窓の外では、いつもと変わらない夜景が広がっていた。マンションの明かりが、星のように点々と灯っている。向かいのビルでは、残業をしているサラリーマンの影が見える。その日常の風景が、今までとは全く違って見える。まるで、もう二度と戻れない異世界の光景のように。
「佐藤さん、この部分の実装について質問していいですか?」
新入社員が、おずおずと声をかけてきた。システムエンジニアとして働き始めて七年目の健一は、最近では若手の教育係も任されるようになっていた。
「ああ、このループ処理のところね。ここはね...」
説明を終えると、時計は六時を指していた。健一は画面に映る自分の顔を見た。疲れた目が微かに赤くなっている。早めに帰ろうと思っていたのに、また定時を過ぎてしまった。
「じゃ、お先に失礼します」
デスクの上に置かれた写真立てに目をやる。結婚式の写真だ。白いドレス姿の由里が、はにかんだ笑顔を見せている。写真の横には手帳があった。来週の土曜日に、新居の家具を見に行く約束が書き込まれている。
エレベーターに乗り込みながら、スマートフォンを取り出した。由里からのメッセージが三件届いていた。
『今日は唐揚げ作るね。新しいレシピ見つけたの!』
『あ、ニンニクの効いた甘辛味だよ。健一が好きな感じ』
『仕事、頑張ってる?』
返信を打ちながら、健一は思わず微笑んだ。
「そうだ」健一は突然思いついたように文を送った。
『子供の名前、航って名前はどう?大空を飛ぶイメージで」
由里は妊娠しており健一は早く子供の顔を見たいと思っていた。
『航...素敵な名前ね。私、大好き!』。
健一は会社から帰宅しマンションのエントランスに着くと、同じ階に住む夫妻とすれ違った。二歳の双子を連れた若い夫婦だ。
「あら、佐藤さん。今日は早めなのね」
「ええ、まあ...」
双子が元気に手を振る。健一も笑顔で応えながら、自分たちの未来を想像していた。
そしてポストに手を伸ばすと、普段の郵便物の感触と違う何かがある。チラシや請求書の束に混ざって、一通の封筒が目に留まった。夕陽に照らされ、不自然なまでに赤く輝いている。
一見すると自衛隊を思わせるエンブレムが印刷されている。しかし、よく見ると現行の自衛隊のものとは微妙に異なっていた。より近未来的な、どこか無機質な印象のデザインだ。
教科書の歴史の章でしか見たことのないものが、いま自分の手の中にある。震える指で封を切る。高級な和紙のような手触りの紙が、中から姿を現した。
『召集令状』
黒々とした活字体で印刷された文字が、夕暮れの薄明かりの中で異様な存在感を放っている。
佐藤健一、1992年8月15日生まれ。現住所、職業、家族構成——すべての個人情報が克明に記されている。
「これは...冗談か?」
誰かの悪質ないたずらを疑いたくなる。しかし、封筒の質感も、印刷の精密さも、紛れもなく公文書としか思えない重みがある。それに、このエンブレムの違和感。現代の技術では作れないような、微細な加工が施されているようにも見える。
汗ばんだ手でスマートフォンを取り出し、検索を始める。「赤紙」「召集令状」「現代日本」しかし、関連する記事は戦前の歴史的な解説ばかりで、現代における類似の事例は一件もヒットしない。
マンションの自室の前まで来ると、中からは料理の音と香りが漂ってきた。いつもなら心が躍る瞬間なのに、今は胃の底が凍るような感覚に襲われる。
玄関のドアノブに手をかけた瞬間、ふと思い出した。今朝、由里が話していた週末の計画。新しいソファを見に行って、その後は映画を観る約束をしたばかりだった。たった数時間前の会話が、まるで遠い過去のように感じられる。
「た、ただいま...」
自分の声が震えていることに気づく。ドアを開けると、台所から由里が顔を出した。白いエプロンに、お気に入りの紺のワンピース姿。結婚してからよく見る光景なのに、今日は特別に痛々しく映る。
「お帰りなさい!ねえ、唐揚げ、もう少しで」
由里の声が途切れた。健一の表情に、何か異変を感じ取ったのだろう。彼女の笑顔が徐々に消えていく。
「どうしたの...?顔色、悪いわよ」
台所から出てきた由里に、黙って赤紙を差し出す。彼女はエプロンを外しながら、おそるおそる受け取った。文書に目を通す彼女の顔が、みるみる血の気を失っていく。
「うそ...でしょう?こんなの...現代の日本じゃ...ありえない...」
由里の声が震えている。書類を持つ手も小刻みに揺れている。健一は何も答えられない。ただ、崩れ落ちそうになる妻を抱きしめることしかできなかった。
「これから...私たち...どうなるの?」
その問いに、健一は答えることができなかった。まだ二人の生活が始まったばかりなのに。これから家族を作っていこうとしていた矢先に。子供部屋にしようと話していた部屋は、このまま物置きのままなのだろうか。なぜ、こんな形で未来を奪われなければならないのか。
台所からは、唐揚げを揚げかけたままの油の香りが漂ってくる。火を止めるのも忘れて、二人は長い間、ただ抱き合っていた。
その夜、健一は眠れなかった。エアコンの微かな音と、時折聞こえる由里の寝返りの音だけが、暗闇の中に響く。天井を見つめながら、いくつもの考えが頭の中を駆け巡る。会社にはどう説明すればいいのか。両親にはなんと伝えればいいのか。そもそも、これは本当に現実なのか。
隣では由里が、不安げな寝息を立てている。普段は安らかに感じる寝顔が、今は痛々しく見えた。結婚指輪が、月明かりに微かに光っている。
窓の外では、いつもと変わらない夜景が広がっていた。マンションの明かりが、星のように点々と灯っている。向かいのビルでは、残業をしているサラリーマンの影が見える。その日常の風景が、今までとは全く違って見える。まるで、もう二度と戻れない異世界の光景のように。
赤紙を受け取った翌朝、健一は会社に向かった。いつもの通勤電車が、どこか非現実的に感じられる。スマートフォンを見ながら無表情に座る会社員たち。彼らは知らない。今、自分の手元にある非常識な召集令状のことを。
その夜、由里と二人でインターネットを徹底的に調べた。「現代」「赤紙」「召集令状」—検索キーワードを変えながら、可能性のある情報を探す。しかし、どれも歴史的な解説か、フィクション作品の話だった。
「これ、偽物なんじゃない?」
由里が震える声で言う。彼女は広告代理店でコピーライターとして働いている。文字や印刷物を見る目には自信があるはずだ。
「でも、この紙質も印刷の質も、一般的な技術では作れないと思う。それに、このエンブレム。見る角度によって模様が変化するの。ホログラムでもこんな精密なものは...」
翌日、都内の法律事務所を三つ回った。どの弁護士も首を傾げるばかり。一人は防衛省の関係者に問い合わせてくれると約束したが、結局、返事はなかった。
時間だけが過ぎていく。由里は会社を休んで付き添ってくれた。実家にも相談しようか迷ったが、却って心配をかけるだけだと思い、止めた。
そうして一週間が経過した。指定された日時、午前九時の十分前——。
突然のインターホンに、二人で顔を見合わせた。
「佐藤健一様、お迎えに参りました」
モニター画面に映っていたのは、黒いスーツに身を包んだ二人の男だった。一見すると普通のビジネススーツに見えたが、生地の質感が異様に滑らかで、光の加減によって微妙に色が変化する。まるで液体金属のようなつやを持っていた。
「行かないで...」
由里が健一の腕にしがみつく。その手が震えているのがわかった。
ドアを開けると、男たちの持つ機器が目に入った。スマートフォンのような形状だが、全面が透明なガラスのようで、その中を青い光が走っている。画面には立体的な文字が浮かび上がり、何かのデータが流れている。明らかに現代の技術レベルを超えていた。
「お時間となりました。ご同行願います」
低く落ち着いた声音。しかし、その中に含まれる威圧感に、背筋が凍る。
「待ってください。せめて、妻に別れを...」
「申し訳ありません。これ以上の接触は許可されておりません」
男の一人が透明な機器を掲げた瞬間、二人の間に青白い光の膜のようなものが形成された。由里の手が、まるで磁石の反発のように健一から離される。
「健一さん!」
由里の悲鳴が、不思議なほど遠くから聞こえる。視界が歪み始め、体が急に重く感じられる。足元がふらつき、意識が遠のいていく。最後に見た由里の表情が、網膜に焼き付いて離れない。
目が覚めたのは、真っ白な天井の下だった。体は柔らかなベッドのような台の上にある。指先を動かすと、布地は通常の繊維とは明らかに異なる感触だった。
「気分はどうですか?」
声をかけてきたのは、白衣を着た若い女性だった。その姿は医師のようでいて、どこか違和感がある。白衣の生地も、先ほどの黒服の男たちと同じような不思議な質感を持っていた。
「ここは...?」
喉が渇いているのか、声が掠れる。
「第七転送施設です。まもなく説明会が始まります」
立ち上がってみると、そこは巨大なドーム状の空間だった。直径は五十メートルはあるだろうか。壁面には見たこともない装置が並び、、半透明のスクリーンに浮かび上がっている。天井からは青白い光が降り注ぎ、未来的な雰囲気を醸し出していた。
部屋の中には、自分と同じように召集されたらしき人々が三十人ほど集まっていた。年齢層は様々。スーツ姿のビジネスマンもいれば、作業着姿の人も。女性は五人ほど。皆一様に困惑した表情を浮かべている。
「君も召集されたのかい?」
声をかけてきたのは、四十代半ばくらいの男性だった。短く刈り込んだ髪に、知的な印象の眼鏡。
「ええ...一週間前に赤紙が」
「私もだ。大学で量子物理を教えているんだが...まさかこんなことになるとは」
話を聞いてみると、他にも様々な分野の専門家が集められているようだった。AIの研究者、宇宙工学の技術者、それに医療関係者。しかし、なぜ自分のようなシステムエンジニアまでが選ばれたのか。そして、この未来的な施設の目的は何なのか。
その時、ドーム中央の空中に、巨大なホログラムが浮かび上がった。三次元の映像が、まるで実体があるかのように空間に浮かぶ。技術者である健一の目には、それが既知の技術の範疇を超えていることが明らかだった。
映像の中で、一人の人物が姿を現した。そして、彼の最初の言葉が、部屋中の空気を凍りつかせた。
「皆様、お待ちしておりました」
その夜、由里と二人でインターネットを徹底的に調べた。「現代」「赤紙」「召集令状」—検索キーワードを変えながら、可能性のある情報を探す。しかし、どれも歴史的な解説か、フィクション作品の話だった。
「これ、偽物なんじゃない?」
由里が震える声で言う。彼女は広告代理店でコピーライターとして働いている。文字や印刷物を見る目には自信があるはずだ。
「でも、この紙質も印刷の質も、一般的な技術では作れないと思う。それに、このエンブレム。見る角度によって模様が変化するの。ホログラムでもこんな精密なものは...」
翌日、都内の法律事務所を三つ回った。どの弁護士も首を傾げるばかり。一人は防衛省の関係者に問い合わせてくれると約束したが、結局、返事はなかった。
時間だけが過ぎていく。由里は会社を休んで付き添ってくれた。実家にも相談しようか迷ったが、却って心配をかけるだけだと思い、止めた。
そうして一週間が経過した。指定された日時、午前九時の十分前——。
突然のインターホンに、二人で顔を見合わせた。
「佐藤健一様、お迎えに参りました」
モニター画面に映っていたのは、黒いスーツに身を包んだ二人の男だった。一見すると普通のビジネススーツに見えたが、生地の質感が異様に滑らかで、光の加減によって微妙に色が変化する。まるで液体金属のようなつやを持っていた。
「行かないで...」
由里が健一の腕にしがみつく。その手が震えているのがわかった。
ドアを開けると、男たちの持つ機器が目に入った。スマートフォンのような形状だが、全面が透明なガラスのようで、その中を青い光が走っている。画面には立体的な文字が浮かび上がり、何かのデータが流れている。明らかに現代の技術レベルを超えていた。
「お時間となりました。ご同行願います」
低く落ち着いた声音。しかし、その中に含まれる威圧感に、背筋が凍る。
「待ってください。せめて、妻に別れを...」
「申し訳ありません。これ以上の接触は許可されておりません」
男の一人が透明な機器を掲げた瞬間、二人の間に青白い光の膜のようなものが形成された。由里の手が、まるで磁石の反発のように健一から離される。
「健一さん!」
由里の悲鳴が、不思議なほど遠くから聞こえる。視界が歪み始め、体が急に重く感じられる。足元がふらつき、意識が遠のいていく。最後に見た由里の表情が、網膜に焼き付いて離れない。
目が覚めたのは、真っ白な天井の下だった。体は柔らかなベッドのような台の上にある。指先を動かすと、布地は通常の繊維とは明らかに異なる感触だった。
「気分はどうですか?」
声をかけてきたのは、白衣を着た若い女性だった。その姿は医師のようでいて、どこか違和感がある。白衣の生地も、先ほどの黒服の男たちと同じような不思議な質感を持っていた。
「ここは...?」
喉が渇いているのか、声が掠れる。
「第七転送施設です。まもなく説明会が始まります」
立ち上がってみると、そこは巨大なドーム状の空間だった。直径は五十メートルはあるだろうか。壁面には見たこともない装置が並び、、半透明のスクリーンに浮かび上がっている。天井からは青白い光が降り注ぎ、未来的な雰囲気を醸し出していた。
部屋の中には、自分と同じように召集されたらしき人々が三十人ほど集まっていた。年齢層は様々。スーツ姿のビジネスマンもいれば、作業着姿の人も。女性は五人ほど。皆一様に困惑した表情を浮かべている。
「君も召集されたのかい?」
声をかけてきたのは、四十代半ばくらいの男性だった。短く刈り込んだ髪に、知的な印象の眼鏡。
「ええ...一週間前に赤紙が」
「私もだ。大学で量子物理を教えているんだが...まさかこんなことになるとは」
話を聞いてみると、他にも様々な分野の専門家が集められているようだった。AIの研究者、宇宙工学の技術者、それに医療関係者。しかし、なぜ自分のようなシステムエンジニアまでが選ばれたのか。そして、この未来的な施設の目的は何なのか。
その時、ドーム中央の空中に、巨大なホログラムが浮かび上がった。三次元の映像が、まるで実体があるかのように空間に浮かぶ。技術者である健一の目には、それが既知の技術の範疇を超えていることが明らかだった。
映像の中で、一人の人物が姿を現した。そして、彼の最初の言葉が、部屋中の空気を凍りつかせた。
「皆様、お待ちしておりました」
巨大なホログラムに映し出された人物は、軍服のような制服を着ていたが、そのデザインは現代の自衛隊のものとは明らかに異なっていた。より洗練された未来的なデザインで、肩章には見たことのない階級章が輝いている。
「私は統合防衛軍第三師団長の山本です。皆様には大変な困惑を与えていることと思います」
その声は穏やかでありながら、強い意志を感じさせるものだった。
「我々は2045年の日本から、皆様を召集しています。この施設は、2025年の日本国政府と我々2045年の日本国政府が共同で運営する特殊施設です。現在の国会でも極秘裏に承認された『時空間安全保障協定』に基づいて設置されています」
会場がざわめいた。健一の隣にいた量子物理学の教授が、眼鏡の奥で目を細める。
「ここで進められているのは『時間徴用計画』と呼ばれる作戦です。2045年の日本は、かつてない規模の戦争に直面しています。その戦争に対処するため、我々は現在の日本政府と協議を重ね、この異例の対応を決定しました」
ホログラムが切り替わり、アジア太平洋地域の地図が浮かび上がった。そこには複雑な戦線が描かれ、紛争地域が赤く示されている。
「2042年に始まるこの戦争は、既存の概念を超えた新しい形の戦争です。AIによる戦術予測、量子暗号通信、ナノテクノロジーを駆使した兵器。しかし、皮肉なことに、この高度に発達した戦争において、最も重要なのは依然として『人材』なのです」
画面が切り替わり、時間軸に沿った図表が現れた。山本師団長は続ける。
「なぜ過去から人材を召集するのか。それは、私たちの時代では得られない特殊な適応力と問題解決能力を持つ方々が必要だからです。2025年は、時代の変化の最中にあり、皆様はかつてない速度で変化する技術環境の中で働いてきました。新技術が次々と登場する中で、常に学び、適応し続けてきた世代です。その経験は、私たちの時代の高度な技術を習得する上で、極めて重要な意味を持ちます。
さらに、皆様は限られたリソースと技術的制約の中で、創意工夫を重ねてきました。システムの根本的な仕組みを理解し、時には手作業での対応も厭わない。そうした柔軟な問題解決能力は、高度に自動化された2045年では失われつつある貴重な資質なのです。システムが完全に機能停止した際、基礎的な部分から問題を解決できる人材が、私たちには必要不可欠なのです」
健一は思わず、となりにいる量子物理学の教授を見た。教授は深い思索に耽っているようだった。
「この計画は、両政府の厳重な管理下で実施されています。現代の自衛隊も、極秘裏にこの施設の警備を担当しています。皆様の家族や周囲の人々の安全は、しっかりと保証されています」
そう言いながら、山本師団長の表情が一瞬曇った。
「しかし、申し訳ありません。この召集には拒否の選択肢がありません。皆様には、まもなく実施される転送プログラムによって、2045年の日本へと移動していただきます」
会場が騒然となった。怒号が飛び交い、中には床に崩れ落ちる者もいる。
「なぜ我々が!」
「家族はどうなる!」
「これは人権侵害だ!」
山本師団長は、その混乱を静かに見つめていた。そして、おもむろに新しい映像を投影した。
「これが、未来です。この戦争は、既に多くの国々を破壊しています。そして日本も、その渦中にあります」
映像は次々と切り替わる。避難する市民たち。破壊された建物。そして、見たこともない兵器で武装した軍隊。
「皆様の召集は、決して軽い決断ではありません。両政府とも、これが最後の手段であることを認識しています。しかし——」
その時、会場の後方で誰かが立ち上がった。五十代くらいの男性だ。
「私には分かります」その男性は静かに、しかし確固とした口調で話し始めた。「私は広島で生まれ育ちました。祖父から聞いた話があります。戦争は、突然日常を破壊します。しかし、その後に来るものはもっと恐ろしい」
会場が静まり返る。
「私たちには、それを止める機会があるということですね」
山本師団長は深く頭を下げた。「はい。その通りです」
休憩時間が設けられ、召集された人々は小グループに分かれて話し合い始めた。健一は量子物理学の教授と、もう一人のソフトウェアエンジニアという女性と話をすることになった。
「私には高校生の息子がいるんです」女性エンジニアが静かな声で話す。「どうして突然、こんな...」
「私も、妻と生まれてくる子供のことを考えると...」健一は言葉を詰まらせた。
「時間軸での人材徴用か...」教授が眼鏡を押し上げながら呟く。「時空間移動が理論的には可能性は指摘されていたが、まさか実現されているとは。しかし、これほどの規模での時空間移動には、莫大なエネルギーが必要なはずだ。両政府が共同でこれを承認し、実行するということは、相当な切迫した状況なのかもしれない」
彼らの会話は、同じような境遇の人々の輪に広がっていった。医師、研究者、技術者——それぞれが自分の人生を突然奪われた衝撃と、残してきた家族への思いを語り合う。
「私は統合防衛軍第三師団長の山本です。皆様には大変な困惑を与えていることと思います」
その声は穏やかでありながら、強い意志を感じさせるものだった。
「我々は2045年の日本から、皆様を召集しています。この施設は、2025年の日本国政府と我々2045年の日本国政府が共同で運営する特殊施設です。現在の国会でも極秘裏に承認された『時空間安全保障協定』に基づいて設置されています」
会場がざわめいた。健一の隣にいた量子物理学の教授が、眼鏡の奥で目を細める。
「ここで進められているのは『時間徴用計画』と呼ばれる作戦です。2045年の日本は、かつてない規模の戦争に直面しています。その戦争に対処するため、我々は現在の日本政府と協議を重ね、この異例の対応を決定しました」
ホログラムが切り替わり、アジア太平洋地域の地図が浮かび上がった。そこには複雑な戦線が描かれ、紛争地域が赤く示されている。
「2042年に始まるこの戦争は、既存の概念を超えた新しい形の戦争です。AIによる戦術予測、量子暗号通信、ナノテクノロジーを駆使した兵器。しかし、皮肉なことに、この高度に発達した戦争において、最も重要なのは依然として『人材』なのです」
画面が切り替わり、時間軸に沿った図表が現れた。山本師団長は続ける。
「なぜ過去から人材を召集するのか。それは、私たちの時代では得られない特殊な適応力と問題解決能力を持つ方々が必要だからです。2025年は、時代の変化の最中にあり、皆様はかつてない速度で変化する技術環境の中で働いてきました。新技術が次々と登場する中で、常に学び、適応し続けてきた世代です。その経験は、私たちの時代の高度な技術を習得する上で、極めて重要な意味を持ちます。
さらに、皆様は限られたリソースと技術的制約の中で、創意工夫を重ねてきました。システムの根本的な仕組みを理解し、時には手作業での対応も厭わない。そうした柔軟な問題解決能力は、高度に自動化された2045年では失われつつある貴重な資質なのです。システムが完全に機能停止した際、基礎的な部分から問題を解決できる人材が、私たちには必要不可欠なのです」
健一は思わず、となりにいる量子物理学の教授を見た。教授は深い思索に耽っているようだった。
「この計画は、両政府の厳重な管理下で実施されています。現代の自衛隊も、極秘裏にこの施設の警備を担当しています。皆様の家族や周囲の人々の安全は、しっかりと保証されています」
そう言いながら、山本師団長の表情が一瞬曇った。
「しかし、申し訳ありません。この召集には拒否の選択肢がありません。皆様には、まもなく実施される転送プログラムによって、2045年の日本へと移動していただきます」
会場が騒然となった。怒号が飛び交い、中には床に崩れ落ちる者もいる。
「なぜ我々が!」
「家族はどうなる!」
「これは人権侵害だ!」
山本師団長は、その混乱を静かに見つめていた。そして、おもむろに新しい映像を投影した。
「これが、未来です。この戦争は、既に多くの国々を破壊しています。そして日本も、その渦中にあります」
映像は次々と切り替わる。避難する市民たち。破壊された建物。そして、見たこともない兵器で武装した軍隊。
「皆様の召集は、決して軽い決断ではありません。両政府とも、これが最後の手段であることを認識しています。しかし——」
その時、会場の後方で誰かが立ち上がった。五十代くらいの男性だ。
「私には分かります」その男性は静かに、しかし確固とした口調で話し始めた。「私は広島で生まれ育ちました。祖父から聞いた話があります。戦争は、突然日常を破壊します。しかし、その後に来るものはもっと恐ろしい」
会場が静まり返る。
「私たちには、それを止める機会があるということですね」
山本師団長は深く頭を下げた。「はい。その通りです」
休憩時間が設けられ、召集された人々は小グループに分かれて話し合い始めた。健一は量子物理学の教授と、もう一人のソフトウェアエンジニアという女性と話をすることになった。
「私には高校生の息子がいるんです」女性エンジニアが静かな声で話す。「どうして突然、こんな...」
「私も、妻と生まれてくる子供のことを考えると...」健一は言葉を詰まらせた。
「時間軸での人材徴用か...」教授が眼鏡を押し上げながら呟く。「時空間移動が理論的には可能性は指摘されていたが、まさか実現されているとは。しかし、これほどの規模での時空間移動には、莫大なエネルギーが必要なはずだ。両政府が共同でこれを承認し、実行するということは、相当な切迫した状況なのかもしれない」
彼らの会話は、同じような境遇の人々の輪に広がっていった。医師、研究者、技術者——それぞれが自分の人生を突然奪われた衝撃と、残してきた家族への思いを語り合う。
説明会の後、徴用者たちは仮設の宿泊施設に案内された。未来的な装飾が施された建物の中で、健一は一人、窓際に立っていた。外の景色は巧妙に遮断されており、ここが日本のどこなのかも分からない。フロアを横切るたびに、壁に埋め込まれたセンサーが青く光る。
部屋は広くはないが、これまで見たことのない素材で作られた家具が配置されていた。ベッドは一見普通に見えるが、触れると体温に反応するように形を微調整する。デスクの天板は半透明で、中を光が走っているように見える。
健一は、デスクに向かった。与えられた紙とペンで、由里への手紙を書き始める。しかし、ペンは何度も止まり何度も紙を破り捨てた。結局、短い言葉しか残せなかった。
朝日が昇り始めた頃、施設内のスピーカーから声が響いた。
「転送準備を開始します。徴用者の皆様は、指定の集合場所へお集まりください」
アナウンスの声は、不思議なほど温かみがあった。まるで、彼らの決意を待っていたかのように。
集合場所に向かう廊下で、手紙を、施設のスタッフに託す。黒服の男は「必ず配達される」と約束した。それが唯一の救いだった。
それから健一は昨夜の仲間たちと再会した。先ほどまでの脱出劇が嘘のように、皆整然と列を作っている。しかし、その表情は昨夜とは違っていた。
諦めでも、単なる受容でもない。そこにあったのは、未来を変えるという強い決意だった。それは、与えられた運命を受け入れつつ、なおその中で何ができるかを模索する、人間としての意志の表れだった。
部屋は広くはないが、これまで見たことのない素材で作られた家具が配置されていた。ベッドは一見普通に見えるが、触れると体温に反応するように形を微調整する。デスクの天板は半透明で、中を光が走っているように見える。
健一は、デスクに向かった。与えられた紙とペンで、由里への手紙を書き始める。しかし、ペンは何度も止まり何度も紙を破り捨てた。結局、短い言葉しか残せなかった。
朝日が昇り始めた頃、施設内のスピーカーから声が響いた。
「転送準備を開始します。徴用者の皆様は、指定の集合場所へお集まりください」
アナウンスの声は、不思議なほど温かみがあった。まるで、彼らの決意を待っていたかのように。
集合場所に向かう廊下で、手紙を、施設のスタッフに託す。黒服の男は「必ず配達される」と約束した。それが唯一の救いだった。
それから健一は昨夜の仲間たちと再会した。先ほどまでの脱出劇が嘘のように、皆整然と列を作っている。しかし、その表情は昨夜とは違っていた。
諦めでも、単なる受容でもない。そこにあったのは、未来を変えるという強い決意だった。それは、与えられた運命を受け入れつつ、なおその中で何ができるかを模索する、人間としての意志の表れだった。
転送室は、巨大なドーム状の空間だった。天井までの高さは優に30メートルはあり、その壁面には無数の装置が並んでいる。青く輝くエネルギー導管が網目状に壁を覆い、まるで生命体の血管のようだった。中央には直径20メートルほどの円形プラットフォームがあり、その周囲を青白い光の帯が螺旋状に取り巻いていた。
健一は与えられた白い転送用スーツに袖を通しながら、そのあまりの非現実性に戸惑いを覚えていた。スーツの生地は、触れると微かに温かみがあり、まるで生きているかのように体の動きに合わせて形状を変える。
「では、転送を開始します」
白衣の女性技術者が、宙に浮かぶように見える透明なコンソールに手を置いた。画面には複雑な数式とグラフが次々と展開される。プラットフォームの周囲に立つ12本の支柱が、低い振動音を発し始めた。その先端からは、紫がかった光が放射されている。
「皆様、プラットフォームの中央にお集まりください。所持品は全て専用のコンテナに収められ、別ルートで転送されます」
健一は他の徴用者たちと共に指定の場所へ移動した。足元の金属プレートが微かに脈動しているのが感じられる。表面には幾何学的な文様が刻まれており、それが徐々に淡い光を放ち始めた。
「転送には約30秒を要します。強いめまいを感じる可能性がありますが、これは正常な反応です。意識の喪失を経験する方もいらっしゃいますが、心配はいりません」
カウントダウンが始まると、支柱から放たれる光が徐々に強まっていった。まるで紫がかった霧が空間を満たしていくようだ。健一の視界が歪み始める。世界全体が液体のように揺らぎ、色彩が互いに溶け合っていく。
「10、9、8......」
機械的な声が響く中、健一は懐から取り出したエコー写真を強く握りしめた。由里のことを、そしてまだ見ぬ息子のことを思い浮かべる。
「3、2、1......転送開始」
一瞬の閃光。そして、世界が消失した。
意識が戻ったとき、健一は別の施設の床に横たわっていた。天井の低い、より実務的な印象の空間。医療スタッフらしき人々が、バイタルをチェックしている。
「意識、正常です。バイタルも安定しています」
起き上がると、大きな窓の外には見覚えのある東京の街並みが広がっていた。しかし、それは20年の歳月を経た東京だった。
高層ビル群の形状は基本的に変わっていないものの、その表面は全て光を反射する特殊な素材で覆われていた。建物の外壁には巨大なホログラムが浮かび、天気予報や警報システムの情報が立体的に表示されている。道路には自動運転の車両が整然と流れ、その多くは地上数センチを浮遊していた。空にはドローンらしき物体が規則正しく飛び交い、時折、半透明の円盤のような物体も見える。
街路樹は健在だが、その葉は明らかに人工的な輝きを放っている。幹には微細なセンサーが埋め込まれ、常に環境データを収集しているという。
「環境浄化ナノマシンを組み込んだ改良種です」
案内役の若い士官が説明した。切れ長の目をした30代前半の男性で、名札には「渡辺」とある。
「大気汚染への対策として、街路樹の80%をこのタイプに置き換えています。CO2の吸収効率は従来種の5倍です」
通りを行き交う人々の姿は、しかし、20年前と大きくは変わっていなかった。服装こそ未来的だが、足早に歩くサラリーマン、買い物帰りの主婦、下校途中の学生たち——。その何気ない日常の風景の中に、現代の面影を強く感じた。
人々の多くは、薄型のゴーグルのようなデバイスを身につけている。拡張現実を通して、様々な情報を直接網膜に投影しているのだという。中には、完全な義手や義足を持つ人も珍しくない。その動きは極めて自然で、一目では判別できないほどだ。
「あれが防衛省です」
渡辺士官が指差した先には、巨大な複合施設が建っていた。従来の防衛省とは全く異なる、
「これより、3週間の基礎訓練が始まります」
訓練施設は、地下100メートルの深さに設けられていた。巨大な訓練フロアには、最新の装備が整然と並んでいる。バーチャル戦闘シミュレーターは、完全な没入感を実現する脳内接続型で、実戦さながらの訓練が可能だった。
健一は他の技術者たちと共に、特殊部隊のサイバー戦対策チームに配属された。チームメンバーは10名。全員が2025年からの徴用者だった。
「これが最新の戦術端末です」
配られた装置は、一見するとシンプルな腕時計のように見える。しかし、その機能は現代のスーパーコンピュータを遥かに凌駕していた。量子暗号通信、生体センサー、ホログラフィック投影、脳内接続インターフェース。マニュアルに目を通すだけで、頭が眩むような最先端技術の数々。健一は自分のシステムエンジニアとしての知識を総動員して、この新しい技術の習得に励んだ。
「面白いですよね、この技術」
同じチームのデータサイエンティスト、村上が話しかけてきた。彼女は40代前半の女性で、現代では大手IT企業の研究開発部門で働いていたという。
訓練は過酷を極めた。脳内接続デバイスの使用には強い精神的負荷が伴い、最初の一週間は頭痛に悩まされ続けた。しかし、チームメンバーたちと励まし合いながら、徐々に新しい技術に適応していく。
特に、村上とは親しい関係になっていった。彼女には高校生の息子がいるという。その息子は今、40代になっているはずだ。
ある日、訓練の休憩時間に健一が尋ねた。
「会いたいですか?息子さんに」
村上は遠くを見つめながら答えた。
「ええ」
その言葉に、健一は自分の状況を重ね合わせていた。この2045年のどこかに、自分の子供がいるかもしれない。会いたい気持ちが常に彼の心の中にあった、
健一は与えられた白い転送用スーツに袖を通しながら、そのあまりの非現実性に戸惑いを覚えていた。スーツの生地は、触れると微かに温かみがあり、まるで生きているかのように体の動きに合わせて形状を変える。
「では、転送を開始します」
白衣の女性技術者が、宙に浮かぶように見える透明なコンソールに手を置いた。画面には複雑な数式とグラフが次々と展開される。プラットフォームの周囲に立つ12本の支柱が、低い振動音を発し始めた。その先端からは、紫がかった光が放射されている。
「皆様、プラットフォームの中央にお集まりください。所持品は全て専用のコンテナに収められ、別ルートで転送されます」
健一は他の徴用者たちと共に指定の場所へ移動した。足元の金属プレートが微かに脈動しているのが感じられる。表面には幾何学的な文様が刻まれており、それが徐々に淡い光を放ち始めた。
「転送には約30秒を要します。強いめまいを感じる可能性がありますが、これは正常な反応です。意識の喪失を経験する方もいらっしゃいますが、心配はいりません」
カウントダウンが始まると、支柱から放たれる光が徐々に強まっていった。まるで紫がかった霧が空間を満たしていくようだ。健一の視界が歪み始める。世界全体が液体のように揺らぎ、色彩が互いに溶け合っていく。
「10、9、8......」
機械的な声が響く中、健一は懐から取り出したエコー写真を強く握りしめた。由里のことを、そしてまだ見ぬ息子のことを思い浮かべる。
「3、2、1......転送開始」
一瞬の閃光。そして、世界が消失した。
意識が戻ったとき、健一は別の施設の床に横たわっていた。天井の低い、より実務的な印象の空間。医療スタッフらしき人々が、バイタルをチェックしている。
「意識、正常です。バイタルも安定しています」
起き上がると、大きな窓の外には見覚えのある東京の街並みが広がっていた。しかし、それは20年の歳月を経た東京だった。
高層ビル群の形状は基本的に変わっていないものの、その表面は全て光を反射する特殊な素材で覆われていた。建物の外壁には巨大なホログラムが浮かび、天気予報や警報システムの情報が立体的に表示されている。道路には自動運転の車両が整然と流れ、その多くは地上数センチを浮遊していた。空にはドローンらしき物体が規則正しく飛び交い、時折、半透明の円盤のような物体も見える。
街路樹は健在だが、その葉は明らかに人工的な輝きを放っている。幹には微細なセンサーが埋め込まれ、常に環境データを収集しているという。
「環境浄化ナノマシンを組み込んだ改良種です」
案内役の若い士官が説明した。切れ長の目をした30代前半の男性で、名札には「渡辺」とある。
「大気汚染への対策として、街路樹の80%をこのタイプに置き換えています。CO2の吸収効率は従来種の5倍です」
通りを行き交う人々の姿は、しかし、20年前と大きくは変わっていなかった。服装こそ未来的だが、足早に歩くサラリーマン、買い物帰りの主婦、下校途中の学生たち——。その何気ない日常の風景の中に、現代の面影を強く感じた。
人々の多くは、薄型のゴーグルのようなデバイスを身につけている。拡張現実を通して、様々な情報を直接網膜に投影しているのだという。中には、完全な義手や義足を持つ人も珍しくない。その動きは極めて自然で、一目では判別できないほどだ。
「あれが防衛省です」
渡辺士官が指差した先には、巨大な複合施設が建っていた。従来の防衛省とは全く異なる、
「これより、3週間の基礎訓練が始まります」
訓練施設は、地下100メートルの深さに設けられていた。巨大な訓練フロアには、最新の装備が整然と並んでいる。バーチャル戦闘シミュレーターは、完全な没入感を実現する脳内接続型で、実戦さながらの訓練が可能だった。
健一は他の技術者たちと共に、特殊部隊のサイバー戦対策チームに配属された。チームメンバーは10名。全員が2025年からの徴用者だった。
「これが最新の戦術端末です」
配られた装置は、一見するとシンプルな腕時計のように見える。しかし、その機能は現代のスーパーコンピュータを遥かに凌駕していた。量子暗号通信、生体センサー、ホログラフィック投影、脳内接続インターフェース。マニュアルに目を通すだけで、頭が眩むような最先端技術の数々。健一は自分のシステムエンジニアとしての知識を総動員して、この新しい技術の習得に励んだ。
「面白いですよね、この技術」
同じチームのデータサイエンティスト、村上が話しかけてきた。彼女は40代前半の女性で、現代では大手IT企業の研究開発部門で働いていたという。
訓練は過酷を極めた。脳内接続デバイスの使用には強い精神的負荷が伴い、最初の一週間は頭痛に悩まされ続けた。しかし、チームメンバーたちと励まし合いながら、徐々に新しい技術に適応していく。
特に、村上とは親しい関係になっていった。彼女には高校生の息子がいるという。その息子は今、40代になっているはずだ。
ある日、訓練の休憩時間に健一が尋ねた。
「会いたいですか?息子さんに」
村上は遠くを見つめながら答えた。
「ええ」
その言葉に、健一は自分の状況を重ね合わせていた。この2045年のどこかに、自分の子供がいるかもしれない。会いたい気持ちが常に彼の心の中にあった、
2025年、東京。
由里は届けられた手紙を何度も読み返していた。そこには、「由里、そしてこれから生まれてくる自分たちの子供の未来を守る」という言葉だけが記されている。
そして航は、10月4日に生まれた。
「お母さんは強いね」
見舞いに来た友人はそう言った。「一人で育てるって決めたの?」
由里はただ微笑んで頷いた。夫の突然の失踪。家族からは再婚を勧められることもある。しかし、由里は息子を育てることを選んだ。
数年後。息子は父親そっくりに育った。プログラミングの才能、そして何より、強い正義感も。
そして2042年、アジアで最初の戦火が上がった。
高校を卒業したばかりの航は、すでに父親を超える優秀なプログラマーになっていた。
そんなある日、航の元に赤紙が届いた時、由里は何も言えなかった。ただ、強く息子を抱きしめた。
2045年8月15日の朝。
テレビは戦況を伝えている。新型AI兵器の制御システムの異常を直し多くの命を救った一人の戦死した若い兵士を大々的に報道している。そこには航の名前があった。
その日の夕暮れ、由里は六畳間に座っていた。航の成長を見守ってきた部屋。壁には航の写真が何枚も飾られている。
そして人々は気付いていない。この戦争の裏で、時間を超えた戦いが既に始まっていることを。
由里は届けられた手紙を何度も読み返していた。そこには、「由里、そしてこれから生まれてくる自分たちの子供の未来を守る」という言葉だけが記されている。
そして航は、10月4日に生まれた。
「お母さんは強いね」
見舞いに来た友人はそう言った。「一人で育てるって決めたの?」
由里はただ微笑んで頷いた。夫の突然の失踪。家族からは再婚を勧められることもある。しかし、由里は息子を育てることを選んだ。
数年後。息子は父親そっくりに育った。プログラミングの才能、そして何より、強い正義感も。
そして2042年、アジアで最初の戦火が上がった。
高校を卒業したばかりの航は、すでに父親を超える優秀なプログラマーになっていた。
そんなある日、航の元に赤紙が届いた時、由里は何も言えなかった。ただ、強く息子を抱きしめた。
2045年8月15日の朝。
テレビは戦況を伝えている。新型AI兵器の制御システムの異常を直し多くの命を救った一人の戦死した若い兵士を大々的に報道している。そこには航の名前があった。
その日の夕暮れ、由里は六畳間に座っていた。航の成長を見守ってきた部屋。壁には航の写真が何枚も飾られている。
そして人々は気付いていない。この戦争の裏で、時間を超えた戦いが既に始まっていることを。