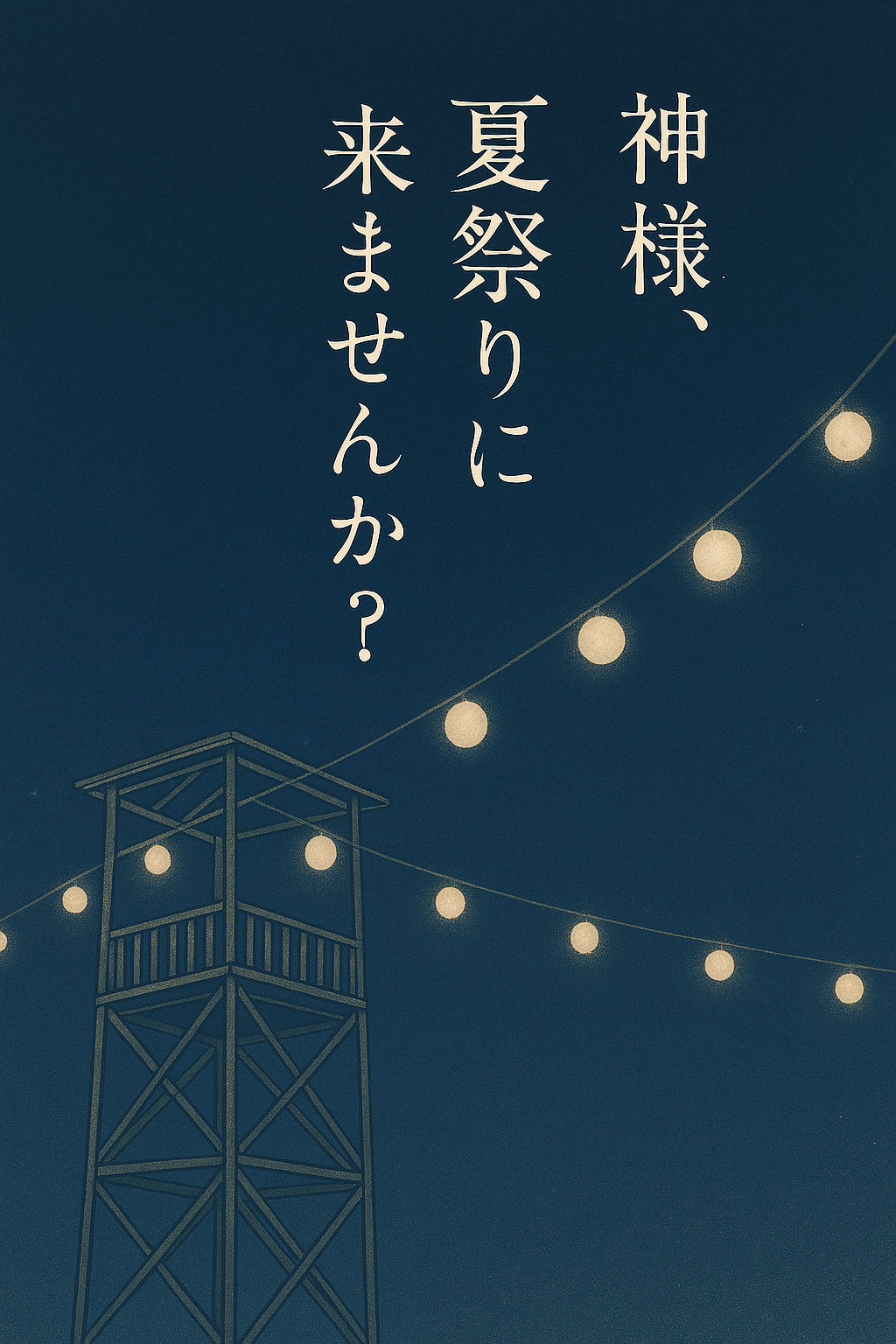化生たちの慕情
ー/ー 神が零落すれば化生となり、崇められた化生は神となる。化生に愛された者は、果たして幸福であったのか。いや、そも、いったい誰がそれを量れるというのか。
屋根が崩れかけ、湿気た空気の満ちる長屋に、シトシトと五月雨が降っている。部屋に響くは三味線の音締め。弥島屋の下級遊女———紫の向かいでは、遣り手の銀が腕を組んで座っている。その針のような眼光を浴びながら、紫は震える撥で弦を打つ。すると、不吉な音を立てて弦が切れた。
「そんなんで客が付くと思ってんのかい!」
そう言って立ち上がると、銀はその勢いのまま紫を殴る。か細い声を上げ、頬に触れようとした紫の小指から、糸のように血が滴った。
「あんたを見世に連れてきたのが、女将じゃなければ追い出せるのにねぇ。顔に痣があるうえに、愛想もなけりゃあ芸もない。まったく、使いもんにならないよ」
銀の怒号と一緒に、骨まで濡らすような空気が、頬の痣を舐める。じっと銀を見据える、紫の瞳に色はない。
十代の女にしては覇気がなく、亡霊のような出立ちの紫は、さしずめ波間を漂う海月といったところだろう。
流されるまま見世に来て、流されるまま遊女になり、流されるまま三味線を弾いている。けれど、男に愛想を振り撒かないことだけは、紫の意思から来るものだった。
「あたしは客を取りたくない、男に媚びてどうするの……」
最後まで言い終わらぬうちに、銀が紫の頬を殴った。
「あんた、まさか 間夫がいるんじゃないだろうね。湯屋の裏の細道に、お前が入ってくのを見たってやつがいるんだ」
「間夫なんかいない。あたしはただ、高善神社にお参りしているだけ……」
「あそこなら、ずいぶん前に火事で焼けただろう。そんなとこに願掛けして何になる。馬鹿なこと言ってるんじゃないよ」
紫の眼前で、銀がもう一度手を振り上げる。直ぐに来るであろう痛みに耐えるため、紫は目を瞑る。
弥島屋に来てから、何度も繰り返された光景だ。今更何も思わない。
紫は思考を愛する男の元へ飛ばす。頬を殴られようとも、罵詈雑言が降り注ごうとも、男のことを思うだけで、痛みも恐怖も全て消え去り、愛する男の笑みだけが残る。紫にとって、男はこの世の全てだった。痣のある顔を綺麗だと言い、殴られて怪我をすれば、その傷に労わるように触れてくれる。
「間夫は罪だと言っただろう!」
殴る力は強く、叱責は終わらない。銀の怒りに比例して、紫の中には男の記憶が広がり続けた。
男に初めて会ったのは、死者のように静かな雨の降る日だった。
湯屋を出た紫は、火事になったことを知らないまま、雨宿りのために高善神社へ向かった。苔むした参道は薄暗く、きな臭い空気が纏わりつくようだった。煤けた鳥居を潜って直ぐ、かろうじて形を留める社殿の前に、その男は座っていた。若い男だった。金の鯉が泳ぐような華やかで歌舞いた衣をまとい、髷は結っておらず、束ねた長髪が風に靡いている。顔立ちも美しい。だがその美しさにには、どこか影と怪しさがあった。
湯屋を出た紫は、火事になったことを知らないまま、雨宿りのために高善神社へ向かった。苔むした参道は薄暗く、きな臭い空気が纏わりつくようだった。煤けた鳥居を潜って直ぐ、かろうじて形を留める社殿の前に、その男は座っていた。若い男だった。金の鯉が泳ぐような華やかで歌舞いた衣をまとい、髷は結っておらず、束ねた長髪が風に靡いている。顔立ちも美しい。だがその美しさにには、どこか影と怪しさがあった。
「雨宿りですか」
紫の声に男が顔を上げる。柔らかな視線が紫の瞼に留まった。
「いいや、人を待っている」
「こんな場所で?」
「ああ、此処じゃなければ意味がないのさ」
男はそう言うと、眩しいものでも見るように目を細めて、
「通りの占い屋に、助介ってやつがいてな。あいつが俺を見て言うんだ。高善神社に待ち人来たり。顔に痣のある女なり。女は孤独を癒し愛をなす。幾つもの試練を越え、痛みを越え、互いの想いが結びつきしとき、常しえの愛を手に入れる———庄助の天眼は何でも見透かせるって評判だが、あんたは信じるかい」
そう問うてきた。
「さあ、どうでしょうね」
紫の脈打つ心臓の音を掻き消すかの如く、雨が強さを増す。煙る視界の向こうに男の顔が見える。辛うじて焼け残った屋根の下、段木に腰掛けた男は薄く笑うと、その白い手で隣を示した。
「此処で会うのも何かの縁。少し話さないか」
弥島屋へ帰るのを億劫に思っていた紫は隣に腰を下ろす。更に強さを増す雨の中、男は九十九と名乗った。その後何を話したのか覚えていない。気がつくと九十九の指が紫の頬を撫でていた。
「さあ、どうでしょうね」
紫の脈打つ心臓の音を掻き消すかの如く、雨が強さを増す。煙る視界の向こうに男の顔が見える。辛うじて焼け残った屋根の下、段木に腰掛けた男は薄く笑うと、その白い手で隣を示した。
「此処で会うのも何かの縁。少し話さないか」
弥島屋へ帰るのを億劫に思っていた紫は隣に腰を下ろす。更に強さを増す雨の中、男は九十九と名乗った。その後何を話したのか覚えていない。気がつくと九十九の指が紫の頬を撫でていた。
「俺は神を信じていないが、お前の顔を見ていると、神がその美貌に嫉妬して、痣をつけたような気がしてくる」
指を伝う熱に、己の火照りが混じる。
「何故だろうな。この痣も、その美しい明眸も、丹花の唇も、全てをものにしたい」
「あんた、変わった人だね」
左頬に浮かぶ赤黒い痣は、紫が生まれた時からそこにあった。
鏡に映る顔を見るたびに、心が虚ろなものへと変わっていく。己へ向かう嘲笑も好奇の眼差しも全て受け入れ、諦めの中で生きていた。そうすれば傷つくことはない。紫は他人に執着しないよう注意を払っていればよかった。
しかし九十九は違う。散々嗤われ病の類だと恐れられた痣に、躊躇うことなく触れている。やがてその体温は、激しく脈打つ血潮となって虚な心へ流れ込む。この男なら全てを差し出せるような、醜い自分を受け入れてくれるような、そんな淡い期待が身体中を駆け巡った。
「明日も此処に来てくれるかい」
紫の潤んだ目元を拭った小指が、目の前に差し出される。
男にしては細く、肌理の整った肌をしていた。恐る恐る指を絡めると、身体が一気に熱くなる。あれから何度指切りをして、逢瀬を重ねたのだろう。
次に気づいたときには銀の姿はなくなり、小指から流れた血溜まりが畳に広がるばかりであった。
紫は心を閉ざしたまま、姉女郎の横で三味線を弾き、客の相手をして床に着く。そしてまた気だるい朝日が迎えに来る。何もかも同じことの繰り返しだと思っていた。けれど、銀に叱られた翌朝。紫は今まで経験したことのない顔の痛みで目を覚ます。
朦朧とする意識の中で鏡を覗くと、顔の半分が爛れていた。額から瞼、頬の痣の上に掛けて、ザラメのような赤い斑点が浮いている。指で触れた肌に熱い痛みが走る。
ああ、これはきっと神様の仕業だと、紫は思う。
自分のような醜い女が、九十九のような美しい男に慕われて許される訳がない。深く息を吐いて鏡に顔を近付ける。そこには恋に憑かれた女がいた。爛れた左目はもう殆ど見えていないというのに、顔が痛くて仕方がないというのに、こうなってしまったのは九十九の言葉が真実だからだと、彼に愛されている証拠なのだと、妙な喜びが湧き上がってくる。
一方的に想いを寄せるのが恋だとすれば、想いが結びついた今を愛と呼ぶのではないか。恋愛とは常に、こうして痛みを伴うものなのか……。
紫は九十九との約束の時間が迫ると、近くにあった帯を頭上に被り、足早に長屋を出た。外には針のように細い雨が降っていた。会いたい気持ちが先走り、強く傘の柄を握ると小指から膿が滲んだ。三味線の弦が引き裂いていった傷は、治るどころか悪化しているように見える。しかし、紫は歩みを止めなかった。酷く痛む顔も膿んだ小指も、九十九との約束を破る理由にはならない。
「おい、そこの女」
紫は振り返る。藍色の着流しの男が、訝しげに瞼を細めている。
「‥‥あたしに何か御用ですか」
「あんた、妙なもんに憑かれてるな。最近変わったことはないか」
「いいえ、特にありません。先を急いでいるので」
紫が会釈をして歩き出すと、男が背後から肩を摑んだ。
「いいから話を聞け。あんたこのままだと死ぬぞ」
「離してください。さっきから何なんです」
紫は男からすっと距離を取った。
「よく見れば、顔も爛れてるじゃねぇか。いやそれよりも、そんなに急いでどこへ行くつもりだ」
「あなたには関係ないでしょう」
「‥‥ああ、確かにそうだ。俺には関係ない。だが、天眼を持っちまった手前、あんたを見捨てるわけにもいかねぇ」
男は不機嫌そうに腕を組んだかと思うと、紫の顔を覗き込む。その目がこちらを睨んだ気がして、紫は思わず目を逸らせた。
「高善神社か。あんな煤けた場所で何をしてる」
男は低い声で言って眉間に皺を寄せた。紫は俯いたまま男を見ようともしない。
「いいかよく聞け。あそこに祀られているは付喪神は、古い道具に宿ると言われていた。火事になる前は折れた櫛や割れた茶碗なんかを供養していたが、今は違う。火事や天災があった場所は魍魎が溜まるもんだ。あんたが熱心に手を合わせる相手が、神だという保証はない」
しかし、男の説得は雨音に紛れるばかりであった。
紫は、九十九、と口の中で名を転がしたものの、引き返そうとはしなかった。九十九の正体が人間であろうがなかろうが、そんなことはどうでもいい。彼を失うより怖いものなどない。
「だからなんだというの。人は得体の知れないものを怖がるけれど、あたしは妖怪や幽霊より、平気な顔をして他人を傷つける人間の方が怖いよ」
紫はそう言うと高善神社へ歩みを進めた。少しずつ遠のいて行く背中に、男は声を張り上げる。
「おい、まだ話は終わってない。あんたに憑いている男は」
そのまま後を追おうとしたが、人並みに紛れる姿は他人を拒むような冷たさがあった。男は踏み出した足を戻す。
「俺の名は庄助。通りで占い屋をやっている。気が変わったら店に来い」
結局庄助の忠告は紫の鼓膜を震わせることはなかった。いつも通り高善神社の軒下で九十九と落ち合い、爛れた顔を隠しながらも話しに花を咲かせた。この時間だけが唯一、紫の安らげる時間だった。
「紫、怪我をしているのか」
九十九の視線から逃れるように、紫は左手を背中へ隠した。
「いや、大した傷じゃないよ」
「どれ見せてみろ」
紫が黙っていると、九十九は腕を伸ばし、背後から紫の腕を引き出した。僅かに力を入れたものの、目の前に迫る広い胸と、腕の感触には抗えなかった。九十九は紫の手を膝に持ってくると、その小指を見つめる。
「これは相当痛むだろう。可哀想に」
「怪我なんかどうでも良い。あたしの指がどうなろうと、顔が爛れようと、誰も気にしちゃいないんだから」
自嘲気味な紫の態度に九十九は表情を曇らせた。それから小さくため息をつくと、その薄い唇を紫の小指に押し当てる。
「やめて」
傷口が何かに反応するように疼いた。九十九の口の中に、己の指が吸い込まれる様をみていると、身体の芯が溶けていくようだった。
「俺の愛でるものを、どうでも良いなんて言ってほしくない」
九十九の瞳が妖しく光る。紫はその危うさに満ちた煌めきを心から愛しく思う。
何度も逢瀬を重ねるたびに、想いの強さは紫の手に余るほどになってきた。その慕情は、座敷の席でも顔を出し、上の空で三味線を弾く紫を、姉女郎が怒鳴りつける事態にまで及んだ。客を前にしても、銀の叱責を浴びていても、紫の頭は九十九が充している。眼を閉じれば、あの柔らかな声が蘇る。その生まれて初めての感情は、はたから見れば『狂』の域に達していようとも、紫は『純真』だった。口づけられた小指が痛もうと、傷口が腐りはじめようと、顔の爛れが首元へ広がろうとも、童子のような笑みを浮かべて、頬や小指をなぞる。もう以前の紫は居ない。そこにいるのは、恋に生きる女だった。
「あんたの水揚げ、嶋田屋の旦那に決まったよ」
縦皺の刻まれた唇の端から、銀は紫煙をゆるく吐き出した。嶋田屋は姉女郎の客だった。つい数日前、爛れた顔で三味線を弾いた記憶はあるが、水揚げを申し出る理由は思い当たらない。何かの間違いだと思った。煙管を咥え、恨めしそうに視線を遣る銀を見つめ返しても、やはり実感が湧いてこない。
「そんでね、他の客を取られる前に身請けしたいんだとさ。あんたみたいな病み女が人気遊女でもあるまいし、急ぐこたァないだろって言ったんだけどねぇ。どうにも聞きゃしない。病の女を娶りたいなんて、好き者にもほどがあるよ」
「……嫌だと言ったら」
紫が煙から逃れるように視線を伏せると、銀は苛立ったように左手を振り上げた。ぱん、と乾いた音が部屋に弾け、紫の頬に激しい痛みが走る。
「断れるわけないだろうが。あんたみたいな汚れた女、座敷にいても金にならないんだよ。さっさと身請けされちまいな」
銀が去ったあと、紫は噛み締めた唇の痛みを堪えながら、爛れた頬に触れた。夏とは思えぬ冷えが部屋に漂い、拳を握りしめる手先は、もはや自分のものではないようだった。辛うじて形を保つ小指に触れると、昨日よりさらに感覚が失われている。
――これじゃあ、指切りもできないね。
呟いた声は、座敷から漏れる遊女たちの笑い声に吸い込まれた。あと何度、九十九と約束を交わせるのだろう。
地面に伸びた影を踏みながら、高善神社の参道を進む。鳥居の向こう、段木に腰掛けた九十九が手を振った。その無邪気な笑みに胸がざわめく。間夫の恋など、長く続くものではない。ましてや、身請けが決まったとなればなおのことだ。今日ですべてを話して終わらせるべきなのか。それが、自分にできるのか。
「水揚げが決まったの。嶋田屋って人……あたしを身請けしたいんだって」
その言葉が終わるより早く、九十九は紫の腕を引き、社殿の奥へ押し入った。閉められた扉の向こうでは、舌が絡む湿った音と荒い息遣いばかりが響く。
「九十九さん。もう、離して」
抱きすくめられた苦しさに、紫は呻いた。しかし九十九は逃がそうとしなかった。腰に回した腕は、紫が何処かへ行ってしまうのを拒むかのように痩せた腰に食い込んだ。
「誰かのものになるくらいなら……いっそ、このまま死んでしまってもいいかもしれないね」
「……あたしを殺すつもりなの?」
「冗談さ」
言葉とは裏腹に、九十九の声音は掠れていた。その伏せられた瞳に、紫は自分の行く末を見たような気がした。愛していない男に瓜を破られ一生を共にする日々は、愛した男に殺される瞬間よりも、ずっと悲しい結末が待っているだろう。
ならば一層のこと、ひと思いに殺してくれないか。喉に引っかかった声は、頭を撫でる九十九の感触によって行き場を無くした。愛してやまない彼の手を汚してはならないと、紫は言葉を飲み込む代わりに、九十九の胸に頬を預ける。けれど、心臓の鼓動は聞こえなかった。
朝焼けが東の空に滲み始めた頃。紫は忙しない足音で目を覚ます。布団に寝転んだまま、じっと耳を澄ませると、遠くの方で遊女や銀の慌てた声が聞こえた。
何事かと起き上がった瞬間、どろりとした感触が喉を伝った。唾液とも痰ともつかない臭いがした。にたまらず咳をすると、口を覆った手に鮮血が飛び散る。最近此処らで流行っている病は血を吐くものだと聞いたので、その類だろうと思ったのだが、己の手を見て驚愕する。肌を染める血液に混じって、歯と思わしきものが転がっていたのだ。
震える舌先で歯の一本一本をなぞろうとしたが、戸の外に人の気配がして、紫は慌てて口を拭った。
「嶋田屋さんが殺されたよ」
青褪めた顔で銀が言った。
「湯屋の前の通りで倒れてたそうだよ。首と、いちもつが切り取られてるって話だ。あんた、心当たりは?」
「まだ……嶋田屋さんは、そこに」
銀が頷くのを見届けると、紫は身支度もそこそこに長屋を出た。いつまでも狭霧の晴れない朝だった。不吉に煙る通りを走りながら、紫は九十九のことを考える。嶋田屋に恨みを持った人間の仕業なら、殺すところまでは理解できても、男性器を切り取る必要はない。九十九に嶋田屋のことを話したのは昨日、もしや、自分が身請けされることを嫌がって、嶋田屋を殺したのだろうか。
湯屋の前に差し掛かる。薄ぼんやりとした視界の向こうに、茣蓙のかけられた死体があった。べっとりと血がついた茣蓙の横から、恰幅の良い腕が伸びていて、その指先に無数の青蝿が止まっている。
紫は死体そのものより、嶋田屋を手に掛けたであろう九十九が捕まってしまう方が怖かった。
「また会ったな」
振り返ると、藍の着流しに鋭い眼光を持つ男──庄助が立っていた。
「わかっただろ。あんたの好いた男は、人の皮を被った化け物だ」
「証拠もないのに……どうしてそんなこと言えるの」
「俺の天眼は嘘をつかない」
青みがかった瞳を指し示す。鼻で笑おうとした紫の脳裏に、九十九の言葉が蘇る。
『高善神社に待ち人来たり……顔に痣のある女なり……』
紫は庄助を睨む。
「この言葉、あの人に授けたのは、あんたなんじゃないの」
「馬鹿言うな。そんな相談を受けた覚えはない。騙されたんだ」
庄助に言われ、もう一度記憶を辿るも、疑わしい点が浮かび上がるばかりだった。人が来るのを待ち構えていたところに、たまたま自分が現れて、たまたま痣があったが故に、気を持たせるようなことを言ったのだとしたら。
庄助の苦い顔が、紫の心に疑念を植えつけた。
「肉吸いって妖怪を知ってるか」
「知らない」
「甘い言葉で人間を誑かして交わり、触れた場所から正気を吸い取る。肉吸いに魅入られた者は身体の至る所を腐らせて死ぬ。その目も指も口も、肉吸いの仕業だろう」
それでも紫は首を振り続ける。九十九は優しい男だった。除け者にされた自分を受け入れてくれる唯一の存在だった。目を閉じると頬に触れた美しい顔が思い出される。
「初めて見たとき、言いそびれたがな。あんたに憑いていた男は、眼球と小指を持っていたよ。まるで宝物みたいにな」
「九十九さん……」
その名を呼ぶだけで、紫は現実から目を逸らすことが出来た。愛する男の正体がなんであろうと、それが例え自分の身を滅ぼす者だったとしても、愛した相手だ。庄助と話して初めて、抗い難い想いに気付いた。
「どうでもいいよそんなこと。あたしはあの人が好きなんだ。あの人が望むなら、この眼も指も歯も全部あげるよ」
やつれた顔を撫で、薄らと頬を染める紫の振る舞いに、庄助は一瞬目を瞠った。我を忘れて情念を燃やす紫を見て、諦めることしかできなかった。恋に生きる女の輝きは、それほどまでに眩しいものだ。
「そのせいで自分が死ぬことになってもかい」
紫は微笑みを返すと庄助に背を向けて、高善神社の方へと歩き出す。庄助はただ、小さくなっていく背中を見送ることしかできなかった。
太陽に醒まされるように、歩みを進める紫の影をくっきりと映し出す。しかし、一歩踏み出すたびに突如として現れた焦りが、紫の心に影を落とした。病に侵された遊女は客を取れない。稼ぎがないからには食事も貰えず、ただひたすら暗い部屋で死を待つのみだ。もう見世に戻る理由は無い。どうせ死ぬのなら、骨の髄まで好いた男に愛されて死にたい。そんな想いが通じたのか、高善神社の段木には九十九が座っていた。紫はいつもの調子で駆け寄ると、静かに隣へ座る。
「嶋田屋が死んだんだってな」
紫の顔を見ないまま、呟くようにして九十九が言った。
「ああ、さっき仏さんを見てきたよ。首といちもつを切られていたそうじゃないか。酷いことする人もいたものだね」
「俺は当然だと思うね。あいつは病の女ばかり買って嬲り、死ねば病死で済ませる男だった」
その言葉で、紫の疑念が形を持った気がした。九十九は紫に一瞥をくれ、焼け落ちた楠木に視線を移す。唐突に吹いた風がざあざあと葉を揺らす中、紫は微かに息を吐き、腐った小指を包むようにして握った。
「あんたが」
風が止むのを待ち、紫が小さく言葉を発した。
「なんだ」
「九十九さんが嶋田屋さんを殺したの」
自分の全てを欲していたからこそ、嶋田屋を殺したのか。それとも人を喰う妖怪の性がそうさせたのか。何も答えないまま、九十九は紫の手を取り、膿んだ小指に口付ける。
「殺したと言ったら逃げるかい。それとも、罪を一緒に背負って逃げるか」
「あたしは、九十九さんが何者でもいい。好きな場所へ連れてって」
次の瞬間、強く抱きすくめられ、社殿の影に引き込まれた。
「九十九さんに、あたしの全部をあげるよ」
やっと言えた言葉は、吐息と衣擦れの音に混じって消えた。痺れるような甘い疼きが全身を駆け巡り、強引な口付けと愛撫の応酬に流されていると、自分が女であることを実感する。
あんたが好いている男は人間の皮を被った化け物だ。
庄助の声がよみがえる。九十九が人を喰う化け物だとしたら、紫は慕情に命を懸ける化け物だ。仕事を捨て、生活を捨て、男に全てを差し出して、人の道を外れた。心から愛しい男に出会った瞬間から、紫の人生は決まっていたのだろう。破滅を約束されていたのだろう。
その日の未明、嫌な胸騒ぎを覚えた庄助が、月明かりを頼りに高善神社へ行くと、そこには変わり果てた紫の死体が転がり、鼻を覆いたくなるほどの腐臭が漂っていた。陰鬱な闇の中、唐突に気配を感じて振り返る。
「お前が殺したんだな」
そこに立っていたのは九十九だった。夜に溶けてしまいそうな瞳で、じっと庄助を見ている。
「好いた女と添い遂げるためなら、手段を選んでいられないだろう」
「人間を肉としか思っていないくせに」
「あんたは俺に心がないと思ってるのか」
九十九が視線を上げた先には、煌々と光る満月があった。その美しい横顔に、庄助は得体の知れない恐怖を覚える。九十九の唇がゆっくり動いた。
「紫は美しかった。その美しい女を虐げる者が憎かった。この度し難い気持ちを、人はなんと呼ぶのだろうな」
そう言い残し、九十九は闇の中へ消えた。我に帰って辺りを見回すと、臭気を放っていた紫の死体も無くなっている。
「‥‥化生のものも慕情を抱くのだな」
静けさに満ちた境内で庄助は呟いた。
化生に愛された者は、果たして幸福であったのか。いや、そも、いったい誰がそれを量れるというのか。
紫は死体そのものより、嶋田屋を手に掛けたであろう九十九が捕まってしまう方が怖かった。
「また会ったな」
振り返ると、藍の着流しに鋭い眼光を持つ男──庄助が立っていた。
「わかっただろ。あんたの好いた男は、人の皮を被った化け物だ」
「証拠もないのに……どうしてそんなこと言えるの」
「俺の天眼は嘘をつかない」
青みがかった瞳を指し示す。鼻で笑おうとした紫の脳裏に、九十九の言葉が蘇る。
『高善神社に待ち人来たり……顔に痣のある女なり……』
紫は庄助を睨む。
「この言葉、あの人に授けたのは、あんたなんじゃないの」
「馬鹿言うな。そんな相談を受けた覚えはない。騙されたんだ」
庄助に言われ、もう一度記憶を辿るも、疑わしい点が浮かび上がるばかりだった。人が来るのを待ち構えていたところに、たまたま自分が現れて、たまたま痣があったが故に、気を持たせるようなことを言ったのだとしたら。
庄助の苦い顔が、紫の心に疑念を植えつけた。
「肉吸いって妖怪を知ってるか」
「知らない」
「甘い言葉で人間を誑かして交わり、触れた場所から正気を吸い取る。肉吸いに魅入られた者は身体の至る所を腐らせて死ぬ。その目も指も口も、肉吸いの仕業だろう」
それでも紫は首を振り続ける。九十九は優しい男だった。除け者にされた自分を受け入れてくれる唯一の存在だった。目を閉じると頬に触れた美しい顔が思い出される。
「初めて見たとき、言いそびれたがな。あんたに憑いていた男は、眼球と小指を持っていたよ。まるで宝物みたいにな」
「九十九さん……」
その名を呼ぶだけで、紫は現実から目を逸らすことが出来た。愛する男の正体がなんであろうと、それが例え自分の身を滅ぼす者だったとしても、愛した相手だ。庄助と話して初めて、抗い難い想いに気付いた。
「どうでもいいよそんなこと。あたしはあの人が好きなんだ。あの人が望むなら、この眼も指も歯も全部あげるよ」
やつれた顔を撫で、薄らと頬を染める紫の振る舞いに、庄助は一瞬目を瞠った。我を忘れて情念を燃やす紫を見て、諦めることしかできなかった。恋に生きる女の輝きは、それほどまでに眩しいものだ。
「そのせいで自分が死ぬことになってもかい」
紫は微笑みを返すと庄助に背を向けて、高善神社の方へと歩き出す。庄助はただ、小さくなっていく背中を見送ることしかできなかった。
太陽に醒まされるように、歩みを進める紫の影をくっきりと映し出す。しかし、一歩踏み出すたびに突如として現れた焦りが、紫の心に影を落とした。病に侵された遊女は客を取れない。稼ぎがないからには食事も貰えず、ただひたすら暗い部屋で死を待つのみだ。もう見世に戻る理由は無い。どうせ死ぬのなら、骨の髄まで好いた男に愛されて死にたい。そんな想いが通じたのか、高善神社の段木には九十九が座っていた。紫はいつもの調子で駆け寄ると、静かに隣へ座る。
「嶋田屋が死んだんだってな」
紫の顔を見ないまま、呟くようにして九十九が言った。
「ああ、さっき仏さんを見てきたよ。首といちもつを切られていたそうじゃないか。酷いことする人もいたものだね」
「俺は当然だと思うね。あいつは病の女ばかり買って嬲り、死ねば病死で済ませる男だった」
その言葉で、紫の疑念が形を持った気がした。九十九は紫に一瞥をくれ、焼け落ちた楠木に視線を移す。唐突に吹いた風がざあざあと葉を揺らす中、紫は微かに息を吐き、腐った小指を包むようにして握った。
「あんたが」
風が止むのを待ち、紫が小さく言葉を発した。
「なんだ」
「九十九さんが嶋田屋さんを殺したの」
自分の全てを欲していたからこそ、嶋田屋を殺したのか。それとも人を喰う妖怪の性がそうさせたのか。何も答えないまま、九十九は紫の手を取り、膿んだ小指に口付ける。
「殺したと言ったら逃げるかい。それとも、罪を一緒に背負って逃げるか」
「あたしは、九十九さんが何者でもいい。好きな場所へ連れてって」
次の瞬間、強く抱きすくめられ、社殿の影に引き込まれた。
「九十九さんに、あたしの全部をあげるよ」
やっと言えた言葉は、吐息と衣擦れの音に混じって消えた。痺れるような甘い疼きが全身を駆け巡り、強引な口付けと愛撫の応酬に流されていると、自分が女であることを実感する。
あんたが好いている男は人間の皮を被った化け物だ。
庄助の声がよみがえる。九十九が人を喰う化け物だとしたら、紫は慕情に命を懸ける化け物だ。仕事を捨て、生活を捨て、男に全てを差し出して、人の道を外れた。心から愛しい男に出会った瞬間から、紫の人生は決まっていたのだろう。破滅を約束されていたのだろう。
その日の未明、嫌な胸騒ぎを覚えた庄助が、月明かりを頼りに高善神社へ行くと、そこには変わり果てた紫の死体が転がり、鼻を覆いたくなるほどの腐臭が漂っていた。陰鬱な闇の中、唐突に気配を感じて振り返る。
「お前が殺したんだな」
そこに立っていたのは九十九だった。夜に溶けてしまいそうな瞳で、じっと庄助を見ている。
「好いた女と添い遂げるためなら、手段を選んでいられないだろう」
「人間を肉としか思っていないくせに」
「あんたは俺に心がないと思ってるのか」
九十九が視線を上げた先には、煌々と光る満月があった。その美しい横顔に、庄助は得体の知れない恐怖を覚える。九十九の唇がゆっくり動いた。
「紫は美しかった。その美しい女を虐げる者が憎かった。この度し難い気持ちを、人はなんと呼ぶのだろうな」
そう言い残し、九十九は闇の中へ消えた。我に帰って辺りを見回すと、臭気を放っていた紫の死体も無くなっている。
「‥‥化生のものも慕情を抱くのだな」
静けさに満ちた境内で庄助は呟いた。
化生に愛された者は、果たして幸福であったのか。いや、そも、いったい誰がそれを量れるというのか。
みんなのリアクション
まだリアクションはありません。最初の一歩を踏み出しましょう!
神が|零落《れいらく》すれば|化生《けしょう》となり、崇められた化生は神となる。化生に愛された者は、果たして幸福であったのか。いや、そも、いったい誰がそれを量れるというのか。
屋根が崩れかけ、湿気た空気の満ちる長屋に、シトシトと五月雨が降っている。部屋に響くは三味線の音締め。|弥島屋《やじまや》の下級遊女———紫の向かいでは、遣り手の銀が腕を組んで座っている。その針のような眼光を浴びながら、紫は震える|撥《ばち》で弦を打つ。すると、不吉な音を立てて弦が切れた。
「そんなんで客が付くと思ってんのかい!」
そう言って立ち上がると、銀はその勢いのまま紫を殴る。か細い声を上げ、頬に触れようとした紫の小指から、糸のように血が滴った。
「あんたを見世に連れてきたのが、女将じゃなければ追い出せるのにねぇ。顔に痣があるうえに、愛想もなけりゃあ芸もない。まったく、使いもんにならないよ」
銀の怒号と一緒に、骨まで濡らすような空気が、頬の痣を舐める。じっと銀を見据える、紫の瞳に色はない。
十代の女にしては覇気がなく、亡霊のような出立ちの紫は、さしずめ波間を漂う海月といったところだろう。
流されるまま見世に来て、流されるまま遊女になり、流されるまま三味線を弾いている。けれど、男に愛想を振り撒かないことだけは、紫の意思から来るものだった。
「あたしは客を取りたくない、男に媚びてどうするの……」
最後まで言い終わらぬうちに、銀が紫の頬を殴った。
「あんた、まさか |間夫《まぶ》がいるんじゃないだろうね。湯屋の裏の細道に、お前が入ってくのを見たってやつがいるんだ」
「間夫なんかいない。あたしはただ、|高善《こうぜん》神社にお参りしているだけ……」
「あそこなら、ずいぶん前に火事で焼けただろう。そんなとこに願掛けして何になる。馬鹿なこと言ってるんじゃないよ」
紫の眼前で、銀がもう一度手を振り上げる。直ぐに来るであろう痛みに耐えるため、紫は目を瞑る。
弥島屋に来てから、何度も繰り返された光景だ。今更何も思わない。
紫は思考を愛する男の元へ飛ばす。頬を殴られようとも、罵詈雑言が降り注ごうとも、男のことを思うだけで、痛みも恐怖も全て消え去り、愛する男の笑みだけが残る。紫にとって、男はこの世の全てだった。痣のある顔を綺麗だと言い、殴られて怪我をすれば、その傷に労わるように触れてくれる。
「間夫は罪だと言っただろう!」
殴る力は強く、叱責は終わらない。銀の怒りに比例して、紫の中には男の記憶が広がり続けた。
男に初めて会ったのは、死者のように静かな雨の降る日だった。
湯屋を出た紫は、火事になったことを知らないまま、雨宿りのために高善神社へ向かった。苔むした参道は薄暗く、きな臭い空気が纏わりつくようだった。煤けた鳥居を潜って直ぐ、かろうじて形を留める社殿の前に、その男は座っていた。若い男だった。金の鯉が泳ぐような華やかで歌舞いた衣をまとい、髷は結っておらず、束ねた長髪が風に靡いている。顔立ちも美しい。だがその美しさにには、どこか影と怪しさがあった。
湯屋を出た紫は、火事になったことを知らないまま、雨宿りのために高善神社へ向かった。苔むした参道は薄暗く、きな臭い空気が纏わりつくようだった。煤けた鳥居を潜って直ぐ、かろうじて形を留める社殿の前に、その男は座っていた。若い男だった。金の鯉が泳ぐような華やかで歌舞いた衣をまとい、髷は結っておらず、束ねた長髪が風に靡いている。顔立ちも美しい。だがその美しさにには、どこか影と怪しさがあった。
「雨宿りですか」
紫の声に男が顔を上げる。柔らかな視線が紫の瞼に留まった。
「いいや、人を待っている」
「こんな場所で?」
「ああ、此処じゃなければ意味がないのさ」
「こんな場所で?」
「ああ、此処じゃなければ意味がないのさ」
男はそう言うと、眩しいものでも見るように目を細めて、
「通りの占い屋に、|助介《しょうすけ》ってやつがいてな。あいつが俺を見て言うんだ。高善神社に待ち人来たり。顔に痣のある女なり。女は孤独を癒し愛をなす。幾つもの試練を越え、痛みを越え、互いの想いが結びつきしとき、常しえの愛を手に入れる———庄助の天眼は何でも見透かせるって評判だが、あんたは信じるかい」
そう問うてきた。
「さあ、どうでしょうね」
紫の脈打つ心臓の音を掻き消すかの如く、雨が強さを増す。煙る視界の向こうに男の顔が見える。辛うじて焼け残った屋根の下、段木に腰掛けた男は薄く笑うと、その白い手で隣を示した。
「此処で会うのも何かの縁。少し話さないか」
弥島屋へ帰るのを億劫に思っていた紫は隣に腰を下ろす。更に強さを増す雨の中、男は|九十九《つくも》と名乗った。その後何を話したのか覚えていない。気がつくと九十九の指が紫の頬を撫でていた。
「俺は神を信じていないが、お前の顔を見ていると、神がその美貌に嫉妬して、痣をつけたような気がしてくる」
指を伝う熱に、己の火照りが混じる。
「何故だろうな。この痣も、その美しい明眸も、丹花の唇も、全てをものにしたい」
「あんた、変わった人だね」
「あんた、変わった人だね」
左頬に浮かぶ赤黒い痣は、紫が生まれた時からそこにあった。
鏡に映る顔を見るたびに、心が虚ろなものへと変わっていく。己へ向かう嘲笑も好奇の眼差しも全て受け入れ、諦めの中で生きていた。そうすれば傷つくことはない。紫は他人に執着しないよう注意を払っていればよかった。
しかし九十九は違う。散々嗤われ病の類だと恐れられた痣に、躊躇うことなく触れている。やがてその体温は、激しく脈打つ血潮となって虚な心へ流れ込む。この男なら全てを差し出せるような、醜い自分を受け入れてくれるような、そんな淡い期待が身体中を駆け巡った。
鏡に映る顔を見るたびに、心が虚ろなものへと変わっていく。己へ向かう嘲笑も好奇の眼差しも全て受け入れ、諦めの中で生きていた。そうすれば傷つくことはない。紫は他人に執着しないよう注意を払っていればよかった。
しかし九十九は違う。散々嗤われ病の類だと恐れられた痣に、躊躇うことなく触れている。やがてその体温は、激しく脈打つ血潮となって虚な心へ流れ込む。この男なら全てを差し出せるような、醜い自分を受け入れてくれるような、そんな淡い期待が身体中を駆け巡った。
「明日も此処に来てくれるかい」
紫の潤んだ目元を拭った小指が、目の前に差し出される。
男にしては細く、肌理の整った肌をしていた。恐る恐る指を絡めると、身体が一気に熱くなる。あれから何度指切りをして、逢瀬を重ねたのだろう。
男にしては細く、肌理の整った肌をしていた。恐る恐る指を絡めると、身体が一気に熱くなる。あれから何度指切りをして、逢瀬を重ねたのだろう。
次に気づいたときには銀の姿はなくなり、小指から流れた血溜まりが畳に広がるばかりであった。
夜が来れば花街は賑わう。
紫は心を閉ざしたまま、姉女郎の横で三味線を弾き、客の相手をして床に着く。そしてまた気だるい朝日が迎えに来る。何もかも同じことの繰り返しだと思っていた。けれど、銀に叱られた翌朝。紫は今まで経験したことのない顔の痛みで目を覚ます。
紫は心を閉ざしたまま、姉女郎の横で三味線を弾き、客の相手をして床に着く。そしてまた気だるい朝日が迎えに来る。何もかも同じことの繰り返しだと思っていた。けれど、銀に叱られた翌朝。紫は今まで経験したことのない顔の痛みで目を覚ます。
朦朧とする意識の中で鏡を覗くと、顔の半分が爛れていた。額から瞼、頬の痣の上に掛けて、ザラメのような赤い斑点が浮いている。指で触れた肌に熱い痛みが走る。
ああ、これはきっと神様の仕業だと、紫は思う。
自分のような醜い女が、九十九のような美しい男に慕われて許される訳がない。深く息を吐いて鏡に顔を近付ける。そこには恋に憑かれた女がいた。爛れた左目はもう殆ど見えていないというのに、顔が痛くて仕方がないというのに、こうなってしまったのは九十九の言葉が真実だからだと、彼に愛されている証拠なのだと、妙な喜びが湧き上がってくる。
一方的に想いを寄せるのが恋だとすれば、想いが結びついた今を愛と呼ぶのではないか。恋愛とは常に、こうして痛みを伴うものなのか……。
ああ、これはきっと神様の仕業だと、紫は思う。
自分のような醜い女が、九十九のような美しい男に慕われて許される訳がない。深く息を吐いて鏡に顔を近付ける。そこには恋に憑かれた女がいた。爛れた左目はもう殆ど見えていないというのに、顔が痛くて仕方がないというのに、こうなってしまったのは九十九の言葉が真実だからだと、彼に愛されている証拠なのだと、妙な喜びが湧き上がってくる。
一方的に想いを寄せるのが恋だとすれば、想いが結びついた今を愛と呼ぶのではないか。恋愛とは常に、こうして痛みを伴うものなのか……。
紫は九十九との約束の時間が迫ると、近くにあった帯を頭上に被り、足早に長屋を出た。外には針のように細い雨が降っていた。会いたい気持ちが先走り、強く傘の柄を握ると小指から膿が滲んだ。三味線の弦が引き裂いていった傷は、治るどころか悪化しているように見える。しかし、紫は歩みを止めなかった。酷く痛む顔も膿んだ小指も、九十九との約束を破る理由にはならない。
「おい、そこの女」
紫は振り返る。藍色の着流しの男が、訝しげに瞼を細めている。
「‥‥あたしに何か御用ですか」
「あんた、妙なもんに憑かれてるな。最近変わったことはないか」
「いいえ、特にありません。先を急いでいるので」
「あんた、妙なもんに憑かれてるな。最近変わったことはないか」
「いいえ、特にありません。先を急いでいるので」
紫が会釈をして歩き出すと、男が背後から肩を摑んだ。
「いいから話を聞け。あんたこのままだと死ぬぞ」
「離してください。さっきから何なんです」
「離してください。さっきから何なんです」
紫は男からすっと距離を取った。
「よく見れば、顔も爛れてるじゃねぇか。いやそれよりも、そんなに急いでどこへ行くつもりだ」
「あなたには関係ないでしょう」
「‥‥ああ、確かにそうだ。俺には関係ない。だが、天眼を持っちまった手前、あんたを見捨てるわけにもいかねぇ」
「あなたには関係ないでしょう」
「‥‥ああ、確かにそうだ。俺には関係ない。だが、天眼を持っちまった手前、あんたを見捨てるわけにもいかねぇ」
男は不機嫌そうに腕を組んだかと思うと、紫の顔を覗き込む。その目がこちらを睨んだ気がして、紫は思わず目を逸らせた。
「高善神社か。あんな煤けた場所で何をしてる」
男は低い声で言って眉間に皺を寄せた。紫は俯いたまま男を見ようともしない。
「いいかよく聞け。あそこに祀られているは|付喪神《つくもがみ》は、古い道具に宿ると言われていた。火事になる前は折れた櫛や割れた茶碗なんかを供養していたが、今は違う。火事や天災があった場所は魍魎が溜まるもんだ。あんたが熱心に手を合わせる相手が、神だという保証はない」
しかし、男の説得は雨音に紛れるばかりであった。
紫は、九十九、と口の中で名を転がしたものの、引き返そうとはしなかった。九十九の正体が人間であろうがなかろうが、そんなことはどうでもいい。彼を失うより怖いものなどない。
紫は、九十九、と口の中で名を転がしたものの、引き返そうとはしなかった。九十九の正体が人間であろうがなかろうが、そんなことはどうでもいい。彼を失うより怖いものなどない。
「だからなんだというの。人は得体の知れないものを怖がるけれど、あたしは妖怪や幽霊より、平気な顔をして他人を傷つける人間の方が怖いよ」
紫はそう言うと高善神社へ歩みを進めた。少しずつ遠のいて行く背中に、男は声を張り上げる。
「おい、まだ話は終わってない。あんたに憑いている男は」
そのまま後を追おうとしたが、人並みに紛れる姿は他人を拒むような冷たさがあった。男は踏み出した足を戻す。
「俺の名は庄助。通りで占い屋をやっている。気が変わったら店に来い」
結局庄助の忠告は紫の鼓膜を震わせることはなかった。いつも通り高善神社の軒下で九十九と落ち合い、爛れた顔を隠しながらも話しに花を咲かせた。この時間だけが唯一、紫の安らげる時間だった。
「紫、怪我をしているのか」
九十九の視線から逃れるように、紫は左手を背中へ隠した。
「いや、大した傷じゃないよ」
「どれ見せてみろ」
「どれ見せてみろ」
紫が黙っていると、九十九は腕を伸ばし、背後から紫の腕を引き出した。僅かに力を入れたものの、目の前に迫る広い胸と、腕の感触には抗えなかった。九十九は紫の手を膝に持ってくると、その小指を見つめる。
「これは相当痛むだろう。可哀想に」
「怪我なんかどうでも良い。あたしの指がどうなろうと、顔が爛れようと、誰も気にしちゃいないんだから」
「怪我なんかどうでも良い。あたしの指がどうなろうと、顔が爛れようと、誰も気にしちゃいないんだから」
自嘲気味な紫の態度に九十九は表情を曇らせた。それから小さくため息をつくと、その薄い唇を紫の小指に押し当てる。
「やめて」
傷口が何かに反応するように疼いた。九十九の口の中に、己の指が吸い込まれる様をみていると、身体の芯が溶けていくようだった。
「俺の愛でるものを、どうでも良いなんて言ってほしくない」
九十九の瞳が妖しく光る。紫はその危うさに満ちた煌めきを心から愛しく思う。
何度も逢瀬を重ねるたびに、想いの強さは紫の手に余るほどになってきた。その慕情は、座敷の席でも顔を出し、上の空で三味線を弾く紫を、姉女郎が怒鳴りつける事態にまで及んだ。客を前にしても、銀の叱責を浴びていても、紫の頭は九十九が充している。眼を閉じれば、あの柔らかな声が蘇る。その生まれて初めての感情は、はたから見れば『狂』の域に達していようとも、紫は『純真』だった。口づけられた小指が痛もうと、傷口が腐りはじめようと、顔の爛れが首元へ広がろうとも、童子のような笑みを浮かべて、頬や小指をなぞる。もう以前の紫は居ない。そこにいるのは、恋に生きる女だった。
何度も逢瀬を重ねるたびに、想いの強さは紫の手に余るほどになってきた。その慕情は、座敷の席でも顔を出し、上の空で三味線を弾く紫を、姉女郎が怒鳴りつける事態にまで及んだ。客を前にしても、銀の叱責を浴びていても、紫の頭は九十九が充している。眼を閉じれば、あの柔らかな声が蘇る。その生まれて初めての感情は、はたから見れば『狂』の域に達していようとも、紫は『純真』だった。口づけられた小指が痛もうと、傷口が腐りはじめようと、顔の爛れが首元へ広がろうとも、童子のような笑みを浮かべて、頬や小指をなぞる。もう以前の紫は居ない。そこにいるのは、恋に生きる女だった。
「あんたの水揚げ、嶋田屋の旦那に決まったよ」
縦皺の刻まれた唇の端から、銀は紫煙をゆるく吐き出した。嶋田屋は姉女郎の客だった。つい数日前、爛れた顔で三味線を弾いた記憶はあるが、水揚げを申し出る理由は思い当たらない。何かの間違いだと思った。煙管を咥え、恨めしそうに視線を遣る銀を見つめ返しても、やはり実感が湧いてこない。
「そんでね、他の客を取られる前に身請けしたいんだとさ。あんたみたいな病み女が人気遊女でもあるまいし、急ぐこたァないだろって言ったんだけどねぇ。どうにも聞きゃしない。病の女を娶りたいなんて、好き者にもほどがあるよ」
「……嫌だと言ったら」
「……嫌だと言ったら」
紫が煙から逃れるように視線を伏せると、銀は苛立ったように左手を振り上げた。ぱん、と乾いた音が部屋に弾け、紫の頬に激しい痛みが走る。
「断れるわけないだろうが。あんたみたいな汚れた女、座敷にいても金にならないんだよ。さっさと身請けされちまいな」
銀が去ったあと、紫は噛み締めた唇の痛みを堪えながら、爛れた頬に触れた。夏とは思えぬ冷えが部屋に漂い、拳を握りしめる手先は、もはや自分のものではないようだった。辛うじて形を保つ小指に触れると、昨日よりさらに感覚が失われている。
――これじゃあ、指切りもできないね。
呟いた声は、座敷から漏れる遊女たちの笑い声に吸い込まれた。あと何度、九十九と約束を交わせるのだろう。
地面に伸びた影を踏みながら、高善神社の参道を進む。鳥居の向こう、段木に腰掛けた九十九が手を振った。その無邪気な笑みに胸がざわめく。間夫の恋など、長く続くものではない。ましてや、身請けが決まったとなればなおのことだ。今日ですべてを話して終わらせるべきなのか。それが、自分にできるのか。
「水揚げが決まったの。嶋田屋って人……あたしを身請けしたいんだって」
その言葉が終わるより早く、九十九は紫の腕を引き、社殿の奥へ押し入った。閉められた扉の向こうでは、舌が絡む湿った音と荒い息遣いばかりが響く。
「九十九さん。もう、離して」
抱きすくめられた苦しさに、紫は呻いた。しかし九十九は逃がそうとしなかった。腰に回した腕は、紫が何処かへ行ってしまうのを拒むかのように痩せた腰に食い込んだ。
「誰かのものになるくらいなら……いっそ、このまま死んでしまってもいいかもしれないね」
「……あたしを殺すつもりなの?」
「冗談さ」
「……あたしを殺すつもりなの?」
「冗談さ」
言葉とは裏腹に、九十九の声音は掠れていた。その伏せられた瞳に、紫は自分の行く末を見たような気がした。愛していない男に瓜を破られ一生を共にする日々は、愛した男に殺される瞬間よりも、ずっと悲しい結末が待っているだろう。
ならば一層のこと、ひと思いに殺してくれないか。喉に引っかかった声は、頭を撫でる九十九の感触によって行き場を無くした。愛してやまない彼の手を汚してはならないと、紫は言葉を飲み込む代わりに、九十九の胸に頬を預ける。けれど、心臓の鼓動は聞こえなかった。
ならば一層のこと、ひと思いに殺してくれないか。喉に引っかかった声は、頭を撫でる九十九の感触によって行き場を無くした。愛してやまない彼の手を汚してはならないと、紫は言葉を飲み込む代わりに、九十九の胸に頬を預ける。けれど、心臓の鼓動は聞こえなかった。
朝焼けが東の空に滲み始めた頃。紫は忙しない足音で目を覚ます。布団に寝転んだまま、じっと耳を澄ませると、遠くの方で遊女や銀の慌てた声が聞こえた。
何事かと起き上がった瞬間、どろりとした感触が喉を伝った。唾液とも痰ともつかない臭いがした。にたまらず咳をすると、口を覆った手に鮮血が飛び散る。最近此処らで流行っている病は血を吐くものだと聞いたので、その類だろうと思ったのだが、己の手を見て驚愕する。肌を染める血液に混じって、歯と思わしきものが転がっていたのだ。
震える舌先で歯の一本一本をなぞろうとしたが、戸の外に人の気配がして、紫は慌てて口を拭った。
何事かと起き上がった瞬間、どろりとした感触が喉を伝った。唾液とも痰ともつかない臭いがした。にたまらず咳をすると、口を覆った手に鮮血が飛び散る。最近此処らで流行っている病は血を吐くものだと聞いたので、その類だろうと思ったのだが、己の手を見て驚愕する。肌を染める血液に混じって、歯と思わしきものが転がっていたのだ。
震える舌先で歯の一本一本をなぞろうとしたが、戸の外に人の気配がして、紫は慌てて口を拭った。
「嶋田屋さんが殺されたよ」
青褪めた顔で銀が言った。
「湯屋の前の通りで倒れてたそうだよ。首と、いちもつが切り取られてるって話だ。あんた、心当たりは?」
「まだ……嶋田屋さんは、そこに」
「まだ……嶋田屋さんは、そこに」
銀が頷くのを見届けると、紫は身支度もそこそこに長屋を出た。いつまでも狭霧の晴れない朝だった。不吉に煙る通りを走りながら、紫は九十九のことを考える。嶋田屋に恨みを持った人間の仕業なら、殺すところまでは理解できても、男性器を切り取る必要はない。九十九に嶋田屋のことを話したのは昨日、もしや、自分が身請けされることを嫌がって、嶋田屋を殺したのだろうか。
湯屋の前に差し掛かる。薄ぼんやりとした視界の向こうに、茣蓙のかけられた死体があった。べっとりと血がついた茣蓙の横から、恰幅の良い腕が伸びていて、その指先に無数の青蝿が止まっている。
紫は死体そのものより、嶋田屋を手に掛けたであろう九十九が捕まってしまう方が怖かった。
紫は死体そのものより、嶋田屋を手に掛けたであろう九十九が捕まってしまう方が怖かった。
「また会ったな」
振り返ると、藍の着流しに鋭い眼光を持つ男──庄助が立っていた。
「わかっただろ。あんたの好いた男は、人の皮を被った化け物だ」
「証拠もないのに……どうしてそんなこと言えるの」
「俺の天眼は嘘をつかない」
「証拠もないのに……どうしてそんなこと言えるの」
「俺の天眼は嘘をつかない」
青みがかった瞳を指し示す。鼻で笑おうとした紫の脳裏に、九十九の言葉が蘇る。
『高善神社に待ち人来たり……顔に痣のある女なり……』
紫は庄助を睨む。
「この言葉、あの人に授けたのは、あんたなんじゃないの」
「馬鹿言うな。そんな相談を受けた覚えはない。騙されたんだ」
「馬鹿言うな。そんな相談を受けた覚えはない。騙されたんだ」
庄助に言われ、もう一度記憶を辿るも、疑わしい点が浮かび上がるばかりだった。人が来るのを待ち構えていたところに、たまたま自分が現れて、たまたま痣があったが故に、気を持たせるようなことを言ったのだとしたら。
庄助の苦い顔が、紫の心に疑念を植えつけた。
庄助の苦い顔が、紫の心に疑念を植えつけた。
「肉吸いって妖怪を知ってるか」
「知らない」
「甘い言葉で人間を誑かして交わり、触れた場所から正気を吸い取る。肉吸いに魅入られた者は身体の至る所を腐らせて死ぬ。その目も指も口も、肉吸いの仕業だろう」
「知らない」
「甘い言葉で人間を誑かして交わり、触れた場所から正気を吸い取る。肉吸いに魅入られた者は身体の至る所を腐らせて死ぬ。その目も指も口も、肉吸いの仕業だろう」
それでも紫は首を振り続ける。九十九は優しい男だった。除け者にされた自分を受け入れてくれる唯一の存在だった。目を閉じると頬に触れた美しい顔が思い出される。
「初めて見たとき、言いそびれたがな。あんたに憑いていた男は、眼球と小指を持っていたよ。まるで宝物みたいにな」
「九十九さん……」
「九十九さん……」
その名を呼ぶだけで、紫は現実から目を逸らすことが出来た。愛する男の正体がなんであろうと、それが例え自分の身を滅ぼす者だったとしても、愛した相手だ。庄助と話して初めて、抗い難い想いに気付いた。
「どうでもいいよそんなこと。あたしはあの人が好きなんだ。あの人が望むなら、この眼も指も歯も全部あげるよ」
やつれた顔を撫で、薄らと頬を染める紫の振る舞いに、庄助は一瞬目を瞠った。我を忘れて情念を燃やす紫を見て、諦めることしかできなかった。恋に生きる女の輝きは、それほどまでに眩しいものだ。
「そのせいで自分が死ぬことになってもかい」
紫は微笑みを返すと庄助に背を向けて、高善神社の方へと歩き出す。庄助はただ、小さくなっていく背中を見送ることしかできなかった。
太陽に醒まされるように、歩みを進める紫の影をくっきりと映し出す。しかし、一歩踏み出すたびに突如として現れた焦りが、紫の心に影を落とした。病に侵された遊女は客を取れない。稼ぎがないからには食事も貰えず、ただひたすら暗い部屋で死を待つのみだ。もう見世に戻る理由は無い。どうせ死ぬのなら、骨の髄まで好いた男に愛されて死にたい。そんな想いが通じたのか、高善神社の段木には九十九が座っていた。紫はいつもの調子で駆け寄ると、静かに隣へ座る。
「嶋田屋が死んだんだってな」
紫の顔を見ないまま、呟くようにして九十九が言った。
「ああ、さっき仏さんを見てきたよ。首といちもつを切られていたそうじゃないか。酷いことする人もいたものだね」
「俺は当然だと思うね。あいつは病の女ばかり買って嬲り、死ねば病死で済ませる男だった」
「俺は当然だと思うね。あいつは病の女ばかり買って嬲り、死ねば病死で済ませる男だった」
その言葉で、紫の疑念が形を持った気がした。九十九は紫に一瞥をくれ、焼け落ちた楠木に視線を移す。唐突に吹いた風がざあざあと葉を揺らす中、紫は微かに息を吐き、腐った小指を包むようにして握った。
「あんたが」
風が止むのを待ち、紫が小さく言葉を発した。
「なんだ」
「九十九さんが嶋田屋さんを殺したの」
「九十九さんが嶋田屋さんを殺したの」
自分の全てを欲していたからこそ、嶋田屋を殺したのか。それとも人を喰う妖怪の性がそうさせたのか。何も答えないまま、九十九は紫の手を取り、膿んだ小指に口付ける。
「殺したと言ったら逃げるかい。それとも、罪を一緒に背負って逃げるか」
「あたしは、九十九さんが何者でもいい。好きな場所へ連れてって」
「あたしは、九十九さんが何者でもいい。好きな場所へ連れてって」
次の瞬間、強く抱きすくめられ、社殿の影に引き込まれた。
「九十九さんに、あたしの全部をあげるよ」
やっと言えた言葉は、吐息と衣擦れの音に混じって消えた。痺れるような甘い疼きが全身を駆け巡り、強引な口付けと愛撫の応酬に流されていると、自分が女であることを実感する。
あんたが好いている男は人間の皮を被った化け物だ。
庄助の声がよみがえる。九十九が人を喰う化け物だとしたら、紫は慕情に命を懸ける化け物だ。仕事を捨て、生活を捨て、男に全てを差し出して、人の道を外れた。心から愛しい男に出会った瞬間から、紫の人生は決まっていたのだろう。破滅を約束されていたのだろう。
その日の未明、嫌な胸騒ぎを覚えた庄助が、月明かりを頼りに高善神社へ行くと、そこには変わり果てた紫の死体が転がり、鼻を覆いたくなるほどの腐臭が漂っていた。陰鬱な闇の中、唐突に気配を感じて振り返る。
「お前が殺したんだな」
そこに立っていたのは九十九だった。夜に溶けてしまいそうな瞳で、じっと庄助を見ている。
「好いた女と添い遂げるためなら、手段を選んでいられないだろう」
「人間を肉としか思っていないくせに」
「あんたは俺に心がないと思ってるのか」
「人間を肉としか思っていないくせに」
「あんたは俺に心がないと思ってるのか」
九十九が視線を上げた先には、煌々と光る満月があった。その美しい横顔に、庄助は得体の知れない恐怖を覚える。九十九の唇がゆっくり動いた。
「紫は美しかった。その美しい女を虐げる者が憎かった。この度し難い気持ちを、人はなんと呼ぶのだろうな」
そう言い残し、九十九は闇の中へ消えた。我に帰って辺りを見回すと、臭気を放っていた紫の死体も無くなっている。
「‥‥化生のものも慕情を抱くのだな」
静けさに満ちた境内で庄助は呟いた。
化生に愛された者は、果たして幸福であったのか。いや、そも、いったい誰がそれを量れるというのか。
化生に愛された者は、果たして幸福であったのか。いや、そも、いったい誰がそれを量れるというのか。